当然といえば当然だが、恐れていたことが現実となった。
振り返ればこの一か月、腹を空かせた記憶など一秒もない。むしろ毎日、腹がはち切れんばかりに飲み食いしていたことしか思い出せない。
そのうえ、ろくに運動もせずフードファイトに勤しんでいたのだから、こうなることは想像に難くないのである。
それでもわたしは、己を信じた。
「わたしだけは違う」
「わたしは特別だ」
「わたしならば大丈夫」
そんな呪文のような根拠のない自信を頼りに、日々とてつもないボリュームの食料を体内へと送り込んでいた。
そういえば、髪の伸びるスピードがやけに速い。
こういう時は決まって、食べ物を大量に食べている。吸収しきれなかった余分な栄養が、髪の毛や爪にバンバン送られているのだろう――。
視界を塞ぐ邪魔な前髪をいじりながら、体重計をチラ見する。
(まだ乗らない。今はまだ、乗るべき時ではない)
正確には「体重計になど乗らなくとも、およその体重はわかっている」というべきか。
床に体育座りをすると後ろへ転がるのだから、腹の内側に何かが詰まっているのは間違いない。
そんな「逆・起き上がり小法師(こぼし)」の状態の人間が、痩せているはずがない。
いや、これはさすがに図々しいか。痩せているはずがないことくらい、誰もが分かっている。問題は「太っているかどうか」である。
わたしは別に、痩せたいわけではない。そんな叶わぬ夢に期待を抱くほど、若くも純情でもないからだ。
だがせめて、太りたくはない。
わたしの場合、太ったときの表現として「ぽっちゃり」は当てはまらない。その代わり、「ゴツイ」「ガタイがいい」「デカい」など、男性の肉体美を称賛するかのような形容詞が圧倒的に似合ってしまうわけで、まったく嬉しくないからだ。
そのことは否定しない。わたしの目は節穴ではないゆえに、己のフォルムが一般的な女性と比べてややガッチリしていることくらい、承知している。
だからこそ、女性らしさを失う恐れのある状態には、決して到達したくないのだ。
今に始まった話ではない。こんなことはとうの昔から分かっていたことである。
にもかかわらず、食に対して異常なほどに強欲なわたしは、餌付けをされれば皿まで舐めまわし、そうでなくとも一回で3人前の飯を食らうわけだ。
摂取カロリー分の消費活動を怠れば、それらが必然的に体重に反映されることくらい、十分すぎるほどに理解していたはずなのに――。
しかし振り返れば、この一か月間はほんとうに幸せな「フードファイト月間」だった。
横浜中華街での大量注文事件を皮切りに、たこ焼きだの、焼き小籠包と月餅だの、シフォンケーキとカステラとプリンだの、高級サーロインステーキだの、とにかく大量の食べ物を連日食べ続けた。
あげくの果てには業務用冷凍庫を購入し、次から次へと送られてくる手作り料理を保存する作戦に出た。
と思いきや、届いた料理はその日のうちに平らげてしまったため、未だに冷凍庫は本領を発揮していないのだが。
十月の後半になると、もはや満腹中枢がおかしくなってしまったのだろう。明らかに体のどの部分よりも膨らんだ胃袋をさすりながら、さらにパンやおにぎりを詰め込む「奇行」に走った。
目の前にある食べ物は、すべて片付けないと気が済まなくなったのだ。
どんなに満腹であっても、食べずにはいられないのだ。
そして本日、これは間違いなく病気だと確信する出来事があった。
友人と食事(もちろん、おごり)をしていたところ、ウエイターがやって来て、焼きたてのパンを一切れ皿に載せてくれた。
その瞬間、わたしは素手でパンを掴むとむしゃむしゃと食べきった。
すぐさま別の焼きたてパンが運ばれてきたが、それも皿に載せられた瞬間にむしり取ると、たっぷりとバターを塗りたくって瞬殺した。
この一連の動作の記憶がないのだ。
にもかかわらず、目の前のパンが消えているのだ。
これは病気としか思えない。この一か月のドカ食いトレーニングで、食べ物が置かれた瞬間に「躊躇なく口へ放り込む」癖がついてしまったのだ。
自分自身の行為とはいえ、かなりドン引きしたわたしは、帰宅後に体重計に乗ってみた。
・・・・・・。
*
今日からわたしは、欲とは無縁の人間になる。どうかしばらくの間、わたしに餌を与えないでもらいたい。
だが「どうしても!」という場合は、コッソリ渡してもらっても構わない。




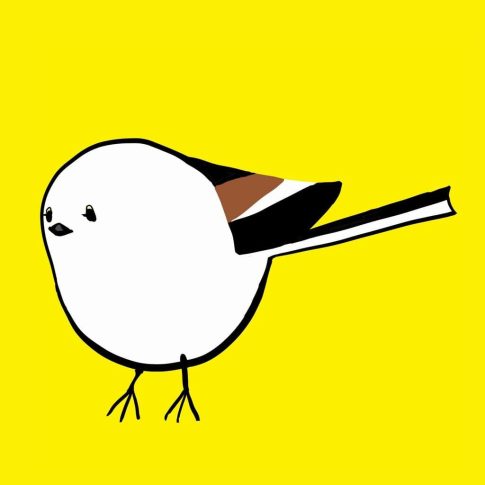



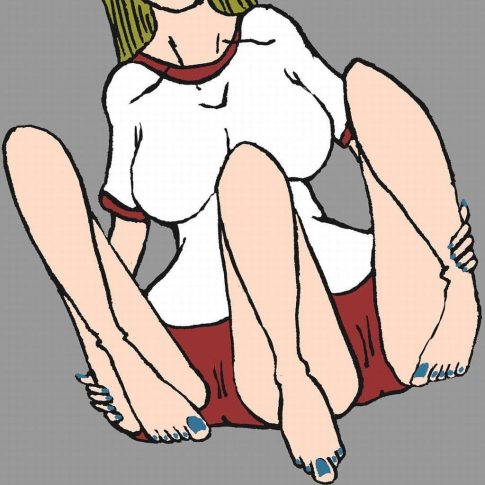












コメントを残す