(おぉ、ついに1200円台突入か・・)
来月から、東京都の最低賃金は1226円となり、今までの1163円からまたしても大幅なアップとなる。これにより、時給者の賃金について切りのいい数字・・ということで1200円で募集を行っていたり、はたまた最低賃金で雇用した後に昇給したことで1200円になったりと、「1200円」という金額で時給を設定していた企業は、来月から強制的に1226円以上に引き上げなければならない。
厚生労働省は9月5日、地方最低賃金審議会が答申した「令和7年度の地域別最低賃金の改定額」を取りまとめて発表した。それによると、改定後の全国加重平均額は1121円ということで、昨年度の1055円から確実に上昇したことが分かる。
しかも、全国加重平均額66円の引き上げというのは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額。
なお、最低賃金額が高い都道府県トップ5は、
1位・・・東京都(1226円)
2位・・・神奈川県(1225円)
3位・・・大阪府(1177円)
4位・・・埼玉県(1141円)
5位・・・千葉県/愛知県(1140円)
となっており、相変わらず東京・神奈川のツートップが3位に50円近い差をつけて独走している。
なんなら、埼玉や千葉/愛知などこれまでの東京・神奈川の最低賃金にも届かないわけで、北区や板橋区そして足立区の端っこで経営する個人店などは、「数百メートル違うだけで、この仕打ちか・・」と、辛酸をなめる思いだろう。
なお、引き上げ額が大きい都道府県を見てみると、
1位・・・熊本県(+82円)
2位・・・大分県(+81円)
3位・・・秋田県(+80円)
4位・・・青森/岩手県(+79円)
5位・・・福島県(+78円)
ということで、地方の中でも低水準である九州と東北地方が、地域間格差を縮める目的で大幅な引き上げを試みた模様。
ちなみに、なぜ地方に限ってこのような増額を行うのかというと、「同じ仕事をするのに、東京なら北区や足立区でも1300円くらいもらえるのに、おらのところじゃ1005円しかもらえねぇなんて、納得いかないべ。おら、村さ出ていく!」という、若者たちの声(?)を反映させたからだ。
こういった、地方における若年層の流出を防ぐ目的もあって、最低賃金の引き上げというのは必要な行為なのである。
念のため、最低賃金が低いトップ5も見ておくと、
1位・・・高知県(1005円)
2位・・・沖縄県(1006円)
3位・・・長崎県(1010円)
4位・・・鹿児島県(1012円)
5位・・・宮崎県(1014円)
ということで、高知県+九州南部が圧倒的な勢いで底辺を死守している。
意外だったのは、東北地方が一つもランクインしていないこと。それどころか、東北地方の最低額は青森県の1029円なので、明らかに高い金額で設定されているのだ。
とはいえ、産業構造として観光や農林水産業など賃金水準の低い職種が多かったり、人口減少や若者の都市部への流出もあったりと、人手不足が否めないこれらの地域状況を鑑みると、最低賃金の引き上げが必須となるのは理解できる。だが、大幅な上昇を強いられれば、中小零細企業の体力の限界を超えてしまうため、その負担との兼ね合いは非常に難しいところだろう。
いずれにせよ、来月からの”強制的な昇給”に頭を悩ませる事業主にとって、目下の悩みの一つは「当初は最低賃金で雇用してきた労働者を、後に昇給させたことで新たな最低賃金に近い金額設定となっていたところを、昇給させていない——つまり、仕事ができない労働者まで自動的に昇給させなければならないのは、どうも納得がいかない」という、ある種のジレンマだ。
売上が増加したわけでもないのに、なぜ仕事ができない者まで強制的に昇給させなければならないのか——悩みというより、憤りを感じる事業主は多いだろう。そしてそれは、たしかにその通りだからだ・・・。
*
政府は、全国加重平均で時給1500円を目指すと明言しているため、このままのペースでいくと2030年前後で目標に到達する見込みとなる。
とはいえ、現実的な課題・・というかリスクとして、「中小企業に対する負担の大きさ」が懸念される。大幅かつ断続的な賃上げに耐えきれず、廃業や人員削減・企業規模の縮小など、悪い方向へ進みかねないからだ。
無論、それらへの対策として政府は助成金や融資、税制などの支援を打ち出してはいるが、こちらもただ単に利用できるわけではなく先を見通した計画が必須となるため、むやみやたらに手を出せるものではない。
いずれにせよ、事業主にとっては「恐怖の」そして労働者にとっては「歓喜の」最低賃金引き上げが、目前まで迫ってきているのである。



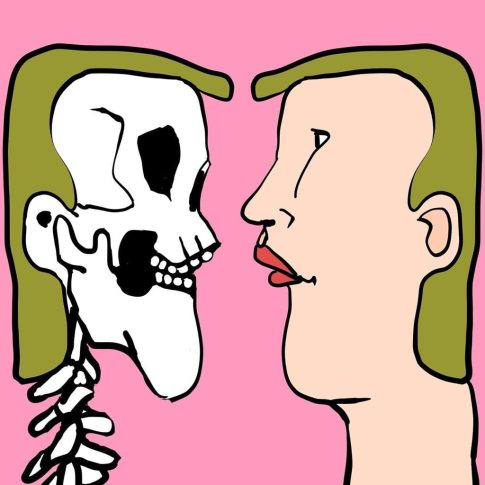
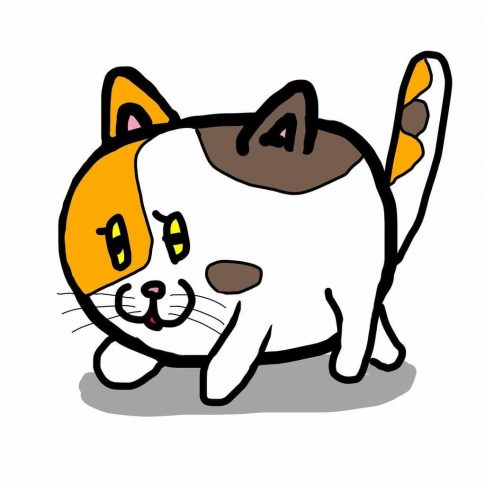

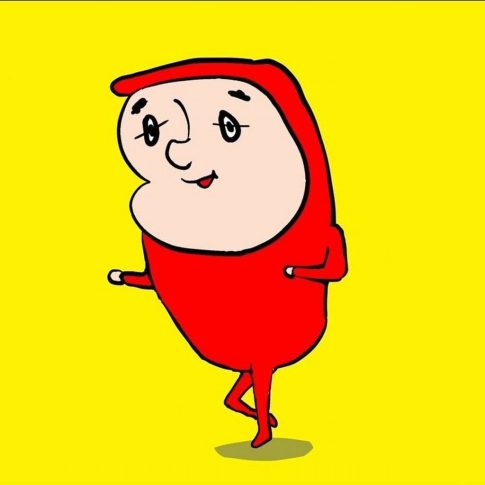


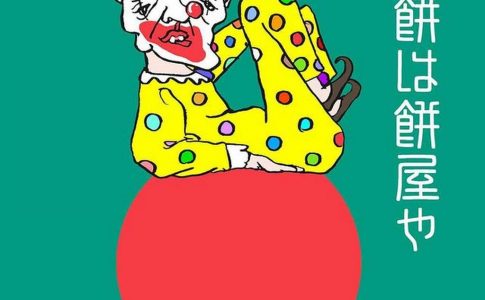
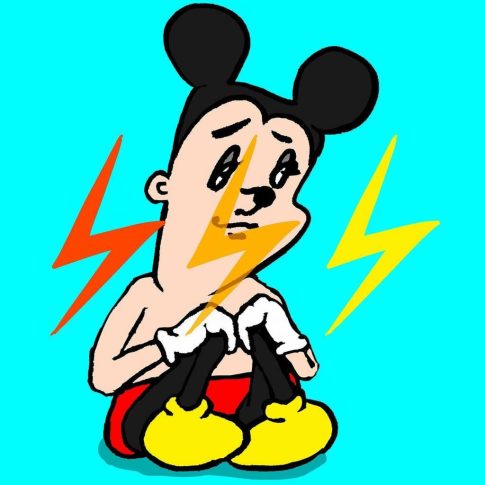










コメントを残す