大したイベントではないが、200人程度の観客が集まると聞いた。あまりに急な話だったのでイベントの詳細は忘れたが、簡単に言うと「趣味のお稽古事の発表会」のようなものだと思う。
とはいえ使用するホールはかなり立派で、収容人数は2,000人を超える。
そのオープニングセレモニーで国歌独唱があるのだが、予定していたヴォーカリストが急遽キャンセルとなり、直前に代役を立てるのが厳しいため、なぜかわたしに白羽の矢が立ったのだ。
確かにわたしはピアノを習っていたが、声楽は受験用の付け焼き刃でしか経験がない。カラオケといっても「北斗の拳の主題歌」や「残酷な天使のテーゼ」のような、パンチの効いたノリのいいアニソンばかりで、「君が代」などとは似ても似つかぬ曲調だ。
ーーなんて曲だったかな、あれは。
淡く苦い思い出がよみがえる。
音大受験の「声楽」でのこと。課題曲が3曲あり、内訳は日本語、イタリア語、ドイツ語の3つだった。イタリア語とドイツ語はメロディーが細かく散りばめられているので、わりと歌いやすい。しかし日本語の歌は、言葉の数も少なければメロデイーも微妙で、とても歌いにくい。
わたしはピアノ科を受験するので、正直、声楽はおまけだと思っていた。とりあえず楽譜の指示通りに歌いきればいいと。
そこで、最も苦手な「日本語の歌」を中心にレッスンを重ねた。先生は、歌詞の意味を考えろだの景色を思い浮かべながら伝えるように歌えだの、無理な注文ばかり言うので苦痛だった。
あのときの日本歌曲がなんというタイトルだったか、今となっては思い出せない。だがとにかく日本歌曲は難しいし歌いにくい、というイメージだけは鮮明に残っている。
そして今、日本歌曲の代表とも言える「君が代」を独唱しなければならないという、緊急事態に直面している。
ステージ上にグランドピアノが用意され、弾きながら歌っても構わないと提案されるが、この申し出は断った。
ピアノ演奏のみでよければ喜んで引き受けるが、弾きながら歌うということは、ただでさえ低い歌唱力が半減してしまう。
よって、ここは歌一本で挑戦させてもらうことに。
時間もないので、早速スマホを耳に当てながら君が代を練習する。とその時、某ジャズシンガーの言葉が頭に浮かんだ。
「君が代はねぇ、変にアレンジしちゃダメなのよ。主催者に怒られるというか、事前に厳しく言われるからね」
海外の国歌、とくにアメリカの国歌などは著名シンガーがこぞってアレンジをする。
NFL(アメリカンフットボール)の決勝戦、「スーパーボウル」のオープニングでの国歌独唱など、実力と人気を兼ね備えたシンガーの中でも運を持った人でなければ、一生お声がかかることのない大舞台。
その中でも、いまだ色あせることなく感動を与えるのは、故ホイットニー・ヒューストンだ。
1991年、湾岸戦争が始まって間もなく開催されたスーパーボウルの開会式、ホイットニーはある種とんでもない「星条旗」を披露した。
アメリカ国歌である「星条旗」は3拍子の曲。それを彼女は「4拍子」にアレンジして歌ったのだ。得意のゴスペルを強調するためのアレンジだが、ビートを変えて国家を歌うなど、日本では考えられない。
しかしながらホイットニーはやってのけた。そして彼女が歌い終わると、割れんばかりの大歓声で総立ちスタジアムの上空を、4機の戦闘機がはるか彼方へと去って行った。
こんな鳥肌モノの国家を熱唱されては、世界中どこの国も太刀打ちできない。そしてその歌声からは、自国を愛する気持ちが滔々(とうとう)と伝わってくる。
日本国民のわたしでさえ羨ましく思った。願わくばアメリカ国民として、誇りを持って一緒に歌ってみたかった、と。
ーーそんなことを考えるも、いま目の前に与えられた課題は、日本の国歌「君が代」を歌いきることだ。
ホイットニーを引き合いに出すこと自体、相当おこがましい。
無伴奏、つまりアカペラで君が代を歌うということは、音のない「静寂」の間合いをどう扱うかが最大の問題となる。
音が出ている時はまだいい。しかしそれが途切れた時、歌の上手い人ならば「余韻」という空白すらも使いこなす。
ところが、歌が上手くないわたしにそれはできない。
さらに調子に乗って微妙な「間」を空けてしまおうものなら、かなりの高確率で次に出す音をミスるだろう。
無音という静寂は、技術あってこそのスパイスなのだから。
ーーじゃあ一体どうすればいいんだ。
人間とは無責任な生き物。
誰かをあてがえば、自分の責任は果たされた、とばかりにしっぽを巻いて逃げていく。
その結果が惨憺(さんたん)たるものであっても、それは自分の責任ではない、歌い手の問題だ、と責任転嫁できるからだ。
わたしだって好き好んで立候補したわけじゃない。だが、担ぎ上げられれば断ることのできない性格ゆえ、ステージに立つことはもはや自分の責任だと覚悟を決めるしかない。
「そろそろ出番です」
見知らぬADが声を掛ける。
ーーもう終わりだ。
不安と絶望を払いのけるかのように、ギュッと歯を食い縛りながら腰を上げる。
そしてゆっくりと、ステージという地獄へ向かって歩き出した。
*
と、ここで目が覚めた。
わたしはびっしょりと汗をかいていた。
Thumbnailed by オリカ
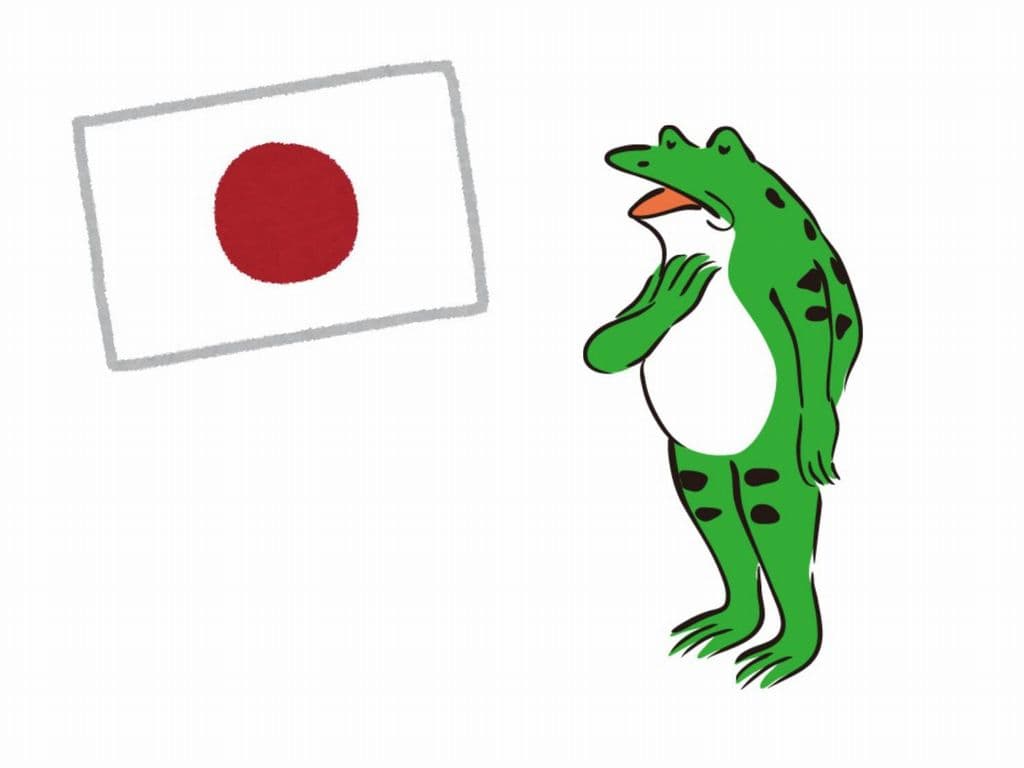




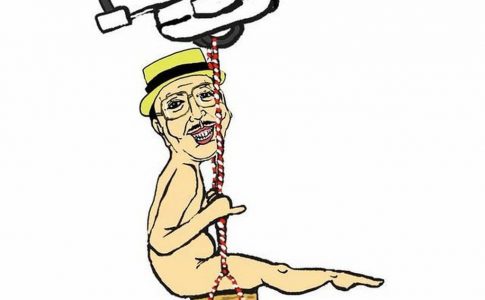















コメントを残す