(・・さ、寒い)
三月末の某日、もうすでに春の到来を察知したわたしは、冬物の衣服をすべてクリーニングに出した。なんせ、日中の最高気温が25度という完全なる春の陽気だったため、"思い立ったが吉日"という言葉に背中を押されて行動に移してしまったのだ。
だがその翌日から、地獄の日々が始まった。
前日との温度差20度という、壮大なスケールのマジックに引っかかったわたしは、自宅に残された薄手のジャケットを羽織る程度の防寒対策しか、対抗する手段が見つからなかった。だからといって、今さら値引きされた冬物のダウンを買う度胸もないため、「わたしは全然寒くない」というフリを装い、春先取りのオシャレさん風情で街を闊歩するのであった。
そして今日、訪れたるは都内某所にあるクライアントの店。完全予約制の料理店というだけあり、決して広くはない間取りだが、天井から床まで趣向を凝らした内装で整えられている。テーブルの端に目をやると、一輪挿しから真っ赤なぼたんが重たげに頭を垂らしているのも、また風流という感じで。
そんな、現実社会の喧騒から隔離された特別な空間へ通されたわたしは、羽織っていたジャケットを脱いだ瞬間に思った——やばい、寒い。
わたしは今日、ここへ料理を食べる目的ではなく打ち合わせに訪れたため、店はいわば定休日なのだ。そのため、エアコンや空調が稼働していない静かな店内では、ずらりと並べられた食器たちを店主が一枚ずつ丁寧に包みながら、三月を締めくくる準備をしている最中だった。
そんな中、畳でできた天板・・という珍しいテーブルカウンターに腰を下ろすと、やや離れたところに置かれた小型のセラミックファンヒーターの方向へと足を伸ばすわたし——あいつから出る温かな風を、少しでも多く確保しなければ。
ヒーターからは上品な温風がそよそよと発せられている。願わくば、石油ファンヒーターでガンガン温めてもらいたいところだが、この店でそれは似合わない。よって、バレない程度にヒーターに近づき、密かに暖をとる作戦に出たわけだ。
もちろん、「少し寒いです・・」と伝えることでエアコンを入れてもらたり、ヒーターの位置を近づけでもらったりすることも可能だろう。だが、変なところで律儀というか気を遣う傾向にあるわたしは、その場所の主が提示した条件をそのまま受けるのが礼儀だと考えているため、多少寒かろうが歯を食いしばり、震えを堪えて平然と振る舞ってしまうのだ。
相手にとってみれば「やせ我慢なんかせずに、正直に教えてくれればいいのに・・」と思うだろうが、そこはわたしのプライドというやつで、与えられた条件でそつなくこなすのが、出来るオンナ——。
こうしてわたしは、上半身は正面だが下半身は大きく右へ捻る形で、バレないように暖をとり続けた。
それにしても、椅子の真下は畳であるにもかかわらず、足裏が接する面は板張りになっているため、いくら靴下を履いているとはいえあそこへ足を下ろしたくはない——。
もしかするとどこかにスリッパがあるのかもしれないが、靴を脱ぐとそのまま室内へと進んだため、つい見落としてしまった可能性がある。かといって、今さらスリッパを探しにノコノコと戻ろうものなら、店主に余計な気を遣わせることとなるので不可。つまりここは、椅子の下へつま先がくるように座るか、ヒーターの方向へ足をずらして畳の上を死守するかの二択しかない。さすがに、椅子の上で正座をするとか体育座りをするとか、そういったマナー違反となる行為を敢行する気はないので、さり気なく足先の着地点を調整するしか方法はないのである。
そんな健気な配慮をしつつ、およそ二時間半の打ち合わせに挑んだわたし。終始おだやかなムードで進み、ではそろそろお暇(いとま)しましょうか・・という時のことだった。
椅子を後ろに下げるべく、足裏を板張りの床に乗せた瞬間、わたしは思わず「あっ!」と声を出してしまった。なぜなら、見るからに冷たい様相を呈する板張りであるにもかかわらず、なんと、床暖房が設置されていたのだ。
靴下を挟んだ足裏へ、柔らかな温もりが伝わってくる——あぁ、あったかい。
*
次回からは、見た目がどれほど冷たそうな板張りの床であっても、一度は足裏を着地させてみよう・・と誓うのであった。



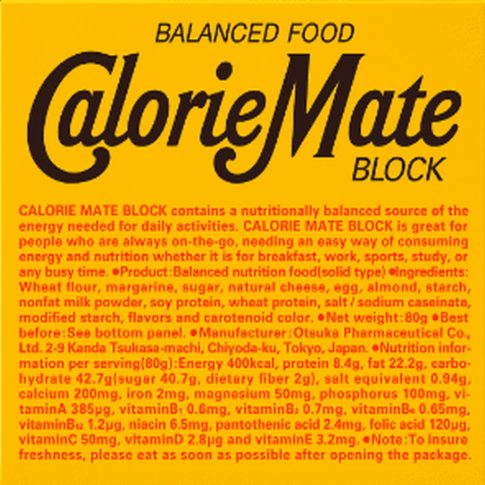

















コメントを残す