"上を向いて歩こう"という歌があるが、なるほどよくできた歌詞である。——上を向いて歩こう、涙がこぼれないように——たしかに、下を向いていると涙がこぼれてしまうが、上を向いていれば大丈夫。
そしてヒトは、涙が出そうになると自然と上を向くのである。その根底には「泣いてはいけない」という思いがあるからこそ、誰に言われるわけでもなく上を向いてしまうのだ。
だが時には、首が痛くなるほど真上を向いていても、目尻から涙が伝うこともある。どんなに強い意志をもって堪(こら)えようとしても、それとは無関係に目から水分がこぼれ落ちるのだからどうしようもない。
——なぜそうなるのかというと、乙があの世へ旅立ったからだ。
*
13歳と一か月を生き抜いた乙は、"相当長生きをした"といえる。フレンチブルドッグの寿命は10年から14年と言われているので、ここだけを見ると「普通じゃないか!」と思うだろう。だが、もしも「余命宣告をされた後に、13年生きた」と言われたらどうだろうか。
なにを隠そう、わたしが乙を家族にしたのは、乙がこの世を去る(かもしれない)数日前だった。あの日、ペットショップに到着するのがあと10分遅かったら、わたしと乙は13年もの時を過ごすことはなかった。そしてあの日、もしもわたしが店員に声をかけなければ、数日後に乙は消えていたのかもしれない。
・・このような事情からも、乙はギネス記録並みに長生きをしたのである。余命数日のところを、なんと13年もの大逆転劇を演じたのだから!!
*
某ホームセンター内のペットショップの片隅に、ひょうきんな顔をしたフレンチブルドッグがいた。しかもかなり長い間、誰にも買ってもらえず一人取り残されており、日に日に値段が下がっていく姿を見るのはじつに不憫でならなかった。
「いい飼い主が現れればいいな」と他人事のように願いながら、ホームセンターへ行くついでにフレブルの様子を確認するのが、いつの間にかわたしの日課となっていた。いや、もしかするとフレブルの様子をうかがうためにホームセンターへ通っていた・・というのが正しい表現かもしれない。
そんなある日の閉店間際、昨日まで例のフレブルが入っていたケージが、今日はもぬけの殻となっていた。
(ついに誰かに買ってもらえたのかな・・)
——こんな希望的観測が事実ではないことくらい、さすがにわたしでも分かる。いつどんな時も、客が興味を示すのはチワワやトイプードルばかりで、あのフレンチブルドッグの前で立ち止まる者など見たことがないのだから。
それにしても、なぜこのフレブルはダメなのか、売れない理由が何かあるのか気になったわたしは、ある日店員に尋ねたことがある。
「このフレブルは、なぜ人気がないんですか?」
すると店員は、
「じつは模様のせいなんですよ。顔の黒い部分が大きすぎるのと、胴体にほとんどブチ模様が入っていないことで、フレブルとしての価値が下がってしまうんです」
と教えてくれたのだ。——模様ごときで価値が下がるって、ニンゲンってまじで何様のつもりなんだろうか。
とはいえ、わが家にはすでに黒柴犬のチヌがいるため、さすがにフレンチブルドッグは飼えない。なんせチヌは臆病で神経質な大和撫子ゆえに、西洋の闘犬の血を引くマイペースな犬など、どう考えても相性が悪い。
そんなこんなで時は過ぎ、とある日の閉店間際——。フレブルの消えたケージが妙に気になったわたしは、閉店作業をしていた店員に声をかけ、「あのフレブルは、売れたんですか?」と尋ねた。すると、
「じつは、明日ブリーダーの元へ送り返すんです」
と、残念そうに教えてくれた。フレブルはこの時点で生後6か月を過ぎており、"売れ残り"として返還対象となっていたのだ。そして、ブリーダーの元で繁殖犬として余生を過ごすのか、あるいは保健所に連れていかれるのかは、正直なところよく分からない・・とのことだった。
その話を聞いたわたしは、居ても立っても居られない気分になった。店内には閉店を知らせる音楽が流れている。そして、わたしがこの場を去ればペットショップは本日の業務を終了し、あのフレブルは明日ここを発つことになる。
その後の人(犬)生は誰にも分からないし、人(犬)生があるのかどうかすら分からないが、そんな悲しい現実を見て見ぬふりはできない——これまで何か月もの間、あのブサイクなフレブルを見守り続けたことで、いつの間にか愛着が湧いたのかもしれない。
そんなことを考えながら、わたしは当時のパートナーに「責任をもって面倒みるから、あのフレブルを飼いたい」と、思わず口走ったのであった。
しばらくすると、店の奥から黒い布をかぶせられたケージが運ばれてきた。その中には、小汚いブサイクなフレブルが静かに座っている。わたしを恐れているわけでもなく、かといって嬉しそうな素振りも見せないその犬は、抱きかかえると犬クサい臭いがプーンと漂ってきた。そのニオイと風貌を間近で観察したわたしは、「おまえ、子犬のくせにずいぶんと苦労してきたんだな・・」と、思わず呟いたのである。
こうして、乙(オツ)と名付けられたその犬と、無責任な飼い主であるわたしとの人生が始まったわけだ。
*
わたしは、乙の死を受けて「決して泣くまい」と誓っていた。なぜなら、「責任もって面倒をみる」と言ったにもかかわらず、引っ越しの際にペット可のマンションを探せなかったため、乙を実家に預ける・・という無責任な行動をとった飼い主に、涙を流す権利などないからだ。
どんな理由や事情であれ、生き物を飼うならば最後まで面倒をみなければならない。それこそが責任であり義務であり、そこに言い訳の余地は皆無。だからこそ、ペットが死んだからといっておいおい泣くのは、ご都合主義の卑怯者だと思うのだ。
最後どころか、乙の人(犬)生のほとんどを親に任せた"無責任な飼い主であるわたし"が、乙に対する最期の誠意をみせるとすれば、それは「涙を見せないこと」くらいだろう。この期に及んで、自分の感情を優先させるなど言語道断。だったらなぜ面倒をみなかった?なぜ途中放棄した?——そんなジレンマがグルグルと渦巻く。
——分かってる。そんなことは分かっている、言われなくても十分に分かっているのだ。だが、寒さが苦手な乙の腹に保冷剤を当てなければならない現実を、どうやったら受け入れられるというのか。どれほど泣くまいと堪えても、堪えても堪えても勝手に涙が溢れてくるのだ。
フワフワの温かい布団にくるまって、今度こそグッスリ眠ってほしいのに、なぜ乙を冷やさなければならない。乙は寒さに弱いのに、なぜ死んでまでこんな仕打ちをしなければならないんだ——。
わたしは誠に無責任で身勝手な飼い主である——本当にそう思っているならば、せめて泣かないことで誠意を示すべきである。だからこうして、上を向いているのだ。涙がこぼれないように、上を向いているのだ。
そして上を向いたまま、目尻からはずっと何かが滴り落ちるのであった。





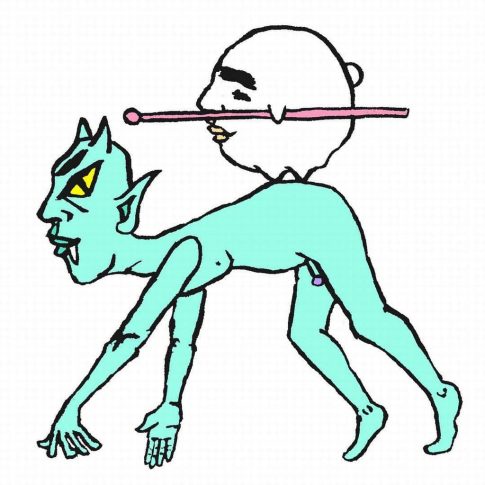


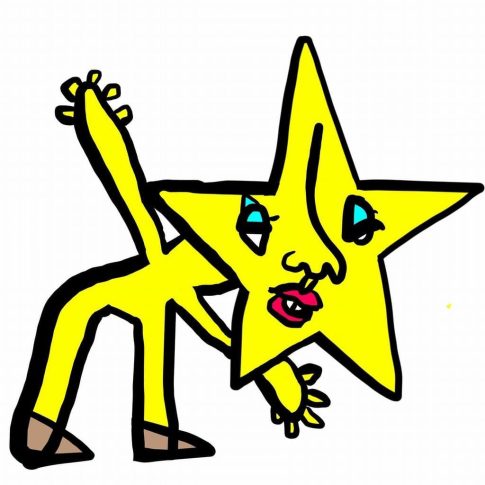













コメントを残す