(もう少し早く歩いてくれないかな・・・)
階段を急いでのぼる必要はないし、ステップを踏み外したり足がもつれたりして、怪我をしたら大変である。だからこそ、無理に急ぐ必要はないのだ。
・・・だが、もう少し早く歩いてもらえないだろうか。なんせ、あなたの前ははるか彼方まで誰もいないのだから。ほら、もう最後の人が階段を上り終えてしまったじゃないか——。
わたしの前をゆっくりと歩く小柄な女性は、歩きスマホで漫画を読んでいた。まぁわたしもよくやる危険行為なので、目くじら立てて怒るわけにはいかない。
それでも前を歩く通行人との距離を縮めるためには、もう少し早く歩いてもらわなければ・・・あ、そうか!!
——その瞬間、わたしはとある話を思い出した。
その昔、イニシャルDというアニメが人気を博していた頃、地方の峠はドリフト野郎で賑わっていたのだそう。かくいうわたしの友人も、ご多分に漏れずドリフトにのめり込み、何台もの車を廃車にしたことを自慢していた。
ある日、友人はプロレーサーであるハナブサ先輩の助手席に座る機会を得た。
ちなみに、友人はトヨタのハチロクに乗っており、アニメ・イニシャルDの主人公も同じ車に乗っていたことから、当時ハチロクは大人気だったのだ。
そして峠の頂上付近で休憩していたところ、他のチームの誰かがハチロクを蔑(ないがし)ろにする発言をしたらしく、それがハナブサ先輩の耳へと伝わってしまった。
無論、相手も本気でハチロクをバカにしたわけではなく、ちょっと調子に乗ってしまった程度で、それ以上の他意はなかっただろう。しかし先輩は、
「お前のハチロク、ちょっと貸してくれ」
というと、友人を助手席に乗せてハチロクのエンジンをかけた。そして例の輩たちが峠を下り始めると、そっと後を追ったのだ。
友人は自分の車のステアリングをハナブサ先輩にあずけ、なすすべもなくプロのテクニックに身を委ねていた。
そしてハナブサ先輩は、みるみる迫りくる前の車のバンパーに、なんと、ハチロクのバンパーを軽く当ててコツンと押したのだ。
まさかの"背後から押される"という離れ技を披露された車は、見事にスピンしてコースアウト。ハナブサ先輩は涼しい顔で、そのまま峠を降りたのだそう。
その光景を目の当たりにした友人は、「プロの世界には、ハナブサ先輩よりもすごいドライバーがたくさんいる。そう思うと、自分なんかとてもじゃないが、おとなしくドリフトするくらいが丁度いいんだ」と思ったのだそう。
その話を聞いたわたしは、「お互いのバンパーに傷はつかなかったの?」と至極まっとうな質問をしてみた。すると「うん、傷もつかないほど、ソフトタッチだった」と、ハナブサ先輩の見事な空間認識能力に感動したのであった。
——その話を思い出したわたしは、今、駅構内の階段をのぼりながら「ハナブサ先輩が運転するハチロク」になりきってみた。そして前を歩く女性のリュックに頭頂部を当てると、そっと押し上げてみたのだ。
(・・気づいていない!!!)
女性は背後から押されていることに気づいていない。それなのに、さっきよりも若干、歩くスピードが速くなっているではないか。
いつの間にかわたしはハチロクの気持ちになっていた。そうか、このくらいソフトタッチならば、ニンゲンは押されていることに気がつかないのだ——。
こうして、階段の半分以上をわたしの押し上げによってのぼった女性は、平らな通路にたどり着いた瞬間にこちらを振り返った。きっと、これまで楽に進んでいた歩様が急に重くなったため、違和感を覚えたのだろう。
だがわたしは、彼女の顔を見ることもなく極めて真面目な顔で追い越したため、彼女に発言させる隙を与えなかった。
視界の端に捉える彼女の顔は、わたしを真っすぐ見つめている。しかしわたしは瞬き一つせず、無表情なまま歩き続けた。
*
こうしてわたしは、見ず知らずの他人の歩行をごく自然に補助することに成功したのである。
とはいえ、その姿を見ていた通行人たちは、わたしのことをどう思ったのだろうか。まさか頭で押しているとは、思いもしなかっただろうが——。







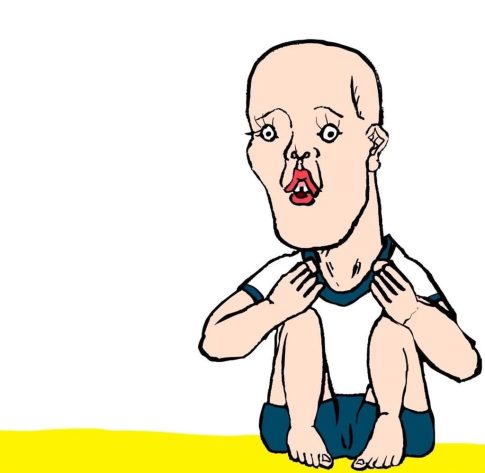

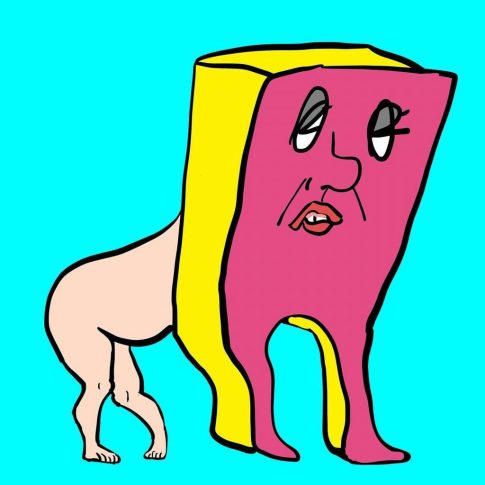











コメントを残す