自宅での作業中に、ふとコーヒーが飲みたくなった。早速、ウーバーイーツのアプリを起動しようとタップするも思いとどまる。
(1分歩けばスタバがあるじゃないか)
窓の外は青空が広がる。
人間にとって太陽の光を浴びることは、生きるために必要な行為といえる。紫外線に当たると皮膚でビタミンDが生成されるため、カルシウムの吸収が促進された結果、歯や骨の成長・形成につながるからだ。
たとえ近所のスタバとはいえ、身支度を整える面倒くささを思うと、つい尻込みしてしまうもの。だが目と鼻の先にあるカフェにすら出向かなくなったら、私は人間として終わるのではないか――と、不安がよぎらないわけでもない。
ましてや日光を浴びる必要性を考えると、なおさらだ。
(とはいえ、顔面だけはしっかりと紫外線を浴びているんだがな)
そう、我が家にはカーテンという文明の利器がないため、ベッド上の窓のブラインドから、毎朝惜しみなく紫外線が届くのである。そのため、顔だけがやけに浅黒くなるという迷惑な現象が起きているわけだ。
久々に会った友人から、
「顔、焼けたねー。海外旅行?」
と言われたときは驚いたが、これが素直な反応なのかと妙に納得したものだ。
そんなことを思い出しつつ顔を洗ってから歯を磨き、前髪をチョンマゲのように結んでマスクを着けた。
(どうせ近所のスタバだ。部屋着のままでいいだろう)
外は日差しも強く気温も高そうだ。タンクトップに短パンは時期尚早な気もするが、モバイルオーダーしたコーヒーをピックアップするだけであり、身なりに気を使うほどのものではない。
こうして私は、颯爽と家を出たのであった。
近所のスタバの目の前。どこかのテレビ局か制作会社だろうか、大型のカメラを担いだ女性と、インタビュアーと思われる女性がキョロキョロと辺りを見回している。手にはケーキやフィナンシェなどスイーツの画像が貼られたボードを持っている。
(どうせなら、ちゃんとした格好で来ればよかった)
僅かに後悔するも時すでに遅し。変に気取らず部屋着でウロウロできる者こそが、地元・シロガネーゼであることを世に知らしめてやろう。
インタビュアーと目が合う。相手が声を掛けやすいように、スタバへは入らずに店の前を通り過ぎようとした。すると、本当に通り過ぎてしまった。
(あれ?おかしいな)
立ち止まって振り向くと、別の方向からやってきたマダムに声を掛けている。ツバの長いダサイ帽子に真っ黒なサングラス、大きなマスクと肘まである手袋をはめている。ノースリーブにゆったりとしたフレアパンツという姿は、やはりあの女性も近所の人間だろう。
(まぁ、声を掛けるタイミングを逃したんだろうな)
スタバを通り過ぎてしまった私は、そのまま直進してパン屋へと向かった。
「あら、いらっしゃい」
馴染みのパン屋で、店番をしている奥さんとあいさつを交わす。ここは現金のみのため、財布を持たない私はいつもパンを買い損ねてしまうのだ。それでも奥さんは、
「今度でいいわよ」
と言いながらパンを渡してくれる、心優しい人である。とりあえず焼きたてのレーズン食パンを2斤(一本)買うと、まだ熱いので袋には入れられないと言われ、紙に包んだ状態で肩に担いで店を出た。
(食パンを担いだまま、テレビに映るのってどうなんだろ)
客観的にみるとシュールだが、白金に住む地元住民にとっては、このくらいは日常茶飯事であることを世に伝えなければならない。そこで張り切って、あのインタビュアーとカメラマンが待つ場所へと向かった。
(お、いたいた)
今度はカメラマンと目が合う。インタビュアーはこちらに背中を向けたまま、逆方向で人材を見つけようとしている。
(早くインタビュアーに教えてやれよ)
私はここにいる。一声かけてもらえればすぐに答えてやろうぞ。
するとカメラマンは私から視線を外した。そしてインタビュアーと同じ方向を見ながら、ぼーっと立っているではないか。なんと間抜けなカメラマンだ!そんなことだから、こんな炎天下で無駄な時間を過ごすことになるんだよ。
呆れ果てた私はスタバへ入ると、さっさと紙袋をピックアップして外へ出た。あの二人はまだ、逆方向を向いている。
(しかたない、ここで待ってやるか)
それほど仕事が詰まっているわけではないので、ビタミンDを生成するためにもしばらく日光浴といこうじゃないか。
手には5杯のコーヒーをぶら下げ、小脇にパンを抱え、広場に建てられたオブジェのような石材の階段に腰掛ける。
しばらくするとあの二人がこちらを振り向き、再びキョロキョロしはじめた。今度こそ私の出番が訪れたのだ。ゆっくりと腰を上げると、大荷物を従えて彼女たちの方へと近づく。
「お忙しいところ、すみません!」
黒いマスクを着けた女の前へ、カットインする形でインタビュアーが突っ込んだ。驚いた女性は一瞬、躓きそうになる。その後、手短に要件を伝えるとインタビュアーはボードを見せながら、スイーツについての質問を始めた。カメラマンは黒マスクの女をしっかりと撮影している。
(・・・私のどこに問題があるというんだ)
怒りでワナワナと震える私は、カメラマンの背後へ近寄ると、インタビューの内容を一緒になって聞いてやった。カメラマンは一切、見向きもしない。ただ、インタビューを受ける黒マスクの女とは、何度か目が合った。
ここら辺のケーキ屋やらスイーツショップやらは、すべて網羅している。この黒マスクの女なんかよりも、私の方が数十倍詳しい。なんなら、今からチーズケーキを買いに行ってもいいくらいだ。
「日本のマスコミはカスだ!」とよく言われるが、たしかにその通り。「オマエの目は節穴か?」という質問に対して「正にそのとおりだ!」と即答できるくらい、気持ちよく貫通したフシアナである。
多忙な私は、枕ほどの大きさの食パンとコーヒー4杯、そしてカラになった1杯の紙コップをもてあそびながら、帰宅の途に就いた。



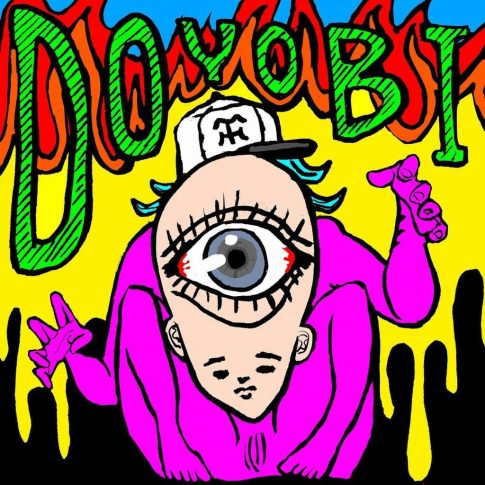

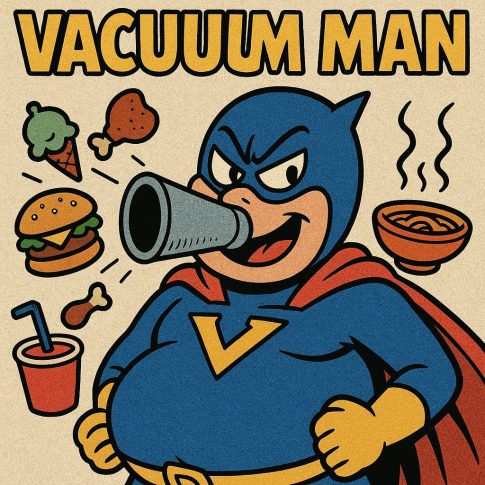


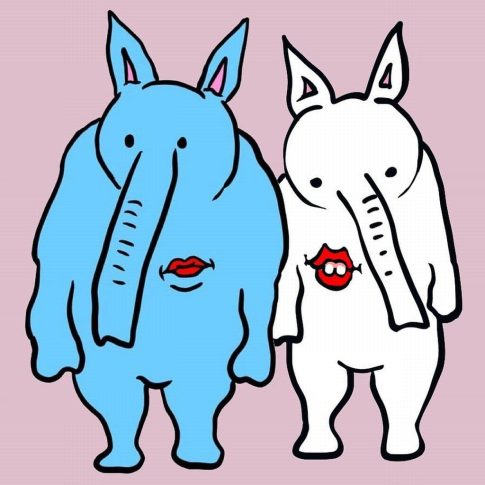












コメントを残す