ある顧問先で、育児休業を終えて職場復帰を目指す従業員がいる。子どもが1歳になり生活リズムが安定してきたため、リモートで仕事をしながら育児との両立を図ろう・・ということで、事業主へ復職の申し出があったのだ。
ちなみに、”育児休業”という言葉はちょっと紛らわしいところがあり、会社が認めれば誰でも育児休業を取得することができるが、雇用保険から支給される「育児休業給付金」については、雇用保険の被保険者でなければ受け取る権利がない上に、子どもが1歳になるまでしか受給できない。
特例で、子が1歳の時点で保育所への入所が決まらなかったり、入院などで育児が困難だったりする場合、子が1歳半になるまで育児休業の延長が可能(さらに2歳まで再延長が可能な場合もあり)となり、育児休業給付金もここまで受給できる。
だが、今年の4月から保育所利用の申し込みに当たり「入所保留となることを希望していないこと」という条件が加わったため、「希望する保育所等に入園できない場合は、育児休業の延長も許容できる」というように、速やかに職場復帰する意思がないとみなされる場合は、育児休業給付金の延長はできない。
これは、育児休業や育児休業給付金の受給延長を目的として、”保育所を利用する意志がないにもかかわらず入所の申し込みをすることは、制度の趣旨に沿わない”という考えに基づく判断だろう。
とはいえ、このことだけをもって「育児休業が終了する」というわけではない。会社によっては、厳密な証明書類がなくとも休業の延長を認める場合もあるため、法律上の最低ラインがここ・・と理解してもらえれば間違いはない。
そして冒頭の従業員について、リモートワークでの作業内容や労働時間、賃金について検討を始めたが、社会保険の資格を喪失しない範囲(ギリギリ週30時間の就労)で復職した場合、従前と比べて賃金が下がる可能性が高い。
通常だと、契約上の固定的賃金(基本給や時給)の増減があった月から3カ月経過した時点で、そこまでの総支給額の平均を社会保険料の等級で比較して2等級以上の差となる場合、月変(随時改定)の手続きを行うことができる。
だが、育休明けの従業員に関しては、特例として「1等級の差」が「1カ月でもあれば」月変の対象となるのだ。
これにより、支払われる賃金に見合った適正な保険料となるため、必要以上に手取りが下がることを防げる。
殊に社会保険料というのは、きれいごとを抜きにして労使ともに負担が大きい。さらに、産休や育休中の保険料は免除できるため、保険料の心配をするならば、復職しないほうが納付も受給も安定する・・ということになる。そんな理不尽というか矛盾を解消するのが、この”月変の特例”なのである。
「でも、保険料の等級が下がるということは、将来受給できる年金額も低くなるってことでしょ?」
確かにその通り。ただし、「通常ならば」という前置きがつく。育休明けの時短勤務により、報酬が減少したことで月変を行った場合は、「厚生年金保険・養育期間標準報酬月額特例申出書」を届出ることで、育休(産休)前の標準報酬月額により年金額の計算が行われるのだ。
ママとなり育児と仕事の両立を強いられる従業員にとっては、現在と将来の両方に対して恩恵を受けられる制度であり、これこそが税金(保険料)の正しい在り方・・と評価されるべき使い道だろう。
産休や育休と聞くと、その期間に受給できる「給付金」について真っ先に思い浮かべがちだが、社会保険料についても「休業期間中の保険料免除」や「休業終了時月変」、そして「従前報酬みなし措置」など、手続きをしなければ認められないが、申請をすることで適用を受けられる制度があるので、該当する場合は適宜手続きを行ってもらいたい。
大きくのしかかる保険料負担に文句を言うことは容易いが、制度として成立している以上、騒いだところで馬の耳に念仏。ならば、制度を適切に使いこなすことで、賢く保険料の負担を軽減させてほしいのである。
「無知は罪なり、知は空虚なり、英知持つもの英雄なり」 by ソクラテス
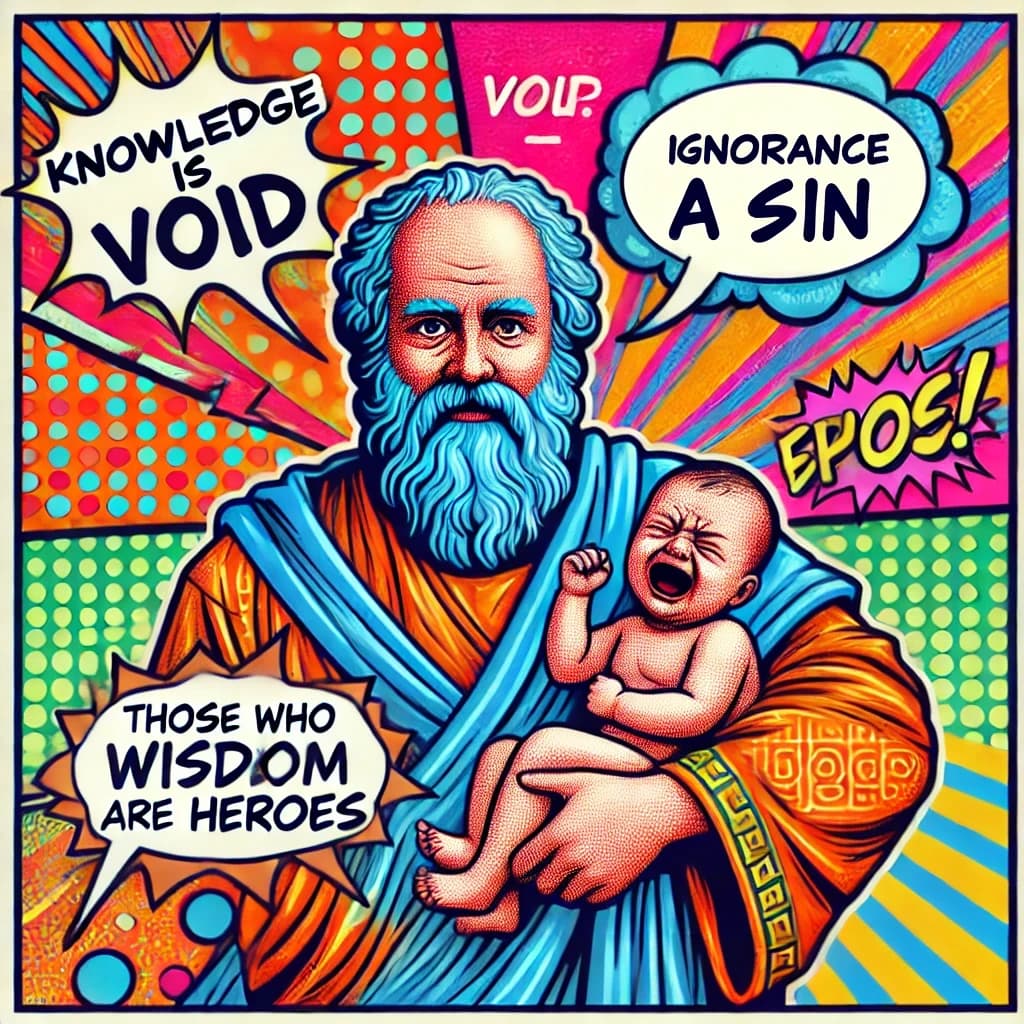


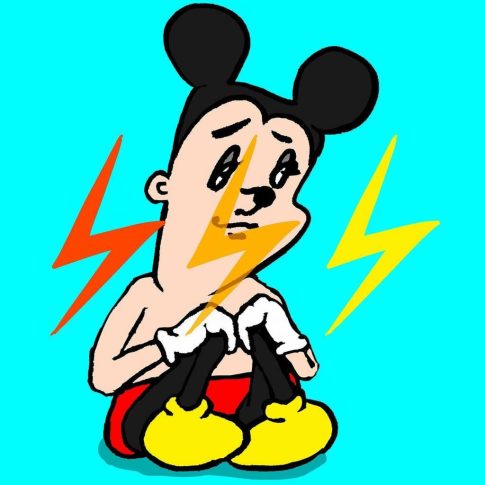
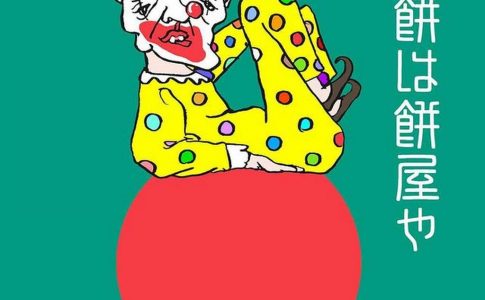


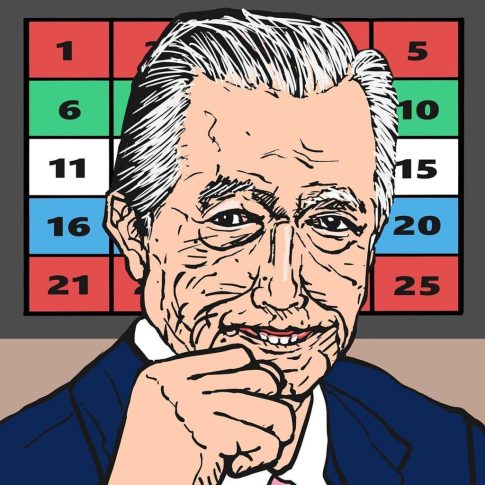

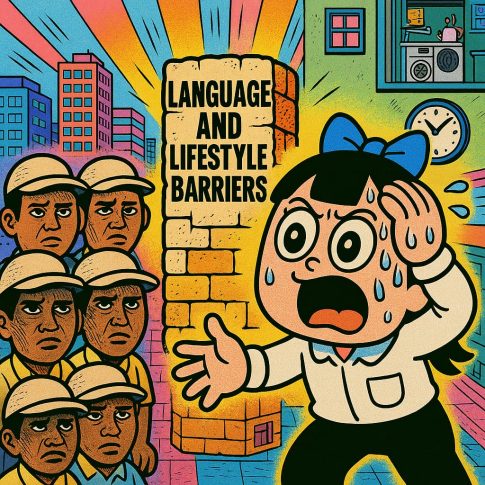
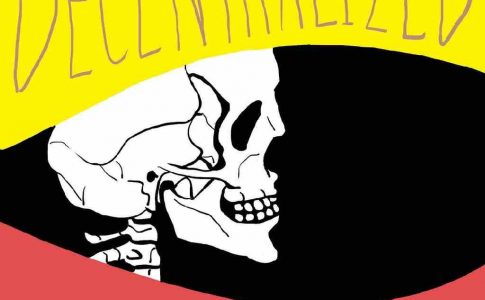










コメントを残す