(これが最後のチャンスかもしれない)
カフェに入ってから何度この言葉が頭をよぎったことか。そして、ことごとくタイミングを逸してきたわたしのつま先は——深緑色のビーチサンダルから覗く十本の指は、まるで死んだタコ焼きのような不気味な色に変わっていた。・・いや、タコ焼きはそもそも生きてはいないのだが。
夏場のカフェというのは、安心してコーヒーを楽しめないくらいに冷え切っている。その理由として、カフェの多くが大型商業施設内のテナントだったりビルトインだったりするため、全館空調の影響で温度設定が調節できないという事情がある。殊に、駅やオフィスが入った建物では設定温度が低い傾向にあるため、しゃれた服装でカフェに入ろうものなら、ものの数分で鳥肌を立てることに。
そんな危険を十分に理解しているわたしは、外出の際には常に薄手のカーディガンを持ち歩いている。そもそも布面積の少ない衣服が夏場のユニフォームなので、冷房から身を守らなければ命の危険すら感じるわけで。
だがこの店はレベルが違った。どの席へ座っても、天井に埋め込まれた空調の吹出し口から、冷気が直接当たるしくみになっているのだ。しかも、とんでもない冷たさの風が容赦なく客へと吹き付けるため、誰一人としてくつろげる者はいない・・と思ったら、頭からすっぽりとフードをかぶり、袖から指先だけを出した状態でパソコンをいじる強者がいた——あれは常連だろう。
さらに別の女子においては、フリフリのワンピースの上に冬物のジャケットを羽織っているではないか——あれも、こういった状況の手練れに違いない。
とはいえ、身を守れるアイテムは薄手のカーディガンしかないわたしにとって、少しでも体温を保つ方法があるとすれば、それは温かい飲み物を注文することだ。なんせここはカフェなのだから、ホットコーヒーもホットラテも、ホットティーだってある。
にもかかわらず、なぜかわたしはLサイズのアサイーボウルを二つと、飲むアサイーを注文したのだ・・おっと、セットでホットコーヒーを二つ頼んでいるので、当然ながら”暖を取る作戦”も怠ってはいない。
だが、Lサイズのアサイーボウルは予想以上に威力があった——そう、量が多い上にものすごく冷たいのだ。
アサイーボウルは、冷凍アサイーをスムージー状にして果物やナッツ、グラノーラをブレンドすることで完成するため、ケーキやプリンといったその辺のスイーツとは一線を画す「冷たさ」を誇る。
そもそもがブラジル発祥の食べ物であるため、火照った体を冷やす目的もあるのだろう。それを、冷房ガンギマリの室内でブルブル震えながら貪り食う・・というのが、なんとも日本人らしくて滑稽である。
——そんな悠長なことをのたまう余裕すらなくなったわたしは、目の前にいる友人の話を上の空で聞き流しながら、カフェの外へ飛び出すタイミングをうかがっていた。
ここは駅構内に併設されたカフェのため、外へ出れば屋外ではないにせよ寒さからは逃れられる。しかも地下道が続いているため、ダッシュするにはもってこいの作りとなっている。よって、せめて2分でいいからその辺りを駆け回り、ウォーミングアップを完成させた状態でアサイーボウルと対峙したいのだ。
しかしながら、ついつい会話が弾み立ち上がる機会を逸すること一時間。みるみるうちに手の指は埴輪(はにわ)のような土色に、足の指は細長いたこ焼きのように変色していった。
(今度こそ出るぞ・・サッと立ち上がってダッシュで店を出ればいいんだ)
そう覚悟を決めても、いざとなるとなぜか話が盛り上がるため、どれほどタイミングを図っても実行に移されることはなかった——ヤバい、コーヒーも底をついたじゃないか。
頼みの綱であるホットコーヒー×2杯すら、もはや空っぽとなってしまったわたしは、目の前に君臨するアサイーボウルと飲むアサイーを戦々恐々の面持ちで見つめていた。あぁ、このままでは低体温症まっしぐら・・・。
「明日もあるし、そろそろ帰ろうか」
突如、天から声が降ってきた。とっくに自身の食事を済ませた友人が、しびれを切らせて退店の打診をしてきたのだ。
「ヨシッ!!」と、心の中でガッツポーズを決めたわたしは、全力でアサイー一味を片付けると、友人よりも早く立ち上がって店を出た——あぁ、命拾いした!
*
毎度毎度、このような瀕死状態に陥ると分かっているにもかかわらず、アサイーボウルがあると無意識に誘い込まれてしまう、食いしん坊なわたしなのである。




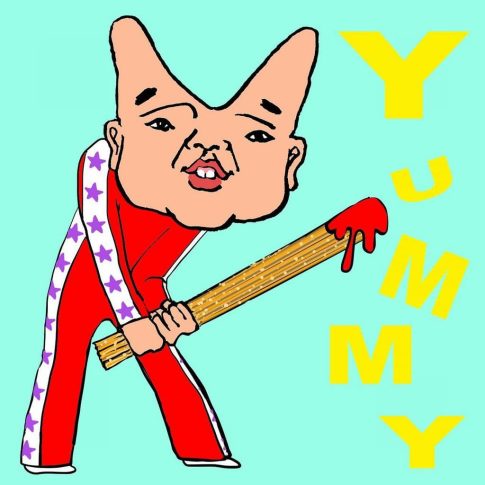
















コメントを残す