ヒトは一生のうちで何回、絶望を味わうのだろうか。
絶望といっても、二度と立ち直れないようなどん底から、あたかも望みは絶たれたかと思いきや、わりとすぐに復活できる落とし穴まで、レベルはさまざま。
そしてそれらの絶望は、受け取る人間の能力やキャパシティ、置かれた状況によって大きくも小さくもなる。
よって、誰かの絶望を嘲笑したり、非難したりすることはできない。
さらに絶望は、ときに圧倒的な「希望」に変わる瞬間がある。どん底であればあるほど、その大逆転劇は華麗かつドラマティックなものとなる。
生きていてよかった、今日という日を迎えられてよかった――。
ほんの小さな出来事かもしれないが、その奇跡は私にとって「今この瞬間」という、ごく当たり前のことに対する感謝を教えてくれたように思うのだ。
あぁ、心の底からありがとう!と言いたい。
*
私はいま、奇跡を体験した。通常ならば考えられないような事象が、目の前で起きたのだ。
なんと、購入したばかりのアイスコーヒーを一口も飲んでいないにもかかわらず、ついうっかり落としてしまった私。
腰の高さから垂直落下した透明なプラスティックカップは、予想以上の速度で電車の床に叩きつけられた。
にもかかわらず、床に横たわるアイスコーヒーは、一秒前と変わらぬ容量を保ったまま静かに横たわっている。
そう、一滴もこぼれていないのだ。
激しくシェイクされた漆黒のアイスコーヒーを見つめながら、私は小さく叫んだ。
(こ、こんな奇跡があるだろうか!)
*
今から三分前。池袋駅構内のドトールで購入した、氷抜きのLサイズのアイスコーヒー。氷がない分、見た目の量は半分ちょっとしか入っていない。
だが、体のためには冷たすぎない飲み物がいい。むしろぬるいくらいがベストといえる。
左肩にはショルダーバッグ、右手には菓子の袋を下げた私は、唯一空いている左手でアイスコーヒーを受け取るしかなかった。
「ストロー、挿しておきましょうか?」
そんな私を見かねたドトールの店員が、こう尋ねてきた。私はすまなそうな表情を浮かべながら、その提案を受け入れた。
電車の出発まであと一分。大荷物のせいで体の自由を奪われながらも、私は目指すべき車両の乗車口になんとか滑り込んだ。
お盆真っ只中、祝日も重なった本日は、さすがに車内が混み合っている。そんな家族連れで賑わう車内を、カニのように体を横に向けながらゆっくりと進んだ。
座席指定の電車における私の選択肢として、「ドア付近の席に座る」という暗黙のルールがある。
これは、もしも殺人犯と同じ車両に乗り合わせた場合に、犯人が毒ガスを噴霧したら真っ先に逃げるためだ。
車両中央では、ガスが充満して目や鼻をやられるかもしれない。そんなことに手こずるうちに、毒が体内に侵入して息絶えるやもしれぬ。
そういった「まさかの事態」に備えて、私は逃走が容易なドア付近を陣取ることにしているのだ。
「犯人が車両に入ってきた途端に、やられる可能性があるのでは?」
チッチッチ。犯人になったつもりで考えてみなさい。
最前列の乗客を仕留めたとすると、それに気づいた他の乗客らは一斉に後方出口へ押し寄せる。そうなると、被害が最小限に抑えられてしまう。
ならばあえて中央付近まで進み、大勢の注目を浴びながら犯行に挑むのが「犯罪者心理」というもの。
つまり、最前列は一周まわって安全なのだ。
このような理由から、一番前の座席を押さえた私は、車両の壁に固定されたテーブルに、アイスコーヒーを置こうとした瞬間、
ドサッ
完全に「やっちまった」音を聞いた。下など見たくもない。なんなら足元一帯がコーヒーまみれとなっているだろう。
特急の床にはグレーの絨毯が敷き詰められている。私はそこへ、真っ黒のシミを植え付けてしまったのだ。言い訳の余地もないくらい、自らの不注意によって。
この不祥事に気づいた周囲の乗客らはシンとなり、なんとも不穏な静寂が広がる。私の背中に刺さる、いくつもの視線が痛い。
だが電車は走り出している。こんなところで突っ立っていてはみっともないし、通行人の邪魔になる。
・・・よし、勇気を出して空のコーヒーカップを拾おう。そしてトイレからトイレットペーパーを拝借して、できる限り床のシミを取り除こう。
それこそが、いま私にできる精一杯の正しい行動だからだ。
ギュッと目を閉じると、おもむろに顔を下へと向ける。
さっさと片付けよう――。
*
ガタンゴトン、ガタンゴトン。
電車が走り抜ける音だけが響く車内。だがきっと、私の周りにいた全ての乗客が、心の中で拍手喝采していたことだろう。
(ブラボー!!)
目を閉じると、聴衆らのスタンディングオベーションが見える。誰もが笑顔で、両手を天へ掲げながら鳴り止まぬ拍手を送っている。
(ありがとう、ありがとうみんな!!)
そして私は「感謝」を忘れなかった。
こんな立派なプラスティックカップを使用しているドトールよ。日頃からスタバばかりを愛用していて申し訳なかった。
今後は、ドトールも私のルーティンに入れることを、この場で誓おうぞ。



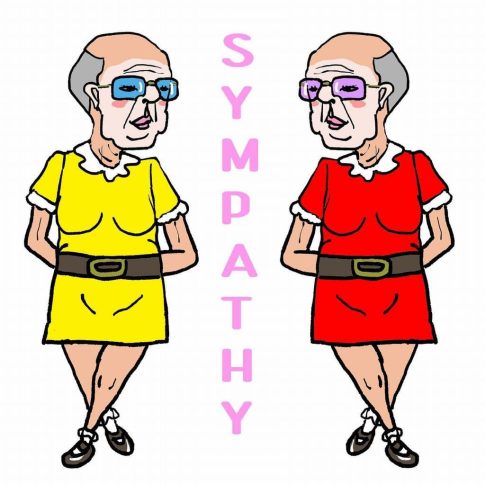

















コメントを残す