YouTubeをランダム再生していたら流れてきた、ヨルシカの「だから僕は音楽を辞めた」を聞いて、思い出したことがある。あまり歌詞を意識して聞いたことがなかったが、虹色侍の歌は聞き流すだけでも刺さる。
曲中の「ある歌詞の描写」が自分の過去と重なり、遠い昔を思い出すこととなった。
*
高校3年の春。大学受験を控えた身でありながらも「授業は寝る時間」を徹底していた。ちょうど窓側の席だったこともあり、授業が始まると体力の回復に向けて睡眠の世界へと旅立った。
——遡ること高2の夏。当時の音楽の先生に呼び出された。私が音大受験することを知っていた先生は、昼休みに音楽室でピアノを弾くことを許可してくれた。
「あなたに紹介したいピアノの先生がいるんだけど」
当然のことながらその当時もピアノの先生はいた。4歳からずっと同じ先生に師事していた。
ピアノに対してとくに情熱を注いでいたわけでもなければ、高みを目指していたわけでもないので、なんでわざわざ先生を紹介されなきゃならないんだろうと不思議に思った。
——なぜこのようにやる気も向上心もなかったかと言うと、常に私がトップだったからだ。練習などする必要もない。
だが「少し刺激があってもいいかな」と思った私は、音楽の先生の提案を受け入れた。
*
高校から自転車で5分の距離に、その先生のピアノ教室はあった。ピアノをかなり舐めていた私は、練習もせず楽譜も持たずに手ぶらで先生の元を訪れた。
先生の名は夏目先生、白髪で長身の男性だった。イメージは「和製ラフマニノフ」のような風貌。
「じゃあ何か弾いてみて」
そう言われて何を弾こう?と考えたが、好みというよりテクニック(恐ろしい勘違い)を見せたほうがいいだろうと思い、モーツァルトのきらきら星変奏曲を弾いた。
弾き終わって間髪入れずに飛んできた言葉は、
「いやー、ひどいねー」
だった。
(え?すごいね、じゃなくて??)
そんな言葉、ピアノを弾いてきたこの13年間で一度も聞いたことがない。いつだって上手いね、素晴らしいねともてはやされてきた。4歳からずっと「天才」あつかいされてきたのに。
「別の曲も聞かせて」
夏目先生からそう言われて私は焦った。きらきら星変奏曲で、ある程度幅のある演奏を聞いてもらえたはずだ。しかし酷評をいただいたわけだ。
―ー次に何を弾けばいいんだ。もはや時代をさかのぼり、小学生の曲を完璧に弾くしかない。
そこで私はドビュッシーのアラベスク1番を選んだ。これならばどう転んだって、間違いなく無難に完璧に弾けるはず。
「う~ん、どういうことだろう。ベートーヴェンかメンデルスゾーン、弾いてみて」
(どういうことだろう?は、こちらのセリフだ)
すでにビビッている私は、ベートーヴェンを選べなかった。メンデルスゾーンならばコンクールの課題曲として最近弾いたやつがある、よし、これでいこう――。
そしてメンデルスゾーンのロンド・カプリチオーソを弾いた。弾き終わると夏目先生は、渋い顔をしながらこう言った。
「う~ん。僕はね、ピアノの上手な子がいるんでちょっと見てやってくれないか、って言われたんだよ。困ったなぁ」
私は言葉を失った。そこへさらに追い打ちをかけるように、
「しかし、こんなレベルでよくここまでやってこれたね」
——完全に撃沈。
何を言われているのかわからなかった、というのは嘘だ。何を言われているのか、痛いほどよく分かっていたからこそ、認めたくなかった。そう、私は狭い世界でぬるま湯につかりチヤホヤされ続けた、お山の大将であり裸の王様だったのだ。
私は、夏目先生にピアノを習うことをその場で決めた。
*
これまで13年間ピアノを教わってきた優しい先生にこの報告をするため、最後のレッスンへと向かった。言いにくかったが正直に伝えた。すると先生は感慨深げに意外なことを言った。
「そう・・・やっぱり運命って巡り合うものなのね」
どういうことだろう?
「じつはね、あなたがまだ小さいころ、あなたのご両親に別の先生に師事することを勧めたの」
そんな話があったのか、それは初耳だ。
「でもご両親は断った。上を目指させたいわけではないからと。そのときに紹介したかった先生こそ、夏目先生なのよ」
——頭がま真っ白になった。
そんな話は聞いてない。もしその当時、私に一言でも相談してもらえたら、私は迷わず夏目先生のところで修業をする道を選んだ。そうすれば、私の人生が間違いなく変わっていただろう。
そんな惨めで悔しい思いを噛みしめながら、ノロノロと自転車をこいで自宅へ戻った。
*
夏目先生のレッスンは壮絶だった。まず出された課題は、小学生が弾くレベルの曲を7パターン、9種類の弾き方をするというものだった。
すべて付点で、すべてシンコペーションで、すべて三連で、ものすごく遅く、ものすごく速く、左手スタッカート右手スラ―で、左手フォルテ右手ピアノで、これら9つの奏法で弾くことだった。
そして私は、こんな単純で簡単なことができなかった。なぜできないのか分からなかったが、夏目先生は分かりやすく簡潔に教えてくれた。
「基礎がまったくできてないんだよ」
そのとおりだ。私はこれまで「雰囲気」や「ノリ」でピアノを弾ききっていた。だから、なんとなく「スゴイ」と思われる演奏になっていた。
——化けの皮が剝がれた瞬間だった
*
睡眠学習中の私は、前の座席のクラスメイトに起こされた。毎回このパターンで起こされる。
「先生が起こせって言うから・・」
なぜいつもバレるのだろう。我ながら完璧に寝ているはずなのに。
すると休み時間にその子が教えてくれた。
「アンタは寝るとピアノ弾き出すんだよ。机でカタカタ弾いてるから、その音でいつもバレるんだよ」
さらに衝撃的な告白を受けた。
「だからあたし、音大受験やめた。ピアノの道へ進む人って、あんたみたいに寝ながらピアノ弾く人なんだよ。だから、授業中寝てていいから、あんたには、頑張って、もらいたい・・」
その子はポロポロと涙をこぼした。
——そんな昔の思い出を、虹色侍が歌うヨルシカの曲で思い出した。
*
考えたってわからないし
青春なんてつまらないし
辞めた筈のピアノ、机を弾く癖が抜けない
ねぇ、将来何してるだろうね
音楽はしてないといいよね
困らないでよ
*
私は、ピアノで大学を受験し合格した。
そして入学することなく、辞退した。



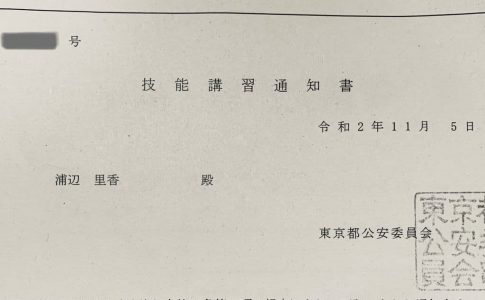



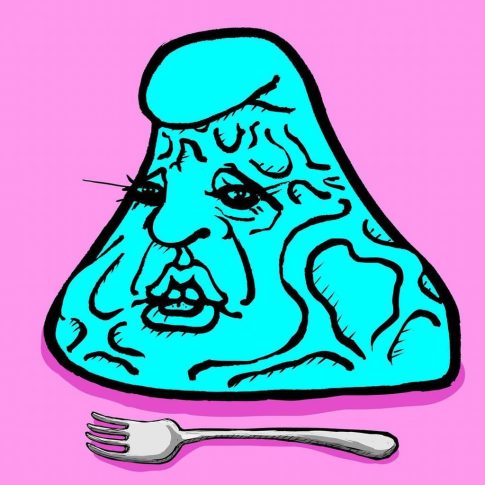













コメントを残す