東京都社労士会会報の5月号を読んでいて、ちょっと興味をそそられる判例に目が留まった。
それは、「事業場外みなし労働時間制と”労働時間を算定し難いとき”に当たるかどうかに関する事案」で、通称、「協同組合グローブ事件(最高裁令和6年4月16日判決)」と呼ばれる裁判についてだ。
「みなし労働時間制」とは、労働基準法第38条の2に規定されている制度で、労働時間を算定し難い場合に、あらかじめ決めてある所定労働時間分の労働をしたものとみなす・・というもの。
ちなみに、昭和62年当時の労働省は、
「業務といたしましては、・・・新聞記者の方であるとかセールスマンであるとか、そういう方が代表的なものであると思っております。そのほか、通常の労働者が事業場外に出張したというような場合もすべてこの規定の対象となるというふうに思っております。」
と答弁している(第109国会参議院社会労働委員会会議録第8号14頁)。
そもそもこの頃は、現代のようにスマホやパソコン、Wi-Fiといった通信機器は一般的ではなく、遠隔地の者と連絡を取る手段といえば有線電話かポケットベル(とはいえ、医師や大企業の営業職など一部の限られた職種だけだろう)という時代なので、上記のような職種が”みなし労働時間制の対象”となるのは頷ける。
だが今では、スマホを持っていない労働者など皆無といえるくらい普及しているため、通信不可能という意味での「労働時間を算定し難いとき」という状況は、電波の届かない地下採掘現場や海の真ん中で作業をするような、特殊な場合のみだろう。
しかしながら行政機関の解釈としては、昭和63年1月1日に出された通達をみると、
・何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
・事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
・事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合
以上の条件に当てはまる場合、「労働時間の算定は可能」という解釈が示されている。
また、テレワークの場合もみなし労働時間制を適用することができる・・という解釈がされており、具体的にには以下の条件を満たす場合に適用できると示されている。
・勤務時間中に、労働者が自分の意志で通信回線自体を切断することができる場合
・労働者が自分の意志で情報通信機器から離れたり、応答のタイミングを判断できたりする場合
・会社からの指示が、業務の目的・目標・期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュールをあらかじめ決めるなど、作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合
なお、「労働時間を算定し難いとき」といえるか否かのリーディングケースとして、平成26年1月24日に最高裁判決が下された「阪急トラベルサポート事件」が挙げられる。
この事案は、”業務の内容(添乗員として同伴する旅程の日程や旅程の管理)が具体的に決まっていたこと”や、”旅程の途中で急な変更が生じた際は、携帯電話で報告と指示を受けるもの”とされていたこと、さらに、”旅程日程の終了後には、詳細な報告を添乗日報により報告させること”が義務付けられていたことから、労働時間を算定し難いとはいえない・・との結論に至っている。
だが、冒頭で触れた「協同組合グローブ事件」においては、来日したばかりの外国人に対する技能実習や生活指導、トラブルの際の通訳など、指導員(労働者)の業務内容が多岐にわたるため、携帯電話の貸与や業務日報の存在のみで「労働時間を算定し難いとき」に該当しないとはいえない・・としたのである。
たしかに、日本語もままならない外国人実習生に対して、イレギュラーな事態が起こらないはずがないことくらい、誰でも容易に想像がつくだろう。計画通りに進まなければ、臨機応変かつ柔軟な対応が求められるわけで、電話やメールで指示ができるとはいえ、現場においては指導員(労働者)の自主的な判断および対応のほうが明らかに重要となる。
要するに、阪急トラベルサポート事件では、現地の添乗員の自主的な判断が必要となる場面があるにせよ、前提として”逐一”会社からの指示で行動していたことからも、労働時間を算定し難いとはいえない・・と判断された。
これに対して協同組合グローブ事件では、業務対応が労働者の裁量による部分が大きいため、携帯電話や業務日報といった形式上のツールがあるからといって、労働時間を把握ができているとはいえない・・と判断されたというわけだ。
*
わたしの関与先は中小・零細企業がほとんどであることと、業種に関しても「みなし労働時間制」を採用しなければならないほど、労働時間の管理が困難な会社はない。
職種として「フルフレックスタイム制」を導入している会社はあるが、こちらは労働時間をみなしているわけではなく、労働者の裁量に委ねて労働時間を管理しているので、「労働時間を算定し難い」わけではないところが大きな違いとなる。
何はともあれ、通信機器と通信環境に恵まれた現在において、協同組合グローブ事件の判決は、労働時間管理の在り方や事業場外みなし労働時間制という制度について、一石を投じることとなったのは間違いない。
それと同時に、働き方の多様性が取り沙汰される昨今であっても、「時間」という普遍的な概念から逃れることはいつまでたっても無理なのだ・・と、改めて認識させられるのであった。
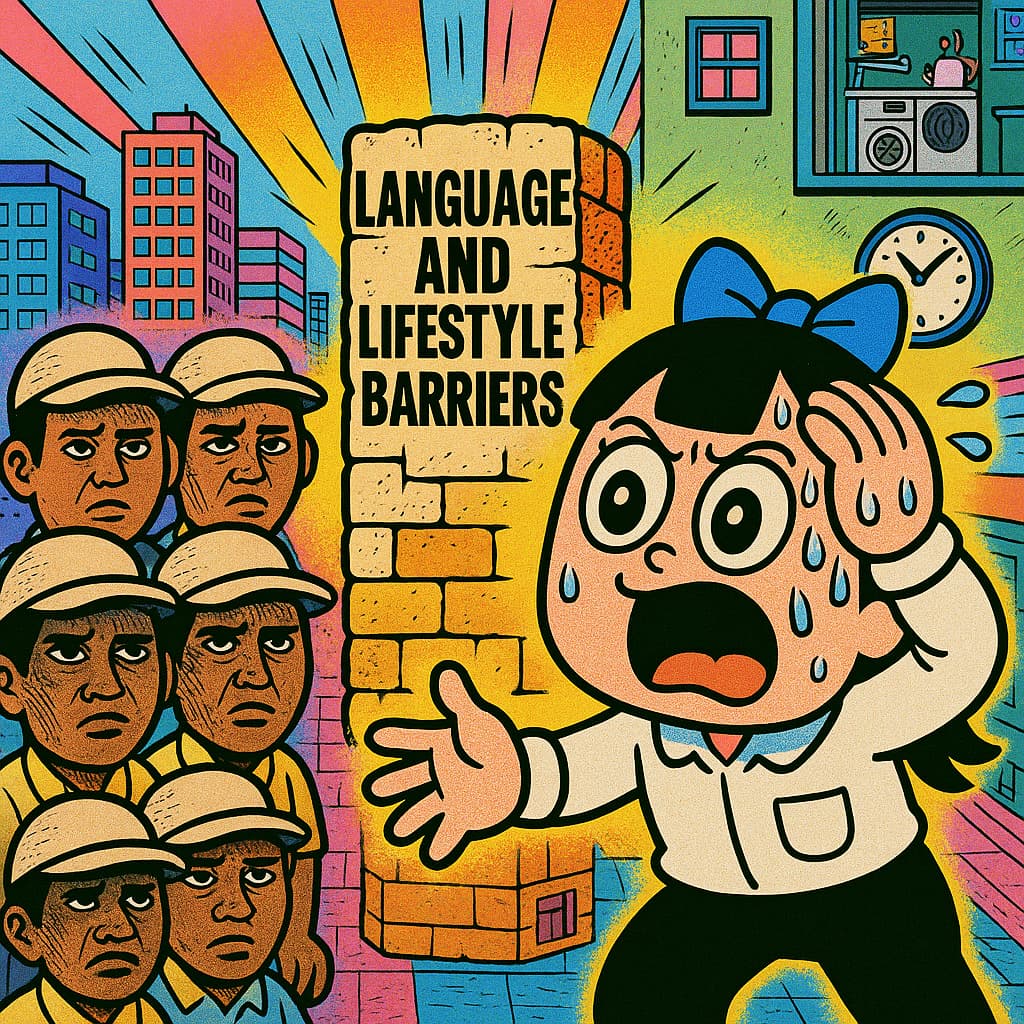





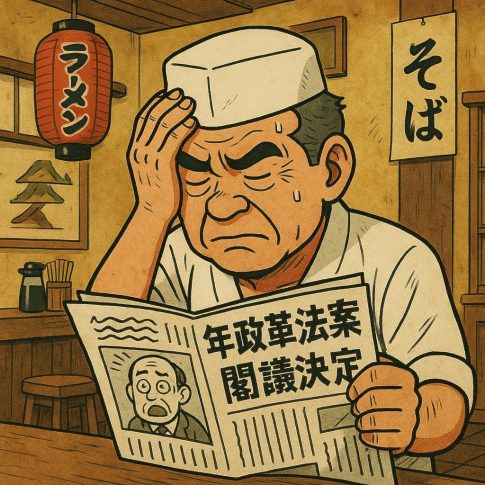



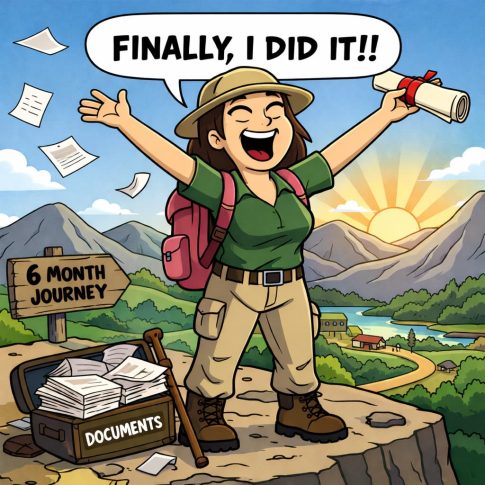










コメントを残す