事業主が初めて労働者を雇うと、裏ではいろいろな手続きが必要となる。
まずは労働保険に加入するために、「労働保険成立届」という書類を作成して管轄の労働基準監督署へ届出をしなければならない。この書類には、事業所の所在地や連絡先・業種・労働者の人数・一年間に支払う賃金額などを記入する。そして、添付した確認書類とともに審査が進められたのちに、労働保険番号が振り出されるのだ。
労働保険番号の知らせを受けたら、次は「概算保険料申告書」の申請である。今年度支払うであろう賃金総額へ保険料率を乗じて、概算で保険料を算出&申告書の申請を行う。そして、申請後に電子納付か紙の納付書にて保険料を納めることで、労災事故や通勤災害に対応できるようになるわけだ。
ちなみに、雇用した労働者が週20時間以上働く場合には、労働保険の成立に加えて「雇用保険適用事業所設置」の手続きをしなければならない。これにより、労働者を雇用保険に加入させられるようになり、納付した保険料は失業等給付や育児休業給付金など、働く者の生活をサポートする給付の原資となる。
さらに、フルタイムで働く労働者を雇用した場合は、社会保険への加入も必要となる。とはいえ、これは労働者の有無にかかわらず、報酬が発生する常勤役員がいる場合は加入義務があるため、個人事業主でなければすでに社会保険適用事業所となっている可能性が高い。
このように、労働者のために各種保険関係への加入・・というか、就業場所自体が保険適用事業所となるべく手続きを行わなければならないわけだが、その他にもいくつかの届出が必要(となる場合がある)。
まずは、1分でも残業する可能性があるならば「時間外・休日労働に関する協定届」、通称「36協定」を労使で締結し、労働基準監督署へ届出なければならない。なお、ここでいう”残業”とは、法定労働時間を超える労働・・すなわち、一日8時間週40時間を超える場合を指すが、「残業代を払えば問題ない!」と勘違いをしている事業主が多いので釘を刺しておこう。
仮に適正な残業代を支払ったとしても、事前に36協定を締結・届出(受理)していなければ、労働基準法第36条違反となるので注意すべし。要するに、36協定+残業代の支払いはセットとなるので、どちらか一方ではダメなのだ。無論、36協定で締結した範囲を超える長時間労働も違法となるので、適正な労務管理を徹底するのは言うまでもないが。
加えて、労働者数が10名以上ならば「就業規則」の作成・届出も必要となる。
就業規則に関しては「(アルバイトを含む)労働者10人以上で届出の義務」が発生するが、人間関係のトラブルを防止するためにも、そして何より”会社のルールブック”として、予め備え付けておくことをお勧めする。
このように事業主は、本業とは別の部分で準備や手続きを行い、労働者の安全を守ったり快適な職場作りに尽力したりしているのである。とくに、初期対応は書類の準備も含めて煩雑なので、単なる事務手続き・・と甘く見ないでもらいたい。
——などと、長々と前置きをした上で何が言いたいのかというと、「入社早々尻尾を巻いて逃げるような行為は、ものすごく謹んでもらいたい」のである。
*
「××さん、バックレました」
先日、顧問先の社長からこのようなLINEが届いた。この一文を読んだわたしは、めまいで倒れそうになった。
たった一名ではあるが、フルタイム労働者の雇用により先述した各種手続きが必要となった会社で、新規適用の対応をすべて済ませた直後の出来事だった。
(・・入社からまだ、2週間も経過していないじゃないか)
今回の新規適用は社労士であるわたしが代行したため、わたしの労力がある意味無駄になった。
いや、実際のところは無駄ではなく必要なことではあったが、それでも、身勝手にバックレて音信不通を決め込むような輩に振り回されたことは、なんというか心中穏やかではいられない。せめて、退職に至るまでの経緯あるいは不満など、言いにくいことかもしれないが、一社会人として事業主と話し合う必要があったはず。
(そういえば、問題を起こす労働者ほど採用時にやたらと権利を主張したがるが、退職の際にはシレっと消えて着信拒否を決め込む傾向にあるよな——)
そうやって、他人に迷惑をかけるような・・言い換えれば、胸を張って誇れない人生を送る輩が、あまりにも多すぎるのだ。
だからこそ、雇われる者も「仮に自分が、雇う側だとしたら」という見方で仕事を振り返ると、今とは違う新たな側面が見えてくるかもしれない。なんといっても、上司だろうが部下だろうが職場を離れれば単なるヒトとヒト。互いの立場を思いやる感覚を、いつの時代でも大切にしてほしいと願うのである。




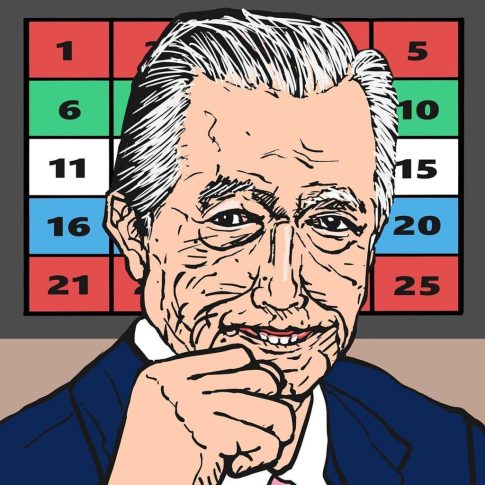



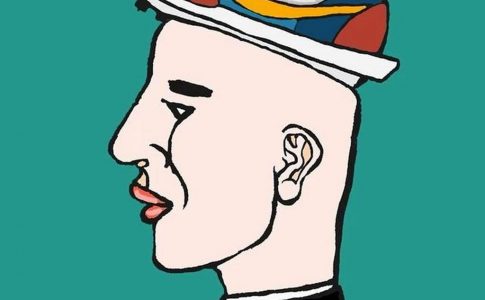












コメントを残す