わたしは今、トウモロコシを食べている。サツマイモ・・というか焼きイモ好きで名を馳せるわたしだが、それと同じくらいトウモロコシも大好物なのだ。
ただ一つ、トウモロコシがサツマイモに勝てない理由があるならば、それは「すべて食べ尽くすことができない」という点だろう。サツマイモは頭からつま先まで、余すところなく完食できる。だがトウモロコシは、皮や芯までをも食べることはできない。ここだけがトウモロコシの弱点であり、残念な部分なのだ。
とはいえ、トウモロコシはややもするとニンゲンよりも偉大な存在かもしれない。我々ニンゲンがトウモロコシを育てているのではなく、トウモロコシによって我々が育てさせられている・・という説があるからだ。
どうやら、トウモロコシの起源は明確ではない模様。そのため"トウモロコシは宇宙からやってきた"という都市伝説的な説まで現れるほど。しかし、今のところの有力候補は、中南米に生息する「テオシント」というイネ科の一年草が突然変異をしたか、もしくは改良によって変化したかで、現在のトウモロコシが誕生した・・という説だ。
そもそも、マヤ文明やアステカ文明において、トウモロコシは重要な作物だったとされる。さらにマヤ神話によれば、「ニンゲンはトウモロコシから作られた」、アステカ神話では「トウモロコシは、ニンゲンが生きるのに不可欠なものとして神よりもたらされた」と、日本人からするとトンデモ話がまことしやかに記されているのだ。
とはいえ、ポポル・ヴフ(Popol Vuh)というキチェ族に伝わる神話や歴史を綴った"マヤの書"には、「創造神たちは、まずは泥からニンゲンを作るが失敗。次に木を彫って作るが上手くいかず。最後に、神聖な食べ物であるトウモロコシの粉から"ニンゲン"を作ることに成功した」とある。
そして、最初に作られた4組の男女がキチェ族などの祖先となり、そこからさまざまな部族が誕生し、今につながっているのである。
要するに、われわれがトウモロコシを食べるということは、われわれの核となる重要な物質を摂取しているということだ。・・たしかに、考えてみればおかしなことばかりじゃないか。通常、植物というのは自生能力があるため、放っておいても自然と受精し繁殖するはず。それなのにトウモロコシときたら、
「トウモロコシは、長い年月の間に栽培植物として馴化された結果、自然条件下における自生能力を失った作物である(OECD, 2003)。」
と、バッサリ切り捨てられているのだから。
おまけに、「トウモロコシの野生種と見られる植物は現存せず(山田, 2001)、国外の自然環境におけるトウモロコシの自生は報告されていない。」とまで断言されており、これすなわち"トウモロコシは、人間との関わりなくしてこの世に存在しない"という根拠となるわけだ。
となるとやはり、ニンゲンがトウモロコシを作ったのではなく、トウモロコシがニンゲンを利用して生き続けている・・と考えるほうが自然だろう。これはもしかすると、まさかのまさかな可能性を否定できないのでは——。
そういえば、トウモロコシの仲間であるジャイアントコーンは、ペルーの極限られた地域でしか生産できない・・と聞いたことがある。遺伝子組み換えもできないため、ペルー(ウルバンバ地方)にもしものことがあれば、ジャイアントコーンもこの世から消え去るわけだ。
これらの条件からも、トウモロコシは現代科学では解明できない不思議な存在であることがわかる。そもそも、トウモロコシの祖先野生種とされる「テオシント」は、見た目がまるで違う。そんなものを無理くり押し付けられても、頭を縦に振ることなど到底できない。
であればやはり"トウモロコシは宇宙からの贈り物説"や"ニンゲンはトウモロコシから作られた説"のほうが、信憑性が高い・・というとりロマンがある分、納得できるじゃないか——。
*
などと小難しいことをごちゃごちゃと考えながら、4本目のトウモロコシを完食したのである。あぁ、トウモロコシはやっぱり美味い——。
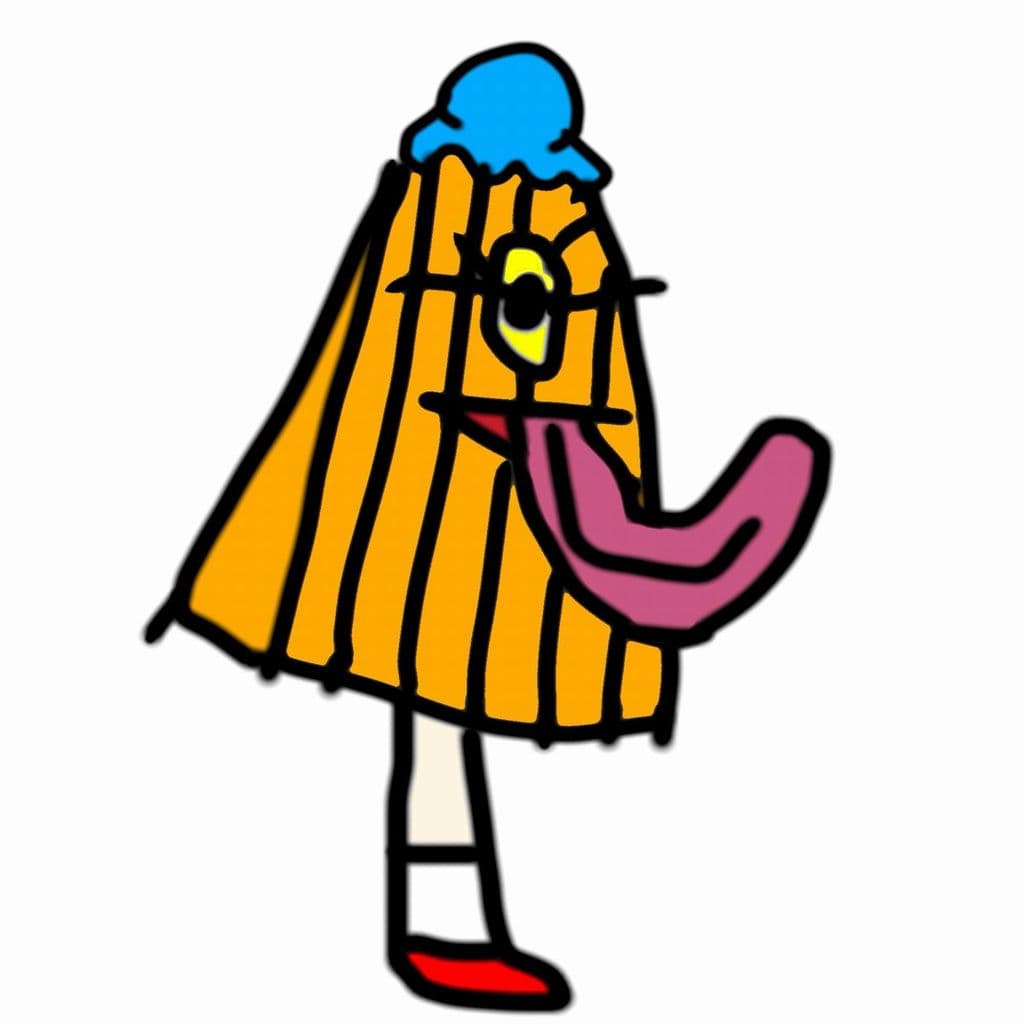



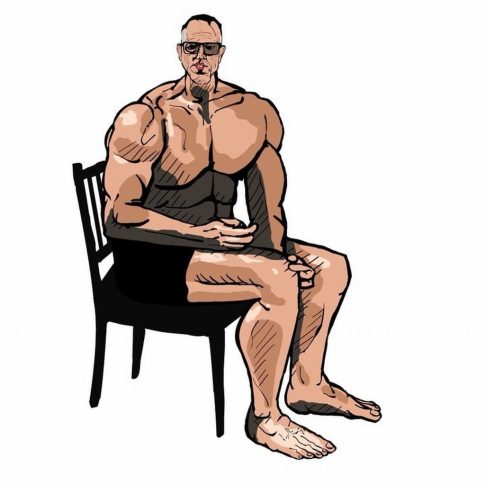
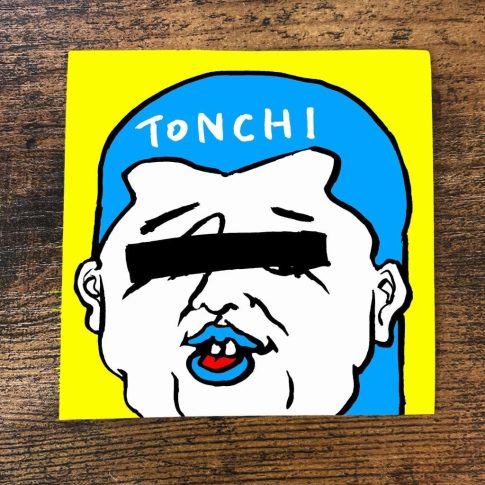

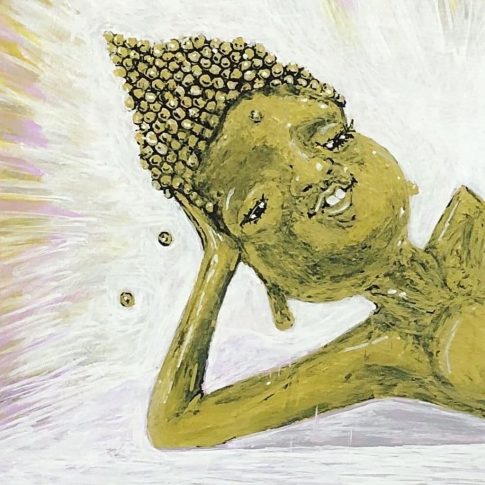
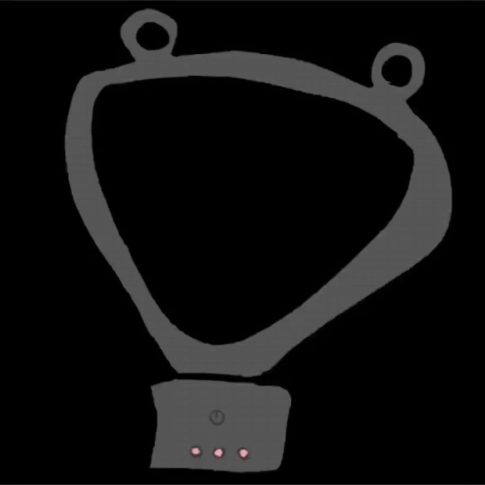












コメントを残す