わたしは今、世間に向かって「小怪我の法則」というものを提唱しようと企んでいる。どのような法則かというと、人間というものは小さな怪我ほど痛がる傾向にある、という法則だ。
これについては、誰しもが思い当たる節があるのではなかろうか?たとえば足を骨折したり、手をガラスでざっくり切ったりすれば、想像を絶する痛みに襲われる。大人ゆえに、涙を流したり騒ぎ立てたりしないにせよ、思わず顔を歪めてうずくまるだろう。
しかし不思議なことに、大怪我の痛みというのはなぜか受け入れられるのだ。大怪我であるがゆえに、事の重大さを理解し冷静に判断した結果、これほどの怪我で痛くないはずがないと納得するのだろう。
わたし自身の直近の怪我といえば肋軟骨骨折か。パキッと鈍い破裂音が周囲に響いた。どこか篭った音だったので、まさかわたしの体内から発せられた音だとは思わなかった。
しかし、疼痛が走る脇腹に触れた瞬間、あの音はここから出た音なのだと実感した。ロンドンにあるタワーブリッジの如く、肋軟骨の真ん中が折れて盛り上がった状態になっていたからだ。
おそるおそる盛り上がった頂点を押してみるが戻らない。このまま固まってしまったら見た目が悪い。ここは無理してでも押すべきなのではないか。
普通に考えて肋軟骨が折れているのだから、余計な圧力をかけるような真似はしないほうがいい。だが、これはどう見たって異常だ。こんな盛り上がりを残したまま治癒してしまったら、あばらに変な突起物のある女として、後ろ指を指されながら生きていくしかない。
わたしは必死になって、そっと圧力をかけ続けた。患部を氷で冷やしながら、その上から静かに押し続けた。だが一向に凹む様子はない。
こうなればもはや強く圧迫するしかない。痛みなど後回しだ。
(この状態で固着してしまったら、後々厄介である。今は痛みを我慢してでも押し戻さねば!)
わたしは鬼の形相で痛みに耐えながら、出っ張った軟骨の頂点を押し続けた。痛みなどどうでもいい、たのむから引っ込んでくれ――。
あれから一年が経過した。わたしのあばらには、見事に小さな山が形成されている。なぜかたまにそこが疼いたりもする。もはやビキニを着てビーチを走ることもできまい。なぜなら、あばらに不自然な突起が確認できるからだ。
結局、折れた肋軟骨はそのままくっついてしまったのだ。
受傷当時、あまりの痛さで横になることもできなかった。仮に横になれたとしても、起き上がることができなかった。よって、夜は座ったまま眠る日々を余儀なくされた。
それほどまでに痛みを感じ、苦痛に悶え、不自由な毎日を過ごしたにもかかわらず、今のわたしはあの時よりも耐え難い痛みに襲われている。
それは何かというと、靴擦れだ。一般的な靴擦れはかかとだが、わたしの場合は外反母趾、つまり第一中足骨の先端部分が擦れて痛いのだ。
ビルケンシュトックのサンダルが外反母趾の部分に当たり、その摩擦で皮膚が薄く剥がれかけている。血が出ているわけでもなければ、足が大変なことになったわけでもない。ただ親指の付け根の内側が擦れるせいで、痛くて歩けないのだ。
「なにもそんな大げさに・・・」
いや、待て。ちょっと思い出してほしい。たとえば指のささくれ、あれだって怪我ではないにせよものすごく痛い。あんな小さな、わずか数ミリの皮膚の亀裂が、手を洗うときも服を着るときも、ものすごい痛みとともに攻撃してくる。
肋軟骨骨折とささくれ、どちらが大怪我かと問われれば、誰もが骨折を選ぶだろう。だが痛みの受け入れ難さはむしろ、ささくれに軍配が上がるかもしれない。なんせ涙が出そうなほどに沁みるし、衣服の繊維に引っかかりでもすれば、悲鳴をあげそうなほどの痛みが襲ってくるわけで。
そんなささくれと並んで、小さな怪我のくせに絶大なる痛みを発するのが靴擦れ。たった一カ所の摩擦点が、とんでもない痛みを与えてくるのだ。
サンダルをつま先に引っ掛けて、地面を引きずりながら少しずつ進む私。ちょっとでも靴擦れに触れると、ギャッ!と飛び上がるほどの痛みが走るため、慎重に、そして確実に患部を守りながら歩を進めるしかない。
たまに外反母趾をチラ見するが、誰がどう見ても大した靴擦れではない。「そんなわざとらしく痛がらなくても」と、冷たい目で見られそうな勢いである。
だがこんなものは、靴擦れができた本人にしか分からない痛みであり、他人にどうこう言われる筋合いはない。
こうして一心不乱にすり足を続けたわたしは、ある時、階段にサンダルを置き忘れて何歩か歩いてしまった。左足は裸足で、背後にはサンダルが取り残されている。
(クソッ、しまった!)
後ろから押し寄せる人混みにうんざりしながら振り返ると、なんと、わたしのサンダルを境に人間が左右に分かれていくではないか。そう、モーゼの海割りのように。
左足だけ裸足のわたしは、振り返らずに三歩下がると、つま先にサンダルを引っかけて再び階段を上り始めた。
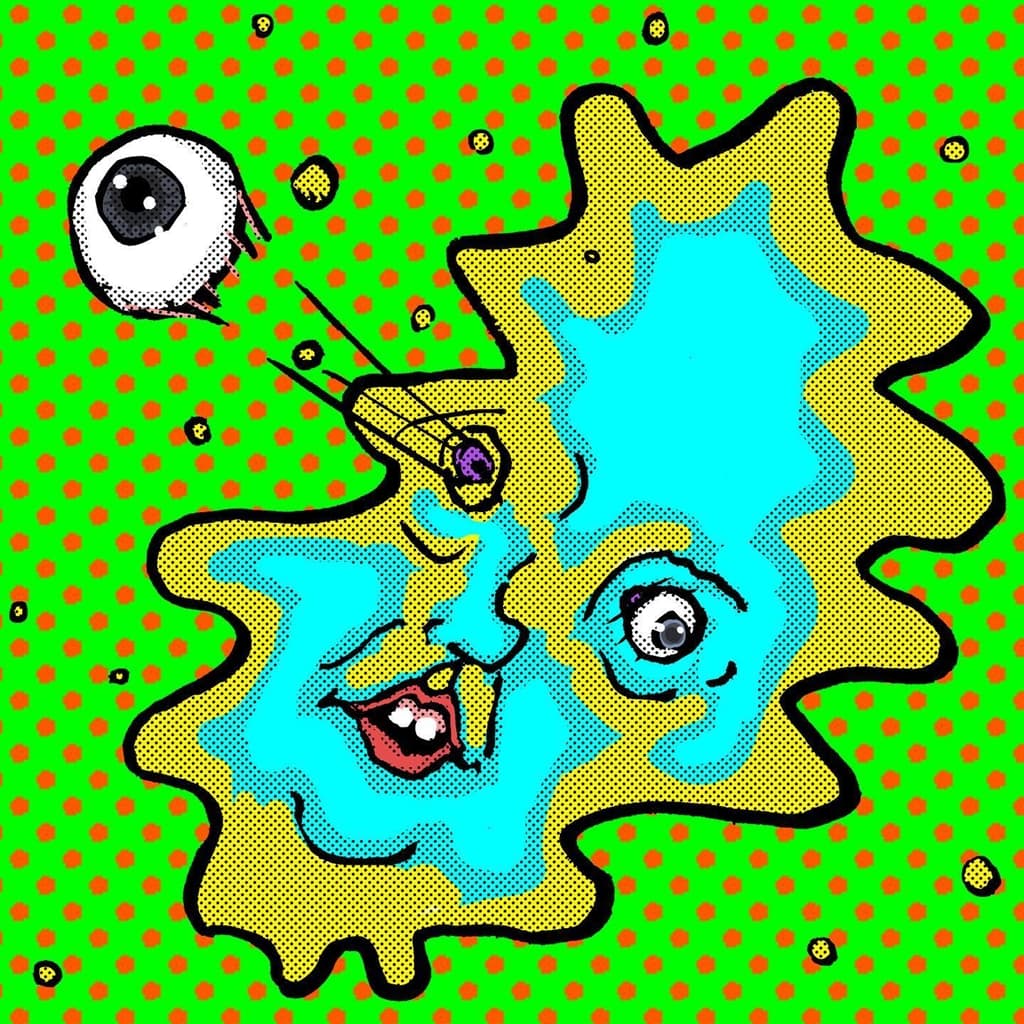


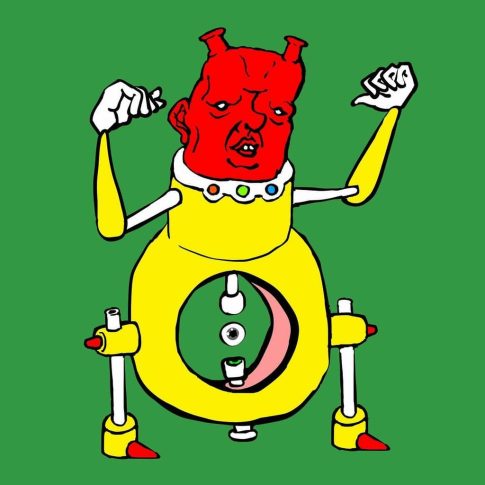

















コメントを残す