かつて、ここまで必死に千切りキャベツの一本一本を凝視したことがあっただろうか。また、煮豆の一粒一粒を観察したことがあっただろうか——。
人生というのは、自分自身が作り上げる壮大なスケールの作品であるとともに、ゴールへ向かってどれだけ寄り道ができるかのゲームでもある。
それ故に、貴重な体験やドラスティックな出来事があるほうが、作品はより迫力のあるものに仕上がるし、失敗や反省を繰り返せば繰り返すほど、ゲームの醍醐味を味わうことができる。
よって、マクロの観点のみで判断するのではなく、時に鼻先がくっつくほど近づいてみるのもまた一興・・と、都合のいい解釈を入れながら、わたしは見事にカットされた千切りキャベツの一本一本を見つめていた。
そもそも、我が人生において「キャベツの千切り」というものを実施した経験がないため、まるでシュレッダーにかけられた紙屑のように完璧な細さで揃えられたキャベツを見ると、「これは人間が切ったのだろうか、はたまた機械がやったのだろうか」と、常に疑問を抱いていた。
おそらく、腕に自信のある個人料理店や高級料理店などでは、シェフが自らカットしているのだろうが、それ以外の飲食店では業務用の千切りキャベツを使用しているのではなかろうか——。
それにしても、これを手作業で行っているとすれば、もはや芸術の域に達している。この細さ、この均一さ、この美しさ・・どれをとっても神技である。
(いやいや、これは絶対に機械の作品だろ)
そんな一人突っ込みを入れながら、わたしはスーパーで購入した千切りキャベツを数本ずつ、口の中へと運んでいた。あぁ、こんなものしか食えないなんて——。
キャベツだけでは味気ないので、同じくスーパーで購入した煮豆の袋を破り開けると、茶色い豆を箸でつまみ上げてじっと見つめた。
わたしは豆が好きなわけではない。無論、「嫌い」というわけでもないが、好んで食べるほど好きな部類ではない。それでも、いま食べることのできる食糧として目に留まったのが、味付けされていない煮豆くらいだったのは事実。そこで、生まれて初めて「煮豆」などという稀有な商品に手を伸ばしたのだ。
煮豆は、もしもこれが食べ物でなければ「薄汚い」と表現してしまいそうなほど、ポジティブな装飾語が見当たらない凡庸な色をしている。
(こういう目立たぬ存在がいるからこそ引き立つ者がいるわけで、全員が全員派手で煌びやかだったら、それこそ華美でうるさくなるだけだ)
これほどの至近距離で煮豆を観察したことなどないわたしは、豆をひっくり返したり匂いを嗅いだりしながら、とりあえずパクっと食べてみた——うん、豆の味がする。
お世辞にも「美味い!」とは言い難い”無味の煮豆”を噛みしめながら、「それでも、ないよりはマシだ」と自らに言い聞かせて二粒目に箸を伸ばした。今度は、赤茶色の豆だった。
(宿敵である小豆とは違うが、なんとなく警戒してしまう色合いだな)
あまり乗り気ではなかったが、食糧が千切りキャベツと無味の煮豆しかないのだから、色がどうこう言っている場合ではない。念のため、この豆もまじまじと見つめた上で口へと運んだ——あっ!!
なんと、うっかり箸から豆が滑り落ちてしまった。しかも、ゴミ箱の中へ!!
ちょっとだけ補足を加えると、今のわたしはソファに腰かけて股の間にゴミ箱を抱えながら、キャベツと豆をつまんでいた。そのため、口へ入る前に落下した煮豆は、確実にゴミ箱へと沈んでいったのだ。
(・・・いや、まだ望みはある)
ゴミ箱を覗くと、ついさっき破り捨てたばかりの煮豆の袋の切れ端の上に、奇跡的に黒い豆が着地しているではないか。たしかに、そこはゴミ箱という敷地内ではあるが、あの袋の切れ端はまだまだ新鮮かつ清潔である。よって、きれいな物の上に落ちたのだから、きれいな状態だと断言できる——よし、拾って食べよう。
人生半ばに差し掛かり、まさかゴミ箱に落ちた一粒の煮豆を拾って食べることになるとは、なんとも情けない限りである。だが、これこそが減量期に現れるニンゲンの本性なのだ。
服用している薬のせいか、代謝がめっきり落ちたわたしは汗も尿も出なくなった。そのせいで、体重が落ちないどころか増える一方となり、苦肉の策として千切りキャベツと煮豆を食べている・・というわけだ。
(こんな惨めな場面すらも作品を彩る1ページとなるのだから、人生において無駄な一瞬など存在しないのである)
・・などとカッコつけながら、ゴミ箱から煮豆をつまみ上げると、改めて口へと運ぶ哀れなわたしなのであった。





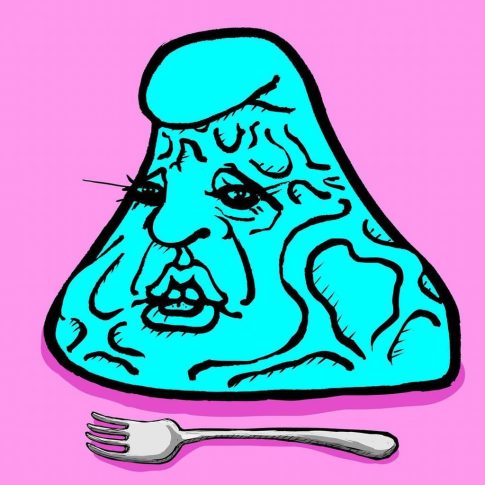















コメントを残す