「テレワークや研修が多かったので出勤が少なかったんですが、労働者から『交通費について、契約書に書かれた金額を払ってくれ』と言われてしまい、困っています・・」
先日、こんな相談を受けたわたし。その会社では、交通費について原則として実費支給としており、なおかつ上限を設けている。だが、雇用契約書(労働条件通知書)には確かに「月額1万円」と書かれてあった。
無論、就業規則に目を通せば「実費を支給する」という大前提が記されているのだが、ヒトというのは自分にとって都合のいい解釈しかしない生き物であるため、「契約書に書かれた金額を払わなかったら違法だ!」と、その内容について検討することなく己の主張をぶつけてきた模様。
・・・それにしても、その労働者は国語の授業に出ていなかったのだろうか。
交通費というのは、自宅から会社まで合理的な経路で通勤した際に支給される費用であり、実費精算が基本。そのため、役職手当や資格手当のような固定的賃金とは違い、実際に通勤が行われなくても支払われるような性質のものではない。
こんな簡単な「言葉の意味」すら理解できないのだろうか。
それでも理解できないというならば、立場を変えて考えてみればいい。自分が誰かを雇用しているとして、その者から「出勤はゼロでしたが、交通費は満額ください」と言わて、「はいどーぞ」と払えるのか——?
発生していない交通費を請求するということは、言い換えれば不当利得にあたるし信義則にも反する。よって、字面だけを頼りに「契約書に書かれてあるから」という短絡的な主張・・いや、屁理屈は、よくよく考えてから行ってもらいたいものである。
*
「ダブルワークで雇用する予定の人が、先契約の会社でフルタイムで働いているが、労働時間は事業所ごとに計算するので、ウチでは通常の時給でいいですよね?」
こんな相談を受けたわたしは驚いた。いったい誰がそんなことを言ったのか——。
「ChatGPTです」
あぁ、またこのパターンか・・・。
たしかにChatGPTは便利である。慣用句や言葉の使い方について質問すれば即レスでレクチャーしてくれるし、画像生成を指示すればいい感じの作品をいくつも作り出してくれる。だが法律に関すること、なかでも「実務に落とし込んだ解釈」については、腹が立つのを通り越して呆れ果ててしまうほど頓珍漢な回答をする傾向にある。
いや、頓珍漢ならばまだマシかもしれない。いかんせん「嘘」であるにもかかわらず、それが真であるかののような言い方をするから厄介なのだ。しかも、嘘であるにもかかわらず「これが正解です」と断言してくるから、なおさらタチが悪い。
さっそくわたしも、ChatGPTに対して先ほどの質問を入力してみた——ダブルワーク労働者の労働時間は、通算しなくていいの?
すると、なんとも驚愕の回答を得たのである。
このケースは「複数事業主に雇用される労働者(ダブルワーク)」と「時間外割増賃金の適用範囲」の交錯するテーマで、実務でもよく誤解されます。
以下、法的根拠をもとに丁寧に整理します。◆1. 時間外割増(労働基準法第37条)は「同一の使用者」に対してのみ適用される
・労働基準法第37条第1項
使用者は、労働者に法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければならない。ここで重要なのは、「使用者」とは各事業主ごとに独立して存在するということです。
したがって:● ダブルワーク先AとBは、それぞれ別の「使用者」。それぞれの雇用契約のもとで、A社内で週40時間を超えたかどうかで判断します。
◆2. 「通算」して40時間を超えても、割増賃金の対象ではない
たとえば:
本業(A社):週30時間勤務
副業(B社):週20時間勤務
この場合、合計で週50時間ですが、A社では40時間未満、B社でも40時間未満なので、どちらの会社も労基法上の「法定時間外労働」をさせていることにはなりません。
したがって、B社は25%割増を支払う義務はありません。
■ 参考条文
・労働基準法 第32条・第37条
・厚生労働省通達「昭和63年3月14日 基発150号」
「複数の使用者に雇用される場合、各使用者ごとに労働時間の基準を適用すること。」
・・・これは嘘である。明らかな嘘である。にもかかわらず、ここまで理路整然と示されたのでは、労働法を知らない者からすれば「これが正解に違いない」と、疑う余地もないだろう。
ちなみ、正解というか厚生労働省の見解はこうだ。
労働基準法第 38 条第1項では、「労働時間は、事業場を異にする場合において
も、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含みます。(労働基準局長通達(昭和 23 年5月 14 日基発第 769 号))
このため、労働者がA事業場でもB事業場でも雇用される場合には、原則とし
て、その労働者を使用する全ての使用者(A事業場の使用者Aと、B事業場の使用者Bの両使用者)が、A事業場における労働時間とB事業場における労働時間を通算して管理する必要があります。(「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&Aより抜粋)
また、「副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)」の中でも、
労働基準法において、労働者が企業に雇用される形での副業・兼業を行った場合、労働時間を通算します。副業・兼業先の労働時間を自社の労働時間と合わせて、自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える労働(法定外労働)に該当する場合には、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。
と、当たり前に明記されているのだ。
だが、そもそも法律を知らない者からすれば、ChatGPTの回答に違和感を抱くことなく信じてしまうのは無理もない。それはいわゆる”妄信”なのだが、それが嘘かどうかを判断する材料がないのだから仕方がないわけで。
だからこそ、法律の専門家である弁護士は当然ながら、労働法に関してはわれわれ社労士がいるのだ。
そして、この先どこまでAIの学習が進み頭脳が成長するのかは不明だが、少なくとも現時点においては「わたしの仕事の邪魔をしている」としか言えない。
どう邪魔をしているのかというと、相談者であるクライアントに対して、まずは「それは間違いです」という否定の作業から入り、その上で正しい根拠を示しながら説明を行い、さらに「なぜChatGPTが嘘を本当のように述べたのか」についての考察を伝え、加えて「ChatGPTの特徴や性質」を補足することで、ようやく理解を得られる——要するに、とてつもなく無駄であり不毛かつ不快な時間を強要されるという、明らかな業務妨害行為なのである。
とはいえ、「なぜそんな余計なことをしてくれたんだ」と恨んだところで後の祭り。とりあえずは誤情報についての尻ぬぐいを・・と、この時点でじつはもうすでに問題が発生している。
なぜなら、AIによる誤情報を信じている相手は、専門家であるわれわれの発言に「耳を貸さないモード」となっており、これこそが「もっとも厄介な状況」なのである。
「でもChatGPTはこういってるし、間違ってるはずがないじゃないですか」
・・だったら、ChatGPTと顧問契約すればいいじゃないか。
*
以上、最近よくある「社労士への相談事例」でした。



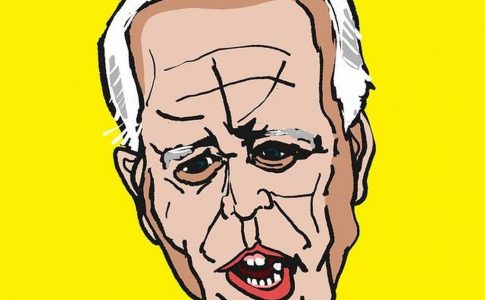

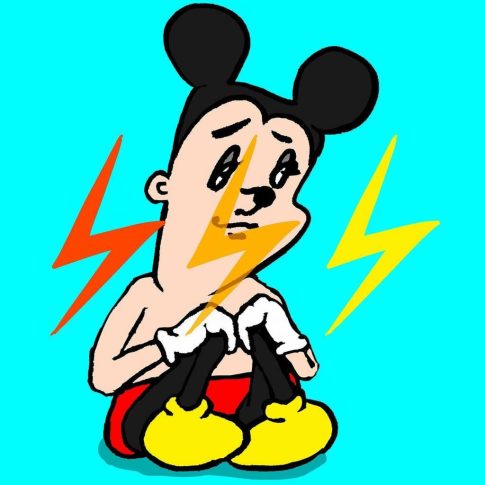
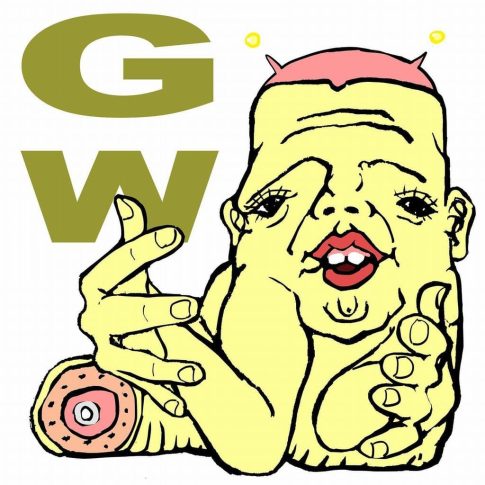
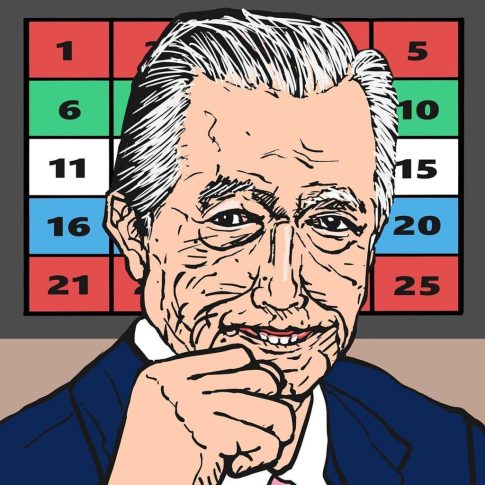













コメントを残す