近所の飲食店あるあるの一つに、「知り合いと会う可能性が高い」が挙げられる。
一人暮らしの人間にとって、近所の飲食店はディナー会場であり、おしゃべりの場でもある。20席ほどの小さなイタリアンならば、カウンター越しにシェフとおしゃべりしつつ、食事に舌鼓を打つのが日常的。
そして、似たようなひとり者が席を一つあけたところに座っていれば、シェフを介して会話が弾み、そのうち互いが仲良くなることは必至である。
さらに「近所に住んでいる」ということもあり、顔見知りになった常連客とコンビニで遭遇したり、犬の散歩中にすれ違ったりと、なんとなく身近な存在となっていく。
最近ではSNSを交換することで、初対面でもすぐに知り合いになれため、友達の輪はどんどん広がる一方なのだ。
しかし、仕事や趣味など生活環境の変化により、近所の飲食店で夕飯を食べる習慣から遠のいてしまうと、顔見知りとなった常連さんの「顔」すらも忘れてしまうもの。
ただでさえ物忘れの激しいわたしは、相手の顔を半年も見なければ、その面影は靄に包まれる。よって、向こうから声をかけられない限り、こちらから挨拶することは不可能となる。
そして今日、久々に訪れた小さなイタリアンレストランで、かつての顔見知り常連さんと出くわした。
・・・と、わたしは思った。
記憶の片隅にある彼の顔は、たしかあんな感じだったはずである。
店のドアを開けた瞬間、カウンターに座る彼と目が合った。かつてはかけていなかった黒縁のメガネに違和感はあるが、その奥に光るつぶらな瞳は間違いない。
ところが、一秒もたたないうちに彼は目をそらした。まるで見ず知らずの他人と偶然目が合ったかのように、表情一つ変えることなく手元の携帯電話に視線を落としたのだ。
(し、しまった。他人の空似ってやつか・・)
――とはいえ、よかった。わたしのほうから「久しぶり!」などと微笑みかけなくて、本当によかった。
よく見たら髪型が違うじゃないか。もっとボサボサしていたし、もう少しロン毛だった気がする。横顔だって、よく見たらまるで他人だ。
近所というだけで、似たような背格好の男性を見間違うとは、なんと恥ずかしいことか。
席に着いて一息つくと、どこからともなく強い視線を感じる。ふと周りを見渡すと、先ほどの黒縁メガネの男性と目が合ったのだ。
今度はメガネを外しており、ますます別人であることが分かる。
さっきわたしがジッと見つめたせいで、なにか勘違いさせてしまったのかもしれない。まずいぞ、これで交際を申し込まれたりしたら、どうしよう――。
今度はわたしのほうから目をそらした。
ちょっとだけ「知人に似ている」などと思い込んだせいで、見ず知らずの男性と見つめ合うこととなったわたし。
笑顔を見せるのもおかしいし、かといって手を振るのも違うだろう。とにかく、あの男性を見ないようにしよう。
そのうち、他人の空似の男性は、カウンター席に座る他の顧客らと会話をはじめた。これこそ、小さな飲食店あるあるだ。
どうでもいい近所ネタに始まり、互いの趣味の話で盛り上がるという、まさに「あるあるの典型」である。
――こうしてまた、小さな友達の輪が広がっていくのだ。
そんな楽しそうな様子を横目で捉えながら、こちらはこちらで久しぶりのイタリアンを楽しんだ。そしていつしか客は消え、店はラストオーダーの時間を迎えた。
そろそろ店を出ようと腰を上げたとき、店のオーナーであるシェフがニコニコしながらこちらへやって来た。
そしておもむろに、こう告げたのである。
「先ほどのお客さまが、お会計をしてくださいましたよ」
なんと!!!あの「他人の空似」だと思っていた黒縁メガネの男性が、知らぬ間にわたしの会計を済ませてくれたのだ。
しかも「勝手に会計済ませておいたら、面白いでしょ?」という、意味不明な理由を残して去っていったのだそう。
そしてしっかりと、わたしの名前を口にしてたとのこと。
――やはりあの人は、かつての顔見知り常連さんだったのだ。
*
一度でも挨拶の機会を逃すと、その後に盛り返すのは至難の業である。
どうかわたしと目が合った際には、嘘でもなんでも「よぉ!」と、親し気に声をかけてもらえるとありがたい。







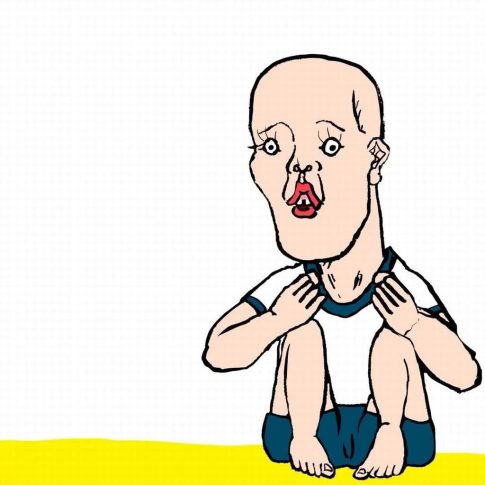


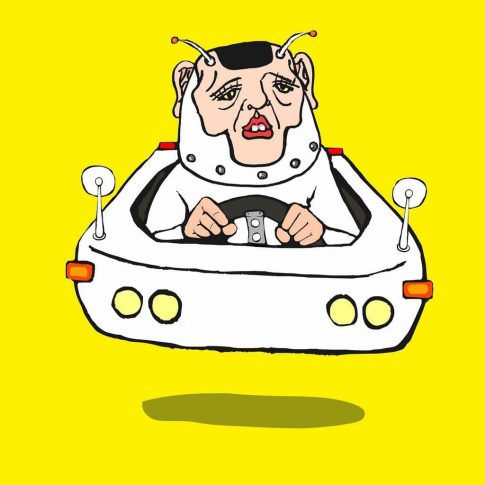










コメントを残す