東京の外れに住む兄(仮名)から、彼の自宅で育ったキウイフルーツが届いた。
縦長の小ぶりな果実が25個ほど、小さくカットされた新聞紙に一つずつ包んで詰められている。
本格的なキウイ農家かと思いきや、兄の職業はサラリーマン。
だが毎年、丹精込めて育てられたキウイは「甘酸っぱいフルーツ」という概念を通り越しており、巷の果物店ではお目にかかれない代物である。
「安心しろ、URABEの分は追熟してるから」
そんなメッセ―ジが届いたのは先月後半のこと。
キウイというのは、収穫したらすぐに食べられるものではない。まだ硬くて酸っぱい時期に収穫し、その後「追熟」させることで完熟させるのだそう。
(そんなこと、キウイ農家でもないのによく知ってるな・・・)
数年前、兄から初めてキウイをもらったときのこと。まだ硬い未熟な個体が送られてきて、
「追熟が必要だから、リンゴと一緒に袋に入れてしばらく置いておけ」
という指示が添えられていた。
・・・追熟とはなにか。そしてなぜ、リンゴと一緒に置いておかなければならないのか。
農業素人のわたしにとって、ハードなミッションである。要は、未熟なキウイを完熟させるために、リンゴが必須ということか?
とりあえずはスーパーでリンゴを買ってくると、キウイと一緒にビニール袋に入れて放置した。
――数日後、キウイを一つ食べる。
包丁で半分に切った時点で、青々とした若すぎる断面が現れた。
(・・・しまった、早すぎた)
とりあえずレンチンして食べてみたが、全然甘くならなかった。
さらに数日後、再びキウイを食べてみたが、やっぱりまだ硬い。
手で握ってもカチコチなので、包丁を入れたところでその硬さが柔らかくなるとは思えないが、それでも待ちきれないわたしは、強引に真っ二つに切り分けた。
(・・・ダメだ、これもまだ食べられない)
キウイに嫌われているのだろうか。何日たってもキウイは柔らかくならないし、当然、甘くもならない。
苛立ちを覚えたわたしは、思わず、追熟用のリンゴに齧りついた。
――甘くてジューシーだった。
こうして、未熟なキウイをちびちびと食べる日々が続く。そのうち、熟れすぎた果実に変化したキウイは、ユルユルのブヨブヨになっていった。
(これは、さすがに兄に言えないぞ・・・)
この事実を密かに察知したのか、その後兄は「追熟したキウイ」を送ってくれるようになった。
*
「今年は試みとして、リンゴではなく追熟剤を使ってみた」
どうやら、エチレンガスを発生する「果実追熟剤」なるもので追熟させるという、画期的な技術を取り入れた兄。
そして「あのメッセージ」から2週間ほどたった昨日、ついに完熟キウイが届いたのである。
白い発泡スチロールのフタを開けると、すぐさまキウイを取り出し包丁を入れる。
・・・おっと、間違ってもキウイの腹あたりで半分にするような、素人丸出しの切り方をしてはならない。
半分に切り分けた果実を、カレー用の大きなスプーンですくって食べるのがわたし流。そのため、ヘタを半分に切り分けるように「縦に」包丁を入れなければならない。
なぜなら、ヘタが残っているとその周辺がうまくすくえないため、果肉を無駄にしてしまうからだ。
包丁が滑らかに、かつ、己の重さを受け入れながら、キウイを切り裂きテーブルへと落ちていく。なんとも無防備で、言われるまでもなく「完熟」であることがうかがえる。
そして真っ二つに別れたキウイは、みずみずしい濃緑の断面を反射させながら転がった。
――これこそが、食べ頃であり最高のキウイである。
わたしはスプーンを手に取ると、ヘタのほうから深く差し込んで一気にすくいあげる。
待ってましたとばかりに、キウイは熟れ熟れの果肉をごっそりと削ぎ取られた。
そして迷うことなく、果肉を口へと一直線に運ぶ。
(・・・う、うまい)
語彙力の乏しさを恥じるしかないが、甘いとかジューシーとかそんな単語では表現しきれないほどの、食べ物としての強い存在感を放つキウイ。
熟した果肉は柔らかいが、その奥にはしっかりとした繊維質が控えている。そして、微かに感じる種の歯ごたえを噛みしめながら、キウイがゆっくりと喉を通り過ぎていく。
「これは、果実というより食べ物だ」
わたしは思わずそうつぶやいた。
フルーツというジャンルを超えた、もっと確固たる呼び方が相応しいであろう、兄のキウイ。
いや、彼の手間暇に加え、自然の恵みとカイオウ(飼い犬のセントバーナード)の見守りにより、立派に実ったキウイには、もはやジャンルなど必要ない。
・・・そう、これこそが「食べ物」なのだ。
*
こうして、食べ頃のキウイ25個をあっという間に平らげたわたしは、満足と満腹により身動きがとれず、さっきからずっとひっくり返っているのである。



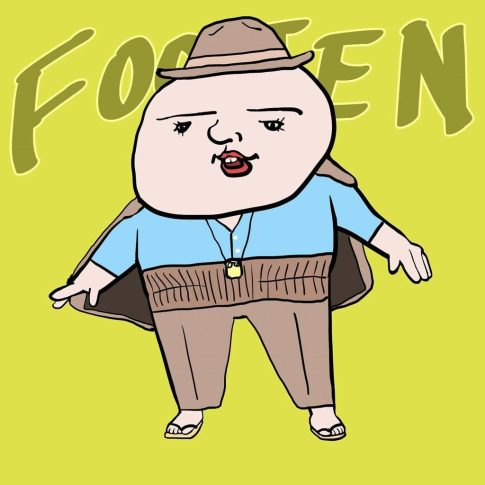

















コメントを残す