義眼の調整に、母が東京へやって来た。
彼女は若くして左眼球を摘出しており、空いた席には義眼が鎮座している。
本人もあまり話したがらないので真相は不明だが、失明した後に眼球周辺の痛みがおさまらず、どうせ機能を失っているのならば摘出してしまえば?ということで、取り除いてしまったのだそう。
医学や科学は日進月歩のため、当時の技術や常識では「眼球摘出」が正答だったのだろう。
現代においても、眼球のせいで何らかの影響が出ているのならば、やはり摘出するのかもしれないし、どれが正しい選択だったのかは誰にも分からない。
だがなんとなく、機能を失った眼球だとしても、わたしならば残しておきたい気がするわけだが。
そんなこんなで義眼歴数十年の彼女は、義眼のレパートリーも様々。やはり女性だからだろうか、少しでも両目のバランスを整えたいと、何度も何度も義眼を作り直してきた。
地方に住んでいるにもかかわらず、評判のいい義眼店の情報を仕入れては東奔西走してきたことからも、彼女の中ではどこかしっくりこない「違和感」があったのだろう。
第三者からすると、見事な義眼と義眼床(義眼の土台)であり、どちらの目が本物なのか分からないくらい、立派なものなのだが。
そして現在では、都内にある株式会社日本義眼研究所にて、かなりワガママなオーダーメイドの義眼を作ってもらっている。
「なんか上を向いているように見えない?」
「もう少し、まぶたに厚みがでるようにしたい」
「左目がギョロっとしてる気がする」
そんなことないよ、と何百回伝えたところで本人は納得しない。やはりコンプレックスというものは、本人にしか分からない根深さというか、こだわりがあるのだろう。
こうして何度も、義眼を調整したり作り直したりしながら、今日に至るのである。
*
事の発端は「日本眼瞼義眼床手術学会」という、眼科や形成外科のドクターの勉強会なるものが存在する、という情報を入手したことによる。
情報提供者は、わたしの友人であり尊敬すべきドクターでもある、宇津木氏だった。
かつて、形成外科医として腕を鳴らした彼は、その後、アンチエイジング専門医として都内でクリニックを開業している。
「義眼は、その土台となる義眼床(ぎがんしょう)によって、出来栄えが変わるんですよ」
「義眼床」という名称自体、耳慣れない言葉である。だがなるほど、土台の作りが悪ければ、どんなに素晴らしい義眼を載せたところで、顔全体のバランスに不自然さが出ることは理解できる。
つまり、「義眼床がイマイチなのかもしれない」というわけだ。
そんな話を母にしたところ、まるで地獄にひと筋の光が差し込んだかのように喜んだ。
義眼による見た目の違和感は、もはやどうにもならないもの…と諦めていたところ、「まだ何か、できることがあるのかもしれない」という、未知の希望を与えられたからだ。
とはいえ、大方ぬか喜びで終わる可能性が高いため、義眼床の手術に係る時間や費用、ドクターの腕前など、そこまで理想通りにはならないことも口酸っぱく伝えた。
宇津木氏も言うように、
「大手術を施したにもかかわらず、ほんのちょっとしか良くならないと、患者さんはガッカリするんです」
というのは想像に容易い。患者側の希望は、海よりも深く空よりも広い。そのため、わずかに良くなった程度では「想像と違う」「だまされた」「ヤブ医者!」となりかねないのである。
――そんなこんなで、母が宇津木氏と面会する日がきた。
「はじめまして、どうぞお座りください」
紳士的に椅子を差し出す宇津木氏。田舎者の母は、半分上着を脱ぎかけたまま着席した。
「どちらが義眼ですか?右?」
気を使ってくれたのかもしれないが、驚くことに本物の目である右目を、義眼かと尋ねる氏。
しかしこれは、あながちわざとではない。なぜなら、そのくらい母の義眼と目の周囲は、本物そっくりのリアルさだからだ。
「右肩が凝ったり、頭痛に悩まされたりしていませんか?」
なぜそんな質問をするのだろうか?義眼は左だと分かっても、なお、右目に着目して質問を続ける氏。
それに対して母は、肩こりも頭痛もありませんと、自慢げに答えていた。
すると宇津木氏は、「それは良かったです」と微笑みながら、質問の「意味」を教えてくれた。
「まぶたが下がっているせいで、右目のほうが小さいんですよね。あ、誰でも35歳をすぎたら、まぶたが落ちてくるので普通ですけどね」
つまり、眼瞼下垂(がんけんかすい)による肩こりや頭痛についての質問だったのだ。さらにこう続ける。
「義眼が入った左目は、もうこれ以上何もする必要はないと思います。非常に綺麗で完璧です。いい先生に出会いましたね。…私は、今の状態でまったく気になりませんが、もしも今後何かするならば、右目のまぶたを少しだけ持ち上げるとかでしょうか」
この発言には、わたしも母も驚いた。
これまで我々は、義眼ばかりを気にしていた。つまり、左目をどうにかして右目に寄せようとしてきたのだ。
そのため、何度も義眼を作り直し、何度もまぶたに脂肪を注入し、ありとあらゆる可能性を追求してきた。一心不乱に、左目だけを見て――。
ところが宇津木氏は、左目などほとんど見なかった。むしろ、右目サイドでできる可能性を提案してくれたのだ。
(言われてみればその通りだ・・・なぜ右目の可能性を探らなかったのだろうか)
思い込みとは恐ろしいものだ。一つのことに固執してしまうと、その呪縛から逃れることは難しい。そして追及すればするほど、その深い沼へとはまっていくのである。
プロだからか、はたまた初対面の第三者だからかは分からないが、宇津木氏からの「思いもよらぬプレゼント」に、母は小さな目をキラキラさせながら東京を後にした。
(これこそが、逆転の発想…ってやつだ)
*
今回のアドバイスにより、母が右目の眼瞼下垂症手術を行うかどうかは分からない。
さらに、わたしも宇津木氏と同じく「何もしなくていいのではないか」という意見のため、あえて勧めるつもりもない。
しかし母は、物理的な変化よりももっと大きな変化を手にすることができた。人工的に作られた完璧な左目ではなく、元来の自分の目である「右目の可能性」という希望を。
実際には、昨日と今日とで何も変わらない彼女の顔。だが、たった一言の「可能性」のおかげで、彼女の人生は豊かに輝けるのである。
宇津木先生。素晴らしい贈り物を、ありがとう。
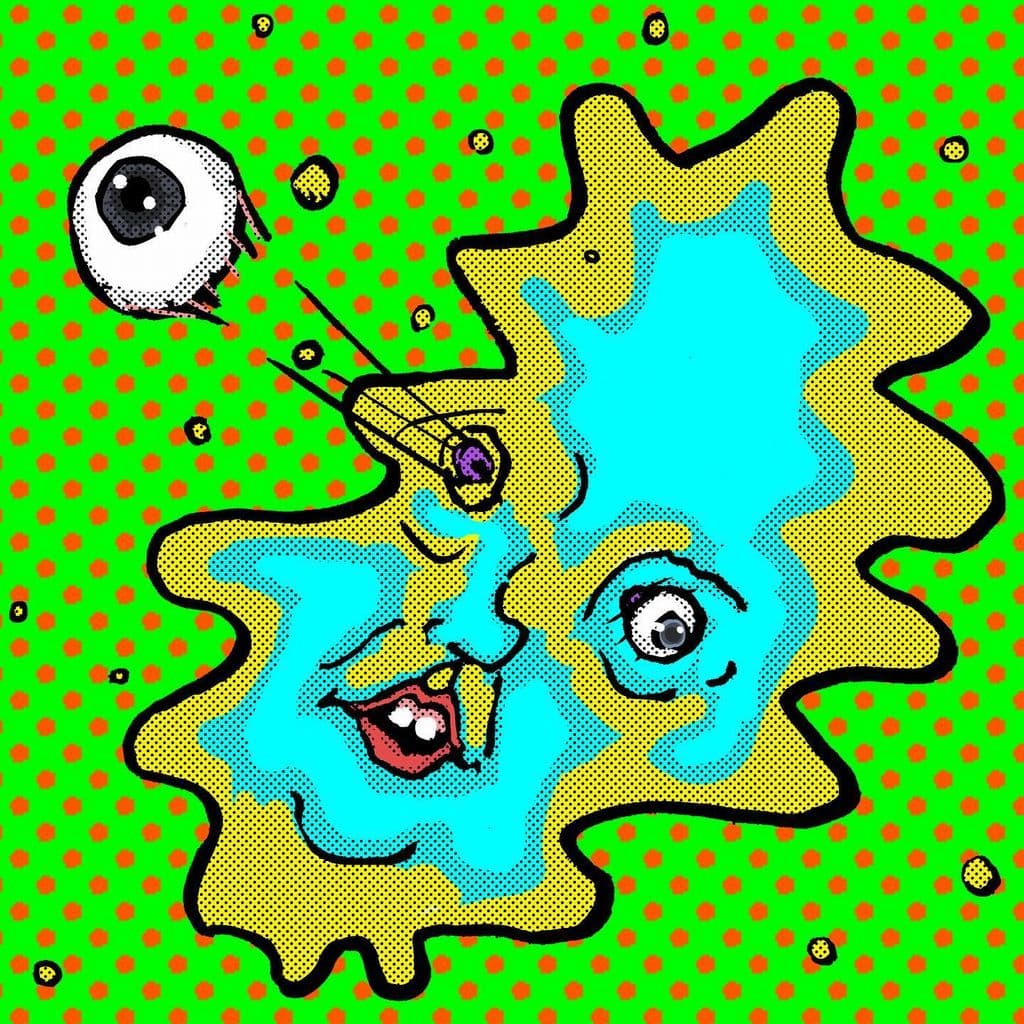


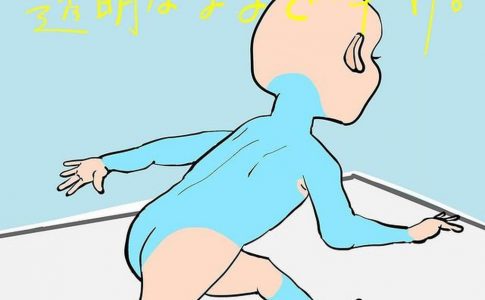

















コメントを残す