「・・・違います」
この言葉しか思い浮かばなかった。
なぜなら、突然、わたしの友人であると名乗りを上げた女性は、見ず知らずの他人だったからだ。
*
いかに久々に会う友人といえど、顔を整形していない限り忘れることなどないだろう。
黒髪を金髪にしようが、カラコンを入れようが、
「お、イメチェンしたねー」
くらいで終わる話だ。
わたしはとある友人と、およそ2年ぶりに対面した。
正確には「対面したらしい」と言うべきか。
「おーっす、ひさしぶり」
声をかけられて振り返ると、そこには見知らぬ女性がいる。
だが、薄暗い中でマスクをしているため、よく確認しないと「見知らぬ女性」と断言できない。
「お、おーす・・・?」
久しぶりかどうかも分からないので、迂闊に余計なことは口走れない。
明らかに怪訝そうな表情のわたしを見て、その女性はピンと来たのか、
「マキちゃんだよーん」
と自らの名前を告げながら、おどけて手を振ってみせた。
そしてこれに対する返事としてわたしが呟いた言葉が、冒頭で登場した、
「・・・違います」
だったのだ。
なぜなら明らかに他人だからだ。
マキちゃんはこんな顔ではない。いくら薄暗くて、いくらマスクで、いくら久しぶりだからと言って、マキちゃんを見間違うほど耄碌(もうろく)してはいない。
わたしは首を横に振りながら、
「違います」
と、もう一度ハッキリと伝えた。
そう断言された女性は、メガネの奥の目をまん丸くさせて言葉を失った。
その時わたしは「巨大な裏組織に騙されようとしている」と悟った。わたしだけがハメられなければならない、何かが起きているのだと。
そうでなければ、なぜこの女性は友人の名前を語ってまでわたしに近づこうとしているのか。
あるいは友人はすでに殺されており、その事実を隠すためにも「マキちゃん」になりきり、周囲を欺きうやむやにしようとしているのか。
わたしを騙したとて、金も地位も何も手に入らない。何の得もないことくらい、わたしを知っている人ならば百も承知のはず。
つまりこの女はわたしを知らない。
だからこそ、このような勘違いをしてまで近寄ろうとしているのだ。
周囲の知人らを見るも、誰もなにも言わないどころか驚きの表情すら見せない。
まるでこの女性が「マキちゃん」であることを受け入れているかのような、自然な振る舞い。
ーーこういう映画、あったな。
自分以外は全員、マインドコントロールされている。まともなのは自分ひとりで、だからこそ自分だけが「おかしい人」に仕立て上げられ、捕まり殺されるのだ。
わたしは震えた。
こんな非現実的なことが、まさか自分の身に降りかかるとはーー。
だが殺されるくらいならば、この女性を「マキちゃん」とみなして会話を成立させるべきだ。
どうせ2年ぶりの再会、今後もしょっちゅう会うわけではない。
顔が違おうが何だろうが、本人が「本人だ」と言うのならば、それでいいじゃないか。
わたしが知っている「マキちゃん」は死んだ。もうこの世にはいないのだ。
忘れよう、すべて忘れようーー。
そう覚悟を決めたとき、「マキちゃん」を名乗る女性が自らの髪の毛を束ねていたゴムをほどいた。
そしてマスクを取ると、メガネも外した。
「あ、マキちゃんだ」
*
あそこまで人相というか、雰囲気が変わる人など見たことがない。
マキちゃんはごく普通のかわいらしい女性。そのマキちゃんにメガネを掛けさせマスクをつけると、ああも変わるものなのか。
むしろあそこまで「本来の自分を消せる」のは、一種の才能といえる。
マキちゃんはもしかすると、海外の工作員とか欧米の潜入捜査官なのかもしれない。
わたしが知っているのは仮の姿で、本業はそういった「秘密裡に遂行しなければならない職業の人」なのかもしれない。
そういえば過去に、彼女の友人の話を聞いたことがある。
「友達でさ、(親御さんの仕事の関係で)子どもの頃から街宣車の助手席に乗せられてたって子がいたよ」
それを聞いたわたしは、
「カッケーな。乳母車が街宣車だなんて」
と、気の利いたジョークをかました。
だがもしかすると、あれはあながちジョークにならなかったのかもしれない。
Illustrated by 希鳳
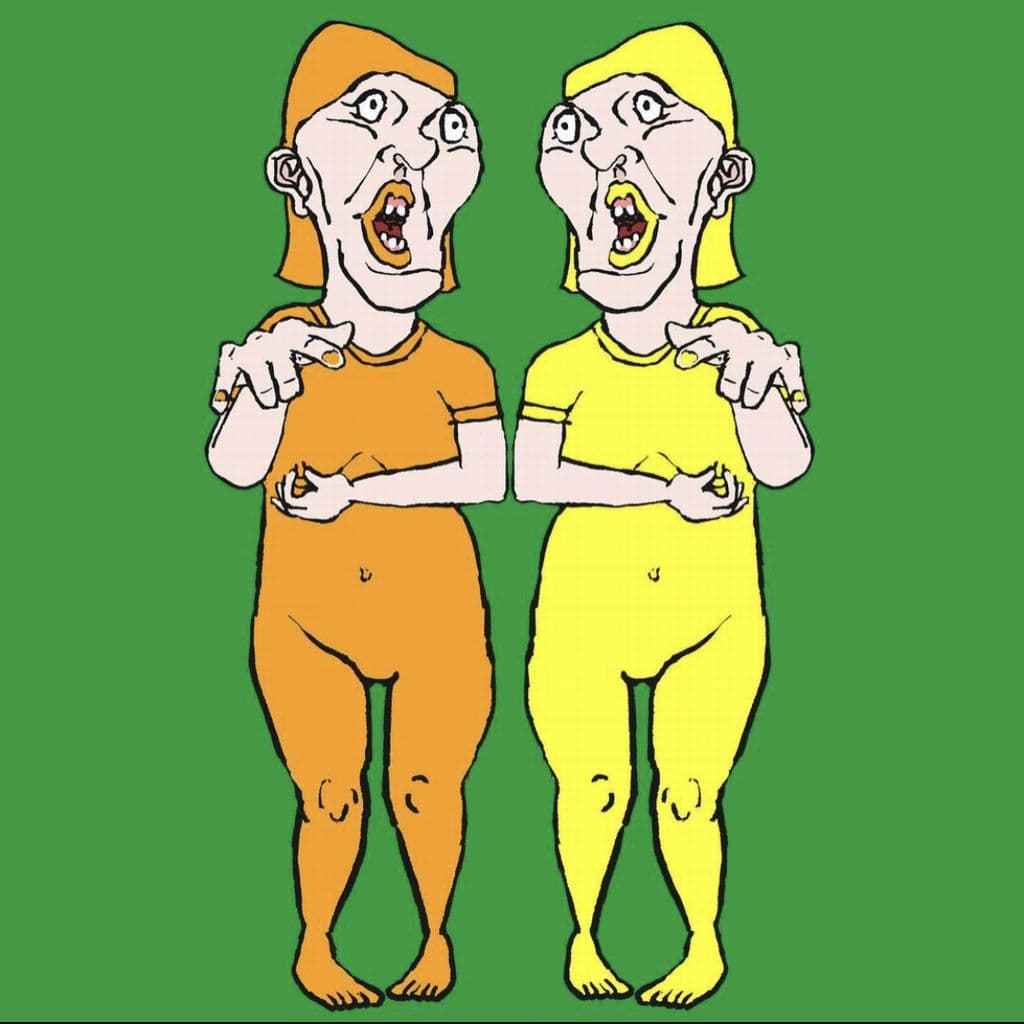






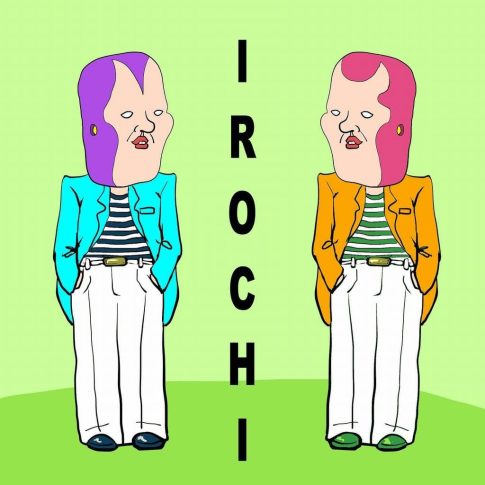













コメントを残す