北陸地方で発生した地震のせいで、新幹線が大幅に遅れていた。普段ならば15分前くらいに乗車券を買うわたしだが、実際には15分前に買った乗車券の新幹線は、一時間50分遅れていた。
駅構内は大量のUターン客で埋まっている。待合室に入りきらないほどの乗客が、ただ呆然と東京方面行きの新幹線を待っている姿は、人間の無力さを象徴しているようだ。そう、新幹線が来なければどんな奴でも東京へは戻れないのだ。
まぁ、自然現象というか天変地異に腹を立てても仕方ないので、わたしは努めて冷静に新幹線を待った。そして一時間50分後にようやく、お目当ての新幹線に乗ることができた。
*
券売機で「普通席/残りわずか」と表示された、北陸新幹線かがやきを見て、思わずため息が漏れた。
直近の新幹線3本はいずれも満席で乗ることができない。「立席」ならば購入することができたが、さすがにこの年になってまで立ったまま東京へ向かうのは、なんというか耐えられない。よって、4本先の「かがやき」の普通席を買うことにしたのだ。
「残りわずか」となっているが、唯一タッチできる4号車を開いた瞬間、空席は一つしかなかった。見間違いではないかと「戻る」ボタンに触れてみたが、やはり「残りわずか」と表示されている。
たしかに「ラスト1席」という表示の準備がなければ、空席が一つでもあれば「残りわずか」となるに決まっている。だがよりによって、グランクラス、グリーン車、そして普通車の中で、たった一つしか席が空いていないタイミングなどあるのだろうか?
それでも、ここでモタモタしていると2つ先の新幹線まで満席が続く。もはや選択の余地はない、4号車12番A席を抑えるしかないのだ――。
その瞬間、隣で乗車券を買おうとしていた男と目が合った。こいつには先を越されちゃいけない、これこそが負けられない戦いってやつだ。
わたしは、ものすごい速さでたった一つの空席をスマッシュした。そして勝った(買った)のだ。
*
A席ということは、3人掛けの窓側のシートだ。事前に満席であることは承知していたため、通路側と真ん中の乗客にペコペコしながら指定の座席へと滑り込んだ。
窓際でラッキーなことといえば、コンセントが二つ使えることだろう。壁側と座席との二か所を独占できるため、色々な電子機器の充電ができるからラッキーだ。
それにしても、乗車率100%の新幹線車内が思いのほか静かである。子連れが少ないことも影響しているかもしれないが、少なくともわたしの横に並ぶ二人はいずれも他人である。
そんな他人である二人に、不思議な現象が起きたのだ。
コロナ禍以降、電車内で気を遣うことといえば「咳」だろう。ちょっとむせただけでも殺意漲る目で睨まれるため、迂闊に咳き込むことはできない。今でこそマスク着用の義務から解放されたとはいえ、やはり密室で咳をするのは好ましくない。
そんな中で、わたしの隣人が弁当を食いながらむせてしまったのだ。周囲に気を使いながらコソコソと弁当を食っていたのだが、運悪く米粒が気管に入ってしまったのか、グゥエッフェッフェと派手な咳をかました。
(あぁ、かわいそ。気管に入った異物を押し出すための咳なのに、濡れ衣を着せられてしまって)
所詮は他人事であり、生温かい目で見守ることしかできない。隣人は健康そうだし、なによりも咳は必然的な生体反応なのだから、それを無理に抑えることのほうが不健康である。わたしなら平気だから、大いに咳き込むがいい――。
すると突然、その隣の乗客がむせたのだ。なんか飲み物を飲んでいたが、やはり誤って気管に入ってしまったのだろうか。ブフェッブフェッと咳き込んだ。
よく「あくびは伝播する」というが、咳にも似たような性質があるのだろうか。隣りで激しくむせると、その近くの人間も思わずむせてしまうなんて、聞いたことはないが実際にその現象が起きているのだから、やはりそうなのかもしれない。
・・そんな不思議現象に感心していたところ、なんと、よりによってわたしの唾液が気管に流れ込んでしまったのだ。
(マズイ!!ここで咳き込んだらコントだ!)
わたしは咄嗟に立ち上がると、デッキへ向かって逃げようとした。さすがにここで咳をしたら、わざとだと思われかねないし、コントだと笑われかねない。なによりも、密室で咳はご法度である――。
そんな緊急事態に遭遇したわたしの目の前には、邪魔なシートが立ちはだかっていた。いや、正確には、B咳の隣人の前のシートがガッツリ倒されているため、わたしが通路へと出られないのだ。
通路側の乗客はそれに気づいて立ち上がった。隣人は席を立とうにも倒されたシートが邪魔なのと、弁当を抱えているため立ち上がれない。そして、わたしが咳を堪えるのも限界を迎えている。も、もうダメだ――。
ガックンガックンガックン
わたしは全力で倒れたシートを揺さぶった。
体格のいいオバハンがもたれかかっていたが、渾身の揺さぶりにより目を覚ました。そして極限状態のわたしと目が合った女性は、口を開けたまま慌ててシートを元に戻した。
数日前にも同じようなことを呟いたが、決してシートを倒していることが悪いわけではない。そういう設計になっているのだから、何も問題はない。だが今は、それどころではないのだ――。
こうしてわたしは隣人とその隣の乗客と、そして前の座席の乗客らの奇異な目に晒されながら、咳をこらえてデッキへと走ったのであった。
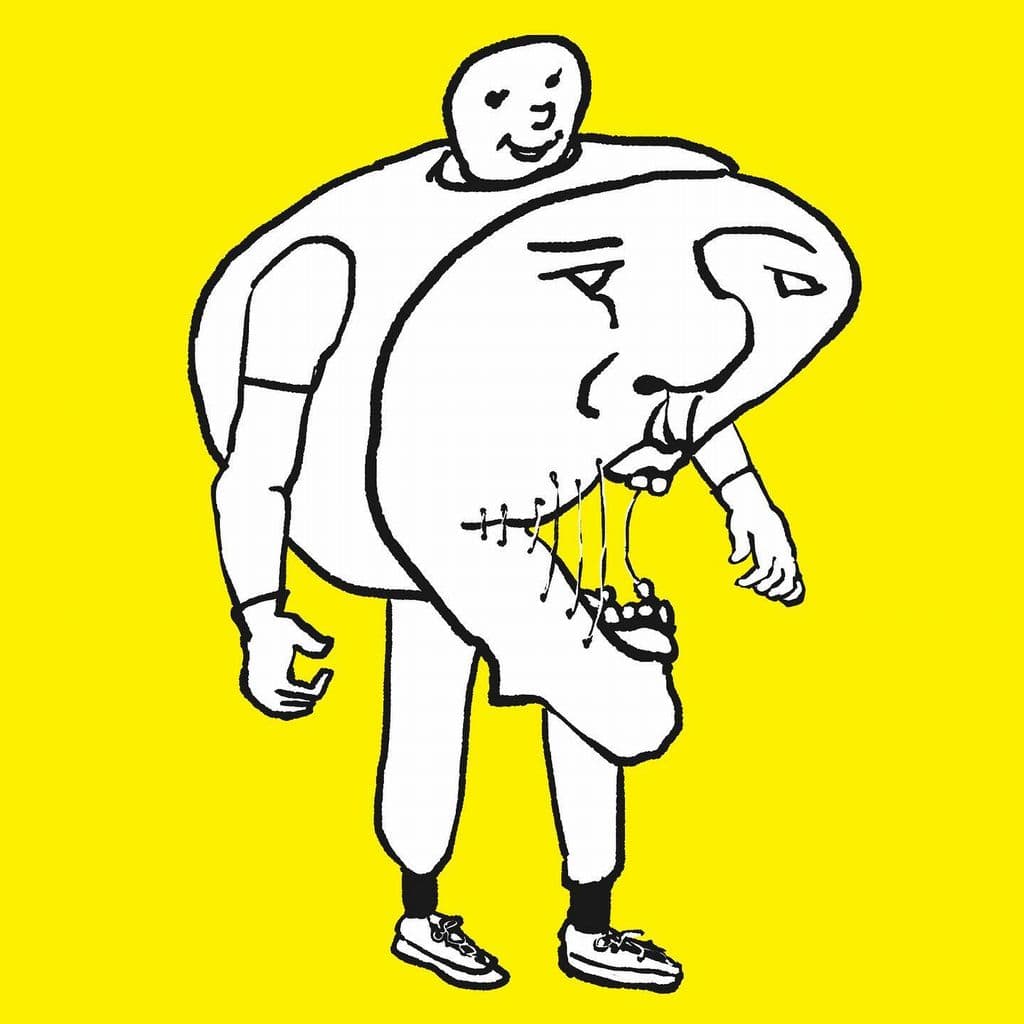




















コメントを残す