四国のド田舎から東京デビューを果たしたのは10年前。目白にある女子大へ入学したわたしは、大学2年の後半から池袋のガールズバーでバイトを始めた。
そこで築いたコネをフル活用して、就職したのはルイ・ヴィトン表参道。美意識の高いオシャレ人間たちに囲まれながら、わたしはそれなりの都会生活を謳歌している。
住まいはもちろん港区。でも道を挟んだ向かい側は五反田という立地。正直、場所なんてどこでもいい。「港区女子」の称号を手に入れるためには、たとえ隅っこでも港区の住民票を死守すればいいわけで。
事実、港区民であるわたしは嘘偽りなく「港区女子」としてチヤホヤされている。
大学を卒業してもう6年。たまに会う同級生たちは、そんなわたしの生活に羨望の眼差しを送る。
ーーただ。
このマンションで過ごす「夜」さえ変われば、本当に輝かしい東京ライフといえるのに。
*
夜21時すぎ。
502号室の住人が帰宅する。わたしの部屋は角部屋なので、唯一の隣人がコイツとなる。3年も住んでいるのに、マンション内ですれ違ったことは一度もない。それでもわたしはコイツの顔を知っている。
ハゲデブメガネのくたびれた中年ーー。
言葉は悪いがそれなりのことをしているのだから、こう言われても仕方がない。このオッサン、気分が良いと大声で歌いはじめるのだ。しかも音痴でドヘタクソ。さらに歌うだけでなく、テレビを見ながら大声で笑うのだ。何度も手を叩きながら。
許せないのはオッサンのいびき。毎晩、地響きのようにわたしの部屋まで轟いてくる。たまに聞こえる寝言など、鳥肌モノで気が狂いそうになる。おそらく、部屋の壁を挟んですぐそこにオッサンが寝ているのだろう。想像するだけで吐き気がする。
挙句の果てには先日、ベランダのガラス戸を開けて網戸にしていると、オッサンが吸うタバコの煙が入ってきた。たまりにたまったわたしの鬱憤(うっぷん)は大爆発。外れそうな勢いで網戸を開けると大声で、
「ベランダでタバコ吸ってんじゃねーよ!煙が入ってくんだよ!」
と怒鳴ってやった。カランと灰皿を蹴る音がしたが、わたしはドアを派手に閉め室内へ戻ったのでその後は知らない。
こうなると容赦はしない。夜中にいびきが聞こえはじめると、壁を思いきり蹴ってやった。蹴りながら罵詈雑言を浴びせた。その瞬間、いびきが消えたのでさすがに気づいたのだろう。
翌朝。
玄関のチャイムが鳴る。ドアレンズ越しに外を見ると、脂ぎった丸顔に黒縁メガネ、ハゲで太ったオッサンが立っている。ヨレヨレのスーツをだらしなくまとい、見るからに仕事のできない"窓際"の人間。
見たこともないオッサンだが、わたしはすぐにピンときた。
ーー隣人だ
食洗器からそっと包丁を取り出す。隣人がバットでも持っていると包丁だけでは分が悪い、盾代わりにフライパンも準備しておこう。
音をたてないようにフライパンを取り出すと、逆の手で包丁を握りしめ玄関へと向かう。
そして再びドアレンズを覗くと、そこにオッサンの姿はなかった。
*
社員2名、今にもつぶれそうな出版社に勤務するぼくは、今年50歳を迎える。お恥ずかしながら現在、離婚調停中の身だ。妻からのDVだけでなく、我が子からも罵倒される日々で身も心もボロボロだ。
ぼくは、青梅線の終点から原付を10分ほど走らせたところにマイホームを建てた。しかし片道2時間半の通勤はさすがに堪えるため、会社近くの安い部屋を借りてもらうことにした。
築15年。古くも新しくもないマンションだが、目下の悩みは隣りに住む女性が、なんというか、すこしおかしいことだ。後ろ姿は何度か見かけたことがある。宅配ボックスから荷物を取り出すと、その扉を足で蹴って乱暴に閉めたり、ポストに入っているチラシをぼくのポストへ詰め込んだり、あまり素行の良い人ではなさそうだ。
ああいう人間とはなるべく関わりたくないーー。
そう思いながらベランダでタバコを吸っていると、突然、隣りから大声で怒鳴られた。
たしかに煙がそちらへ流れてしまったことは謝る。しかし、いきなりあんな風に怒鳴り散らすことはないだろう。あまりにビックリしたせいでスマホが手から滑り落ち、画面が割れてしまった。
さらにその日の夜のこと。
夜中の3時すぎだろうか。突然、壁を叩く音で目が覚めた。同時に女性がわめき散らす声も聞こえる。ぼくはもはや恐怖しか感じなかった。壁を叩く音は30分続き、その間ずっと何かを叫んでいた。
このままでは本当に精神が崩壊してしまうーー。
翌朝、覚悟を決めたぼくは一言お願いをしようと、501号室のチャイムを鳴らした。明るかったドアレンズが暗くなる。中からこちらを覗いている証拠だ。そしてまたすぐに明るくなった。しかしドアは開かない。
ーーハッ、もしかすると!
ぼくは身の危険を感じた。この女は刃物を持って襲い掛かってくるかもしれない。ただでさえ離婚騒動で滅入っているところへ、更なる事件などまっぴらだ。
ぼくは慌ててその場を去り、エレベーターのボタンを連打した。ここは5階、エレベーターは今1階にいる。到着を待っていたら半狂乱の隣人に殺されるーー。
使ったことのない非常階段をダッシュで駆け降りる。運動不足がたたって足がもつれて転びそうになる。だが殺されるよりマシだ。
そして走りながら考える。
ーー午後、半休をもらって新たな部屋を探そう。
ぼくはまだ死にたくない。少なくとも、あんな異常者に殺されたくはない。
(完)



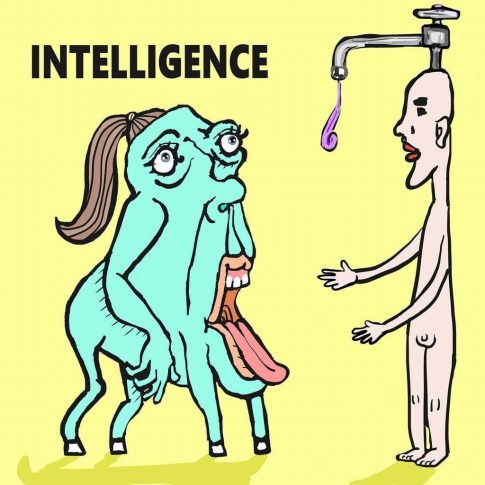


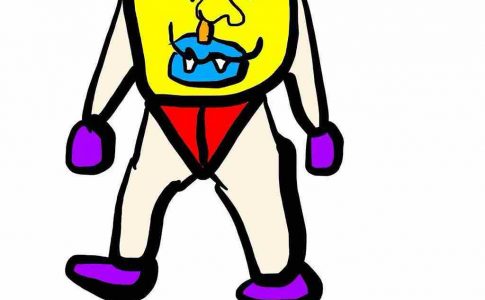


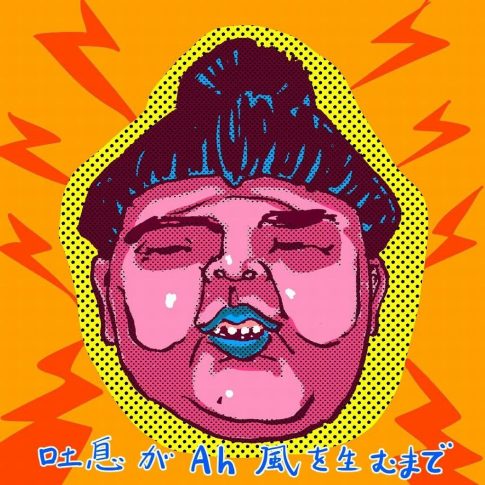











コメントを残す