ずっとずっと疑問に思っていたことがある。
「なんでわたしが犯人だと疑われたのだろう」
大人になった今でもこの謎は闇の中だ。
*
わたしが小学生の頃。当時はまだ「給食費」というものを現金で担任へ渡す仕組みだった。専用の茶封筒に押印してもらい、支払い完了。
教室に立派な金庫があるわけでもなく、担任が各々で現金を管理していた時代。取っ手のついたスチール製の保管ボックスに給食費を入れ、それをどこかへ持って行くことで処理していたようだ。
小学校低学年の児童にとっては「現金」の価値など分からない。分からないわけではないが、少なくともわたしは現金がほしいと思ったことは一度もなかった。むしろ今でもそう思う。
小学3年の春。担任から、
「話があるから放課後ちょっと残って」
と言われた。担任から特別なにかを頼まれる可能性があるとすれば、合唱コンクールでピアノ伴奏をしてほしいという程度で、わざわざ放課後に話す内容でもない。もちろん怒られることもしていないし、どんな用事があるのか皆目見当がつかなかった。
そして放課後、クラス全員が教室から消えたところで担任は口を開いた。
「最近はどうだ、楽しいか?」
「なにかほしいもの買ったりした?」
どうでもいい会話を始めた。特段変わりない日常を過ごしていたし、ほしい物もないので適当に返事をした。そんなしらじらしい会話をしばらく続けたあと、担任は大きく息を吸い込むと本題に切り込んだ。
「じつはさ、給食費がなくなったんだ」
なんのことかピンとこなかった。給食費はわかる、毎月茶封筒で提出しているアレだ。それがなくなった?自分でなくしたのか?誰かが持って行ったのか?そして何のためにわたしにそれを宣言するのか?まるで理解できない。
黙って聞いているわたしの顔をまじまじと見ながら、彼はこう斬りつけた。
「おまえが盗んだんじゃないかと思って」
一瞬、その言葉は日本語に聞こえなかった。
ーーわたしがぬすんだ?
その後、堰(せき)を切ったように担任が話し出す。ーー先生はここに給食費を置いた。あの時、ここら辺に集まっていた生徒は誰と誰と誰だった、そこにおまえもいた。そしてお金を盗むというずる賢い頭を持っているのはおまえくらいだ。怒らないから給食費を返してくれないか。
記憶があいまいだが、このようなことを言われた。
その時わたしが思ったことは、否定や絶望、怒り、悲しみではなく単純に
「よくもそんな根拠のない理由で、わたしを犯人扱いできるな」
ということだった。
今思えば小学3年にしてはかなり”ませた”考えだ。担任から「おまえが給食費を盗んだ」と疑われたことは誰にも話さなかったが、これが現代ならば大問題だろう。そもそも現金を学校へ持参するなど、今はもうやっていないのだろうけど。
ーー悲劇‼︎教師から「給食費を盗んだ」と罪を着せられた小3児童、自殺。
この場で改めて断言するが、わたしは給食費など盗んでいない。今も昔も「金」に興味はない。ましてや人の金など論外中の論外。
その後も2時間ほどこってり絞られた。まるで取り調べを受ける容疑者のように。
あの時のわたしに「冤罪(えんざい)」という言葉は馴染みもなく、なぜ自分がこのような状況に立たされているのかをずっと考えていた。何もしていないのに犯人扱いされる苦痛とずっと向き合わされていた。
給食費がどこにあるのか問いただされる。
給食費を何に使ったのか追及される。
頼むから返してくれと土下座される。
あげくの果てには、おまえの他に誰が盗むんだと逆ギレされる。
逆ギレついでに蹴り飛ばした机が派手に倒れ、引き出しの中身がそこらじゅうに散らばる。
ーー心臓をギュッとつままれる思いがした。
夕日も沈み暗くなったころ、ようやく取り調べから解放。教室を出ると友だちが2人、階段に座って待っている。わたしが一人で残されたことを心配してくれたらしい。
「おこられたの?」
うまい言葉が見つからない。
「ううん、なんか色々聞かれたけどよくわかんない」
なぜか、なんとなく担任をかばう返答をする。それ以上は友だちも聞いてこなかった。子どもなりに何かを感じ取ったのだろう。
いつもより遅すぎる時間、真っ暗な田舎道を3人で歩いて帰った。
*
人から疑われるということはあれが初めての経験だったし、何年たってもあの衝撃は衰えない。
担任はさらにわたしを追い詰めようとしたのか、はたまた真犯人へプレッシャーを与えるためだったのかは不明だが、「取り調べ」の翌日の国語のテストでこんな問題が出た。
つぎの漢字にふりがなをふりなさい
①先生の給食費がぬすまれた
②犯人はうそをついている
このやり方はえげつない。思い出したくもないが、胸がえぐられる感覚が脳裏に焼き付いている。
どんなに「わたしはやっていません」と言っても信じてもらえない。味方はいない。誰にどう助けを求めればいいのか、わからない。
小学3年の無知で無力なわたしには、為す術もなかった。
*
結局、何十年経った今でもあの時のことが記憶から消えないわけで、わたしの脳と心によっぽどの影響を与えた出来事、いや事件だったと思う。
仮に今、同じ状況で同じ取り調べを受けたとして、果たしてわたしはなんて答えるだろう。
ーーやはりあの時と同じ答えしか出てこない。
「知りません」
「わたしはやっていません」
これ以外に口にできる言葉は見つからない。何年たっても、何百年たっても、この事実は変わらない。
Illustrated by 希鳳








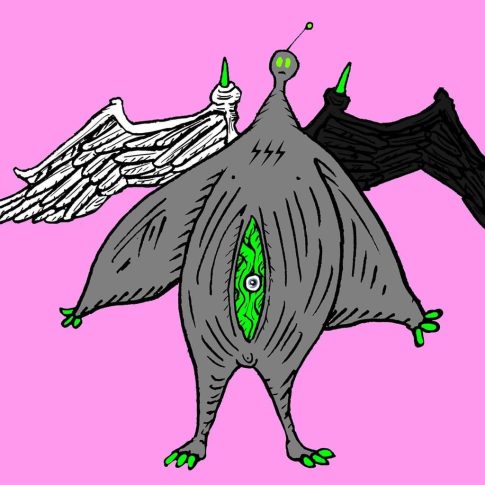












切ないなー😢
私だから耐えられたのだと思う。
口にしたくもなかったし、涙も出なかった。
ただ、その担任が転勤になるまで、毎日「そういう目」で見られ続けたことは忘れない。