文章を読むのが不得意なわたしへ、友人がまた本を送りつけてきた。ありがたいことに、作者の筆致とわたしのそれが似ているというお世辞付きで。
この分厚いハードカバーの単行本を読み切らせるには、そのくらい持ち上げておかなければ無理だろう、と踏んだのだ。
ーーそれ、正解。
ところが驚くほどあっという間に読めてしまったので、もう一度読み返している。2度目はなにか変わるかな、と思いながら進めるも、最初より明らかに「とある友人」が描かれているだけで、なんの代わり映えもしない。
あっという間に読めた理由は、内容が面白いからでも、読みやすい筆致だったからでも、速読ができるからでもない。
シンプルに、わたしが考えることがそのまま書かれていたことに驚いたからだ。そして、登場するはずのないかつての戦友が、見事に描かれていたからだ。
*
アマゾンから届いた本の表紙を見る。
(・・女性が書いた本か)
「今夜、すべてのバーで」というややシャレたタイトルで、さほど読書欲をかき立てられるものではなかった。
だが、送り主の友人は相当にわたしを理解している人間ゆえ、彼が間違うはずがない。その信頼だけを頼りにページをめくる。
「普段からこんな色なんですか、あんたの目」
医者がおれの上下のまぶたを裏返してのぞき込む。
ーーあれ、男なのか?
慌ててわたしは作者の名前を検索する。
「中島らも」
正真正銘の男で、しかも若くしてすでに亡くなっているではないか。一見、男女の判別ができない名前は多いが、まさか「らも」が男だとは思いもしなかった。
そして導入部の書き出し、まるでわたしの「とある友人」が話しかけるような言い方なのだ。一行目にしてぎょっとする。
「はあ。ま、どっちかっていうと濁ってるほうですが。でも、すこし黄色っぽいかな」
「”すこし”じゃないでしょう。顔の色だってほら、まっ黄色だ」
「黄色人種だからね」
おれは口をきくのもだるかったのだが、癖で軽口を叩いてしまった。
冒頭の6行で確信した。中島らもは、わたしの「とある友人」だ。あいつはこんなペンネームで本を書いていたのか。
わたしには腐れ縁の友がいる。だが、もうかれこれ5年以上会っていない。
そいつの特技は「減らず口をたたくこと」「悪態をつくこと」で、仮にわたしが「顔が黄色い」などと言えば「黄色人種だからな」と、間違いなく返してくる。「偉そうな言い方するね」といえば「偉いんだからしょうがない」と返してくるような、屁理屈のかたまりというか。
ーーあいつは今、なにしてるんだろう。
*
中島らものこの本は、アルコール中毒で肝硬変一歩手前の主人公が、いつ死んでもおかしくない状態で病院を訪れたところから始まる。トリスバーで朝まで飲みあかし、昼間っからバーボンをあおって原稿を書く、文士気取りのエッセイスト(ルポライターでもある)の主人公。
こいつの動向や思想、人間性までもが音信不通のあいつそっくりだった。
わたしがあいつの「健康」に気を使ったことは一度もないが、彼の家で
「のど渇いた」
と言ったら、咄嗟(とっさ)に缶ビールを渡された時はイラっときた。
「水、ないの?」
と聞くと、
「水みたいなもんだろ」
と、突っ返した缶ビールを自ら開けてグビグビ飲み始めた。そして瞬く間に2本目のプルタブに指を掛けた時には「死ねばいいのに」と真剣に思った。
いつからか連絡の頻度が減り、もうずいぶんと経つ。もしかすると本当に死んでいるのかもしれないなーー。
*
さっきわたしは、中島らもが「腐れ縁の友」だと言ったが、正確には違う。中島らもがわたしで、主人公が友人だ。
ページをめくるごとにあいつの描写がつらつらと並べられており、本当にこれは「あいつ」なんじゃないかと疑いたくなるほど。
わたしから見た友人が、そこに見事に描かれているのだ。
本を読むことの意義は分からない。だが、読書から他人の空似(そらに)のような現象を味わうことで、一種の懐かしさと切なさを落とし込まれたのは貴重な経験だと感じる。
ーーまだ生きているのかわからないあいつのメールアドレス。なにか送ってみようか。
Illustrated by 希鳳







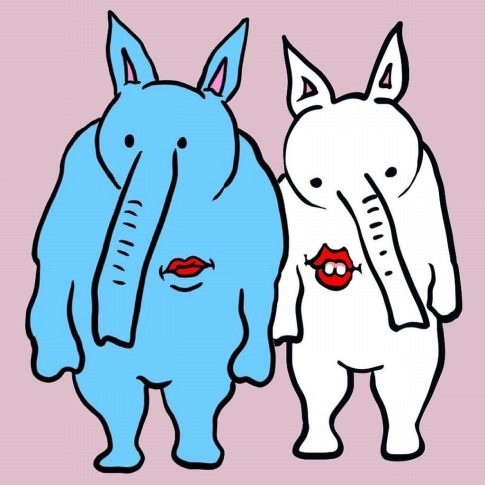













コメントを残す