わたしのピアノの先生の先生・・すなわち「師匠」のところへ通い始めて、もう少しで一年半が経過する。教わっていることといえば、相変わらず「音の出し方や曲の表現方法」といった概念に近い抽象的なことばかり。よって、使用している楽曲は40番ツェルニー(必ずといっていいほど誰もが使う練習曲)で、いわゆる”演奏会で披露する作品”というのは一度たりとも弾いたことがない。
そして上達度は・・というと、さすがに入門当初よりはできることが増えたが、やはり未だに音のバリエーションは少なく、どこか力任せでぶっきらぼうな演奏である。まぁ、偉そうに言うことではないが、たった一年半で師匠の技術を盗み得ることができたならば、それこそわたしは天才だし、音楽の世界で生きていくべき人間といえる。
そんなわけで、「正しい音の出し方」という眩しすぎて見えないいゴールへ向かい、壮大な迷路を手探り状態で進んできたわたしは、とある岐路に立たされた。それは、師匠が放ったこのセリフによるものだった。
「師匠というのはいつか必ず死ぬものです。だからこそ、あなたが自家発電できなければ意味がないのです」
これまでは、師匠の言うとおりに足を使い腕を動かし音を出してきた。そして毎回、師匠から与えられた課題をクリアするべく練習を重ねてきた。ところが、今日からはわたし自身で考えて弾くようにしなさい・・というではないか。
「私が言ったとおりに、ちゃんと弾こうとしている・・それはそれで正しいのよ。だけど、あなたは何をしたいの?という部分が聞こえてこないのよ」
たしかにその通りかもしれない。正直なところ、自分自身で何をどうしたいという気持ちがない・・というか分からないわたしにとって、師匠からの助言を忠実に実行することくらいしか、演奏の目的というものが存在しないからだ。
だが彼女は、わたしが何をしたいのか——要するに、わたしが「どんな音楽を聞かせたいと思っているのかを示しなさい」と言っているのだ。
(そんなこと言われても・・わたしにはそういった感覚がない。そもそも、音楽や芸術性に乏しい大食いの筋肉ゴリラに、そんなハイレベルな要求をされても応えようがないというか・・)
すると師匠は、このようなたとえ話を挙げてくれた。
「お腹いっぱいのところへどんなに素晴らしいご馳走を出されても、『う~ん・・もう要らないわ」となるでしょ。だけど、美味しそうに何かを食べているヒトがいたら、『あら?何を食べているのかしら』って、ちょっと興味をそそるじゃない?そういう演奏を聞かせてほしいのよ」
——なるほど、そういうことか。
師匠の門を叩いた当初から、一貫して「自分が出す音を聞きなさい」と言われ続けたわたしは、その意味を分かっているようで正しく理解していなかったことに気が付いた。
たしかに音は聞こえているし、ちゃんと聞こうとしていた。だがそれは、外部から内部に向かって耳を傾けている・・というか、表面上の音を聞こうとしているだけで、平面に描かれた立体的な絵を見て3Dに触れようとしている感覚に近かった。
平面の絵はどこまでいっても平面にしかない——そこからリアルな凹凸へたどり着くことはないのだ。
さらに思い出すことがあった。それは、多くの友人・知人から「ほんと美味しそうに食べるよね」と褒められることだ。実際に美味しいからそう見えるのだろうが、少なくともわたしは「美味しそうに食べられる」のだから、そういう演奏をすればいいってことだ。
今までは師匠の教えに忠実に、言われたことをすべて詰め込んで「これでもか!」という勢いで押し付けてきた——そう、押し売り状態のピアノだった。だが、それでは確かに「もう十分なのでご遠慮願いたい」となる。そのような押し付けがましい演奏ではなく、相手の興味をそそるような溢れ出る衝動の提示・・北風と太陽のような演奏が理想なのだ。
(美味しいものを「美味しい!」と感じること。その状態こそが「何をしたいのか」ってことなのか。わたしにしかできない「自家発電の演奏」っていうのは、要するに「美味しそうにおむすびを食べること」と同じなのか)
そう悟った瞬間、外から内へ向いていた耳のベクトルが、内から外へと切り替わった。わたしはどんな音を出しているんだ?どれが快適な音なんだ?——いま初めて、わたしは「音」を聞くことができたのである。
*
師匠のレッスンは毎回”目から鱗”の連続だが、ピアノや音楽を教わる以上にヒトとしての在り方を教わっている気がする。
そして改めて感じることだが、年長者から得るものは大きい。それに気付いたうえで己のものにできるかどうかが、若輩者の技量というか義務なのかもしれない。



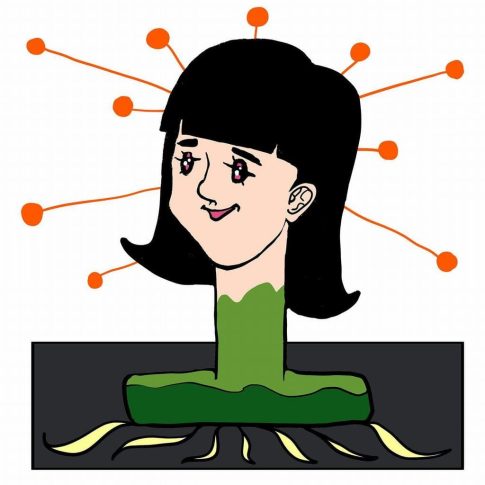



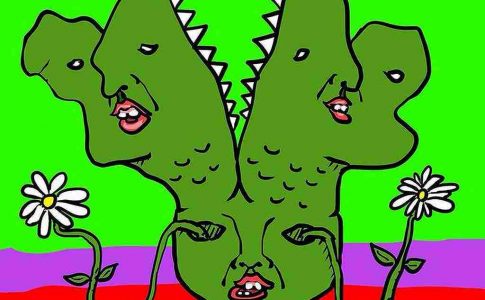













コメントを残す