自宅におけるピアノ練習で必要なことは、「こういう音が出ているに違いない」とイメージしながら弾くことだ。
なぜ「出したい音を出す」のではなくイメージなのかというと、我が家のピアノが電子ピアノだからである。
正確には、アップライトピアノの鍵盤(ハンマー)の裏に消音装置を取り付けているので、打鍵の重みや感触はアコースティックなのだが、聞こえる音は電子制御されている・・すなわち「スイッチ」のオンオフが繰り返されることで音が出る仕組みのため、実際のピアノと比べると音のレンジが極体に狭いのだ。
とはいえ、強弱に関しては4段階くらいの幅はあるが、響きに関しては幅どころか皆無——まぁ電子ピアノなんだから当然ではあるが、要するに自宅のピアノでどれほど練習しても、よそでアコースティックピアノを弾けばその差は歴然。
その結果、「こんなにも音がデコボコだったなんて・・」と、恥ずかしさを通り越してショックを受けるのであった。
*
「ここの長いスケール、一息で弾き切るからもっとキラキラした音がほしいんだけど」
先生からそう言われたとき、わたしは困った。なぜなら、自宅で練習する分には粒の揃った音が出る——というか、そういう音にしか聞こえないため、逆に言うと「粒の揃った音にしかならない」のが電子ピアノの恐ろしさ。そのため、どうしたらキラキラした音が出せるのか分からない——。
そんな事情もあり、レッスンの際はいつも”その場で生練習”が開催されている。本来、一週間の練習の成果を披露するのがレッスンというものだが、わたしにとっては「一週間分の生練習をここでやる」という、本末転倒も甚だしいスタイルなのだ。
だからこそ、わたしは必死だった。
この時期に半袖姿でレッスンを受けているにもかかわらず、レッスンが終わる頃には汗でびしょ濡れになるほど、神経と体力をフル稼働させて挑んでいる。といっても、そうしたくてやっているのではない。自宅のピアノとはまるで違うこの楽器に、必然的に苦戦を強いられた結果がそうなるだけで。
だが、このレッスン中に音の響きや打鍵の深さを覚えておかなければ、次回までの一週間が無駄になる。自宅練習では決して出すことのできない・・いや、聞くことのできない音を感覚で覚えることで、耳では聞こえなくとも脳で感じることができれが、少なからず練習になるからだ。
むしろ、覚えるのは”体の使い方”かもしれない。足や背中、胸の感覚を覚えることで、耳で確かめることはできなくても体で再現できる。そうすれば、電子ピアノであってもアコースティックピアノと同じ感覚で弾くことができるはず——。
というわけで、理屈ではたしかにその通りなのだが、当然ながらそうは問屋が卸さない。スタジオでグランドピアノを弾いてみると、やはり音がデコボコだったり、ただうるさいだけの乱暴な演奏だったりと、なんのために自宅練習があるのか分からないくらいに酷いありさまなのだ。
(こんなことなら、家では弾かないほうがいいんじゃないか・・)
まさにその通りである。間違った練習を繰り返すことで、間違った感覚が身についた結果、それを正すのに倍以上の労力がかかる——そして汗だくになりながら、レッスン中に修正しているのが・・・このわたしではないか!!
ヒトというのは根が真面目だからか、それとも臆病だからかは分からないが、練習をしないと不安を覚える生き物である。だからこそ、それを解消するべく指を動かし時間を費やし「練習したつもり」になっては安堵する。
だが実際に必要なのは、その練習が正しいかどうかだ。何時間練習しようが、間違った感覚を叩きこむくらいならばやらないほうがマシ。だったら、正しいイメージを抱き続けるほうがよっぽど意味がある・・つまり、音を出さずに弾けばいいんじゃ?!
こうしてわたしは、ヘッドフォンを外して無音状態で練習することにしたのである。
音が聞こえるとそちらへ意識が向くため、指や体の感覚を疎かにしがち。だが、音さえ聞こえなければフィジカルに集中できるわけで、どうせレンジが狭くてリアルな音が出ないならば、そんなものをわざわざ聞く必要もない。
そして、こんなことが出来るのは、消音装置がついているピアノだからこそ成せる業——むしろ、ラッキーじゃないか。
*
これぞ、究極の負け惜しみ・・いや、究極のポジティブシンキングなのである。



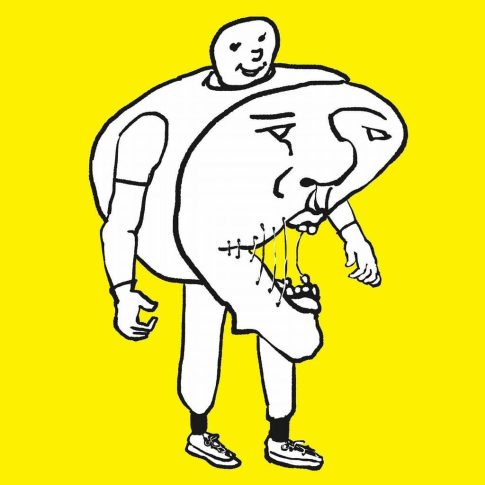




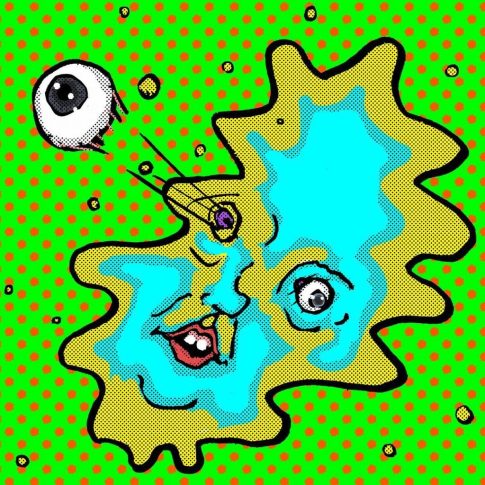

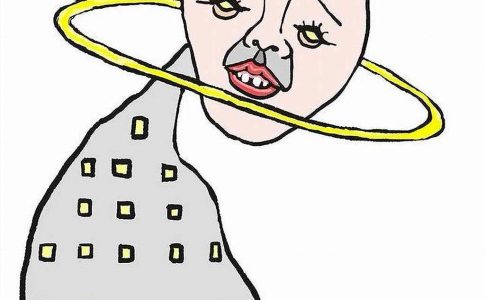










コメントを残す