ここ数日で出会った人々の多くが、夏風邪をこじらせている・・という状況に驚かされた。
滅多に体調を崩さないわたしからすると、このクソ暑い時期に風邪をひいて寝込むとは、拷問に近い仕打ちである。しかもその多くが、熱は下がっても咳が続いている様子で、汗だくになりながらもマスク着用を強いられるという、なんとも哀れなありさま・・。
たしかに、咳というのはやっかいな症状で、他人が咳をすると反射的にイラっとしてしまうのだが、これは生物的な本能たる「自己防衛反応」のせいである。なぜなら人間は、咳(飛沫する唾液)を介してウイルスなどの病原体に感染することから、遺伝子レベルで嫌悪感を示すのだ。
そのため、咳嗽という行為は言い換えれば「攻撃」に当たり、無防備な自身に対する悪意ある攻撃として、不快を通り越して殺意を抱くことすら——。
しかしながら、仕事によっては至近距離でやりとりをしなければならない場合もある。たとえばピアノの先生がそれに当たるが、複数の生徒を相手に入れ代わり立ち代わりレッスンを行うため、高確率でウイルスなどの病原体を取り込みがち。
つい先日も、喘息持ちの子どものレッスンをしていた際に、咳の感じがいつもと違うな・・と思い尋ねたところ、「風邪をひいたが、もう治った」と言われたのだそう。しかしながら・・というか案の定、先生はその翌日から体調を崩し、最終的に咳だけが残る状態となっていた。
このように、先生一人で複数の生徒を抱える場合、しかも狭い部屋で一定時間を過ごさなければならないとなると、感染症のリスクは否が応でも高くなる。もちろん、うがい手洗いやマスクを徹底するわけだが、それでも防ぎきれないことはある。となるとやはり、自分自身の免疫機能を向上させるしかないわけだ。
同様に、弁護士の友人も夏風邪に苦しまされていた。二日間寝込んだものの未だ回復には至らず、仕事上のキャンセルをやむなくされているとのこと。
こちらの仕事もピアノの先生ほどではないにせよ、クライアントとの面談や会合へ参加する際に、秘密保持の観点からも密室にて長時間拘束されがちなことから、なんらかの病原体をもらう可能性は高い。
無論、それだけが原因ではないだろうが、職業柄からも健康に留意している彼ですら、こうやって夏風邪にやられてしまうのだから、とにかくウイルスという奴は恐ろしいのである。
ちなみに、なぜ夏風邪が長引きやすいのかというと、ウイルスに対する特効薬がない=自然治癒に委ねるしかないからだ。
夏風邪として有名なウイルスは、エンテロウイルス(手足口病、ヘルパンギーナなど)やアデノウイルス(プール熱、結膜炎など)だが、これらのウイルスに対する治療薬というものは存在しない。そのため、医療機関を受診しても対症療法しか選択肢がないことから、自宅で安静にすることが効果的な治療となる。
加えて、これらのウイルスは高温多湿な環境で活性化しやすく、腸管などの粘膜にしつこく残り続ける・・という特徴がある。おまけに、環境耐性が強く治ったと思った後もしばらく残存することから、完治に時間がかかったり再感染のリスクがあったりと、夏独自の厄介な特徴があるのだ。
ちなみに、冬風邪の代名詞でもあるインフルエンザは、ウイルスの構造について非常に研究が進んでおり、それによって特定の酵素を標的とする薬——すなわち、抗ウイルス薬であるゾフルーザやタミフルなどが誕生している。
「ならば、夏風邪のウイルスにも特効薬を作ればいいじゃないか!」
・・そう考える素人さんは、これらの研究にどれほどの時間とカネが必要となるのかを調べてみてほしい。
ウイルスというのは種類が多い上に変異も激しく、重症化せずに数日から一週間で完治してしまうとなれば、コスパの点からも薬の開発が難しいのは当然のこと。さらに、副作用とのバランスを考慮すると「作ろうと思えば作れるが、現実的ではない」という結論に至るのだ
なお、インフルエンザ治療薬として有名なタミフルは、基礎研究を含めると10年の開発期間を有し、その費用は500億円以上とされている。同様に、日本が誇る塩野義製薬が開発したゾフルーザは、開発期間はおよそ9年で費用は400億円前後とのこと。
いずれにせよ、これだけの莫大な期間と費用をついやしてまで、特効薬を生み出す必要のあるウイルスかどうかが、研究開発の必要性の是非につながる。そのため、夏風邪に対しては「残念ながら、しばらくの間じっとしていてください」というのが、今のところの第一選択たる治療なのである。
・・そんなわけで、夏風邪のウイルスに体内を侵略されている皆さんは、数日の間は”静かなる戦闘”に専念するべく頑張ってもらいたい。








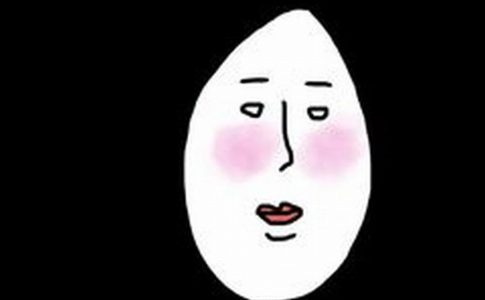












コメントを残す