二時間の邦画を見終えたわたしは、目を輝かせながら鼻息荒く席を立った。とはいえ、こんなにも興奮状態にある観客は、辺りを見回してもわたし一人だったが——。
久しぶりのレイトショーへ足を運んだわたしと友人は、内山拓也監督の『若き見知らぬ者たち』を鑑賞することにした。この作品には多くの友人・知人らが参加しているため、映画館の大きなスクリーンで観なければ失礼にあたると思い、なんとか時間を確保したわれわれは、ポップコーンとメロンソーダを片手に4番シアターへと駆け込んだのだ。
レイトショーにもかかわらず、シアター内は予想以上に埋まっていた。さらに面白いことに、カップルや友人と一緒にではなく、一人で観に来ている客がほとんど。ちなみに、見終えてからの感想ではあるが"単独で足を運ぶ"という客層の在り方も、この作品を象徴する現象に思えるのであった。
そして、ある意味"問題作"ともいえるこの作品は、いつしかわたしを懐かしさで包んでいった。誇張することなくリアルに再現された挙動やセリフ、細部にわたるまで忠実に演じ切る表情やしぐさ、加えて"これ以上の現実はない"というほどウェットで生々しい生活環境が、めくるめくスクリーンに映し出される——。
そう・・かつて仲の良かった友人親子を思い出していたのだ。
(あぁ、あの時とまったく同じじゃないか。これは紛れもなく、リアルな社会の一部を切り取った作品だ)
*
主人公の母は、指定難病である「前頭側頭葉変性症(前頭側頭型認知症)」を患っていた。この疾患は、前頭葉や側頭葉が委縮することで認知機能に障害が出るため、日常生活が著しく困難となる。さらに父親は、仕事のミスが引き金となり精神を病んだ結果、借金を残したまま他界している。
そして残された息子二人・・とくに兄は、将来を有望視されていたサッカー選手だったが、自身の夢を諦め母親の介護を献身的に行っている。おまけに、父親の借金返済のために昼は現場作業で汗を流し、夜は両親が開いたカラオケバーを切り盛りしていた。そんな彼の心の拠り所は、看護師である恋人の存在だったが、彼女もまた主人公一家の闇に片足を突っ込んでいるため、精神的に疲弊していくのであった。
唯一、主人公の弟が総合格闘技の試合でタイトルを手に入れたことが救いだったが、その時点で兄は事件に巻き込まれ死亡しており、母は認知機能が正常ではないので理解できず、前出の父はすでに他界・・という、手放しで喜べないシチュエーションで幕を閉じるのであった。
それにしても、あまりに正確な描写で驚かされたのは、前頭側頭型認知症である母の疾患特有の行動や言動、そして室内の状況だった。なぜそこまで驚いたのかというと、まるで友人の母親を見ているかのようだったからだ。
当時、友人宅は不用品で溢れ汚れていた。おまけに、母親が置いた物を動かしたり部屋の状態を変えたりすると、気が狂ったかのように激高するため、勝手に片付けることは許されなかった。
そして最も衝撃だったのは、彼女が集めた"自身の髪の毛とツメの残骸"が、何か所かに分けて飾られていたことだ。"飾る"という表現は相応しくないかもしれないが、明らかに目立つ場所へまとめて置かれているので、わたしからすると「飾ってある」と感じたのだ。
母親の常同行動や人格・行動の変化により、社会生活がみるみる困窮していく親子の様子を、わたしは近すぎず遠すぎず見守っていた。
同じ店で万引きを繰り返したり、他人に対して失礼な発言をしたり、味覚の変化によりとんでもない塩分を摂取しても気がつかなかったりと、常に誰かの介護と監視が必要な状況にある母——。それでも友人は、笑顔で彼女をなだめるのであった。
すべての責任を一人で背負い歩き続ける後ろ姿からは、他人の介入を一切許さないオーラが感じられた。それはある種の家族愛だったのかもしれないし、運命の呪いだったのかもしれない。
・・そんな絶望的な人生と酷似した現実を、この映画は過不足なく描いていたのである。
しかもそれだけではなかった。一緒に映画を観た友人は大学病院で薬剤師をしているが、作中に出てくる病棟での申し送りや薬剤の説明について、「完璧に再現されていた」と、真顔で教えてくれた。
おまけに、格闘技の世界に身を置くわれわれにとって、選手やセコンドの演技に対する評価が辛辣になるのは仕方がないこと。にもかかわらず、こちらがのめり込んでしまうほどの臨場感とテクニック、そしてセコンドの会話や態度が、実際の試合と比べてまったく遜色のない内容だったことには興奮を覚えた。無論、現役の格闘家やプロの指導者らで固めているため、行動・言動が本物っぽい・・というか、本物であるのは当然なのだが。
そして、病院内でのやり取りや格闘技のシーン、認知症の母親や家庭内の様子など、どれをとっても徹底的に現実を反映させている点は、わたしや友人が経験しているからこそ真偽の程が分かるわけで、ここまで鮮明かつ緻密に再現するには、相当なリサーチと勉強が必要なはず。
(内山監督、そして演者らの熱意と根性、恐るべし・・・)
*
映画館を後にする者は皆、うつむき加減でパッとしない表情を浮かべていた。だがわたしは、他人事とは思えないノンフィクションに触れた興奮と感動で、気分が高ぶっていた。
巷における作品の評価がどうなのかは知らないが、少なくともこの話は"今"を如実に表している。だからこそ、この紛れもない事実は評価されるべきである。そして、ここまで深く掘り下げた心理描写を演じられるなど、今の今まで「あり得ない」と思っていたが、今日、それが可能だということをスクリーンを通して思い知らされたわけだ。
——久しぶりに昔を思い出したわたしは、旧事をしのびつつも迫りくる明日に身を委ねるのであった。





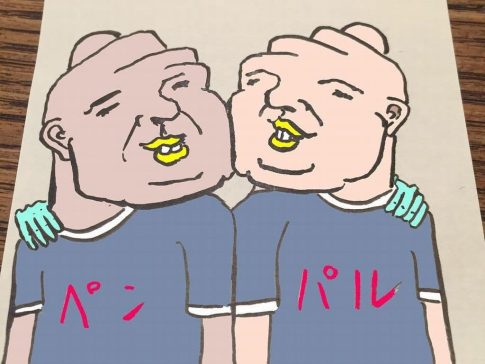















コメントを残す