正直なところ、わたしは"彼"が誰だか分からなかった。なんとなく見たことがある気もするが、このイベントに参加しているメンツとは、過去にどこかで会っている可能性があるので、きっといつかの記憶が残っていたのだろう——。
とくに気に留めることもなく、その他大勢の参加者の一人として彼が披露するパフォーマンスを眺めていた。ところが、手技の最中にわたしと目が合った彼は、一瞬、動きを止めた気がした・・が、気のせいだろう。
その後も変わらぬ様子で、彼は自身の課題を実施していた。
*
わたしは今、ピッツァの大会を観戦するべく都内某所を訪れている。全国から大勢のピッツァイオーロ(ピザ職人)や、本格的なピザ窯でピッツァを焼いてみたいアマチュアたちが集い、制限時間内に規定のピッツァを焼き上げては順位を競っているのである。
この大会の面白いところは、プロとアマが肩を並べて競い合うことができる点だろう。そして、「参加者全員が同じ条件、かつ、最高の薪窯を使ってピッツァを焼ける経験」というのも、そう簡単に実現できるものではないため、遠方からわざわざチャレンジする人が多いことにも頷ける。
さらに、焼き上げたピッツァは審査員用とは別に、われわれ観客の分も用意されているため、テーブルにピッツァが並ぶと一瞬にして消える現象が続いていた。
(次こそは、真っ先に手を伸ばしてやる・・・)
がっつくのもアレなので、後方から静かに見守っていたシロガネーゼ・・もといワタシは、ハイエナの如くピッツァに飛びつく客人たちをじろりと睨むと、5分後に並ぶであろうピッツァを奪取するイメトレを始めた。
「あ、あの・・」
シュッシュッとシャドウボクシングのように、ピッツァをすくい上げる練習をしていたわたしの背後から、突然、誰かの声が聞こえた。振り返ると、先ほどの男性が立っているではないか。
「僕のこと覚えていますか?・・その節は、黙って居なくなって本当に申し訳ありませんでした」
そう言うと彼は、深々と頭を下げた。
一瞬、なにが起きたのか理解できなかったが、脳をフル回転させて点と点をつなげると、ようやく全てが見えてきた。そうか、あの店で働いていた——。
なんと彼は、わたしの顧問先で働いていたシェフだったのだ。あの頃よりもかなり痩せて精悍な顔立ちになっていたため、すぐに思い出すことはできなかったが、言われてみればあの時の彼である。
そして当時を振り返ると、彼はいつからか無断欠勤が続き、気がつくとフェイドアウトするかのように居なくなってしまったのだ。
わたしは社労士という立場上、事業主からの話しか聞くことができない。そのため、場合によっては偏った内容だったり、部分的な側面しか知ることができなかったりする。
そんなことからも、消えていった労働者を慮(おもんぱか)ることは難しいが、仕事で関与する以上は仕方のないこと・・と割り切ることにしていた。
だがそれでも、黙って消えていった"真面目な労働者"のことは、いつまでも頭の片隅に残っているものだった。
(そうか、あの時の・・・しかも料理を続けていたのか)
当時の雇用主からすると、「何も言わずに姿を消した、非常識のならず者!」という認識だろうが、わたしからするとなんだか懐かしく、そして夢を追い続けてくれたことに喜びを感じた。
「料理、続けてくれてたんだね」
思わず笑顔で肩を叩く。すると彼は恥ずかしそうに名刺を差し出してきた。
「今はここで店長をやっています」
前職をバックレてから随分経つが、彼なりに色々な思いを抱えながらも地道に歩き続けた結果である。しかも今では家族も増えて、一家の大黒柱なのだそう。
当時の控え目な印象からは想像もつかないほど、大きく立派に成長した姿がそこにあった。それはまるで、「人生は自ら作り上げるものなのだ」と、彼が体現してくれたようだった。
*
職場の人間関係も恋愛も、うまくいっているときはウキウキのノリノリであり、「痘痕(あばた)も靨(えくぼ)」とは言い得て妙。
ところが関係性にヒビが入ると、加速度的に気持ちが離れていくのも特徴といえる。そしていつしか、別れを切り出せないまま逃げてしまおうか——などと考えるようになるわけで。
とにかく、"別れ話"ほど面倒で厄介でパワーを要する話し合いはない。さらに、責任感が強ければ強いほど泥沼に引きずり込まれるため、だからこそ黙って逃げ出したくなる気持ちも分からなくはないが、やはり幕引きはしっかり行うべきである。
——とはいえ、人間たるもの紆余曲折を経て今日があるわけで、当事者にとったら笑って済ませる問題ではなかろうが、それでも、この世のどこかで「今日」を笑って過ごせているならば、それはそれで「良し」としたい。
だからこそ、彼がいつか前職のオーナーに謝罪する日が来ることを、そしてそこから新たな関係が始まることを、陰ながら期待しているのであった。





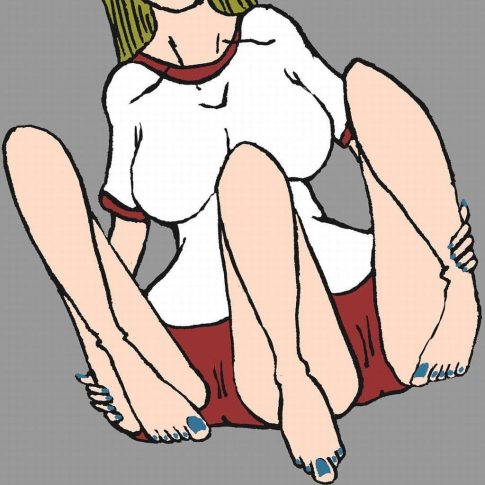


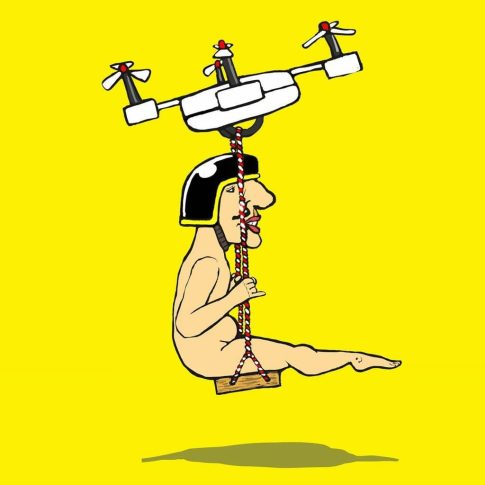

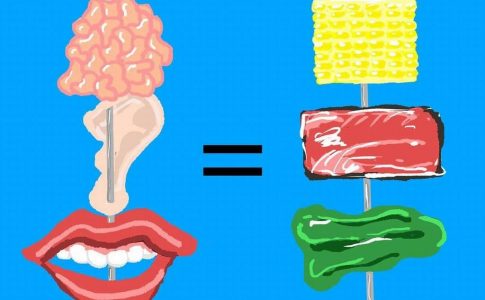










コメントを残す