人の記憶に最も残る感覚は、嗅覚ではないだろうか。
何年経っても私の脳から離れないあのにおい。
そのにおいこそ、人間が生きている証だった。
*
四畳半の古びた和室で正座をする私。
目の前にはうずたかく積まれた布の山。
手ぬぐいのような、包帯のような白い布。
そろそろ西日の差す時間帯だが、そびえ立つ白い山に邪魔をされ、外の景色は見えない。
私はいったい何時間、こうして布をたたみ続けているのだろう。
畳に長時間座っていると体のあちこちが痛くなる。
さらに時計すらないこの部屋では、時間の進み方が異常に遅い。
どれだけたたんでも終わることのない大量の布の正体は、おむつ。
ここは重症心身障害児者の施設。
社会人になりたての私は、関連団体での職場研修の真っ最中。
昨日は国立ハンセン病療養所で一日を過ごした。
*
ハンセン病という名前は聞いたことがあるが、それがどのような病気なのか、どのような歴史を持つのかを知ったのは、日本財団に入職してからだ。
日本財団は1960年代からハンセン病制圧事業に力を注いでおり、医療面と社会面の両方向からハンセン病制圧と差別撤廃のための活動を続けている。
ハンセン病の歴史は古い。
紀元前6世紀のインドの古典やキリスト教の聖書、また日本書紀や今昔物語集にも記述のあるハンセン病。
皮膚にあらわれる斑紋や、知覚障害による身体の一部変形や欠損といった、外見による差別と感染経路不明の恐怖から、患者らは何世紀にもわたり社会的烙印(スティグマ)を押されてきた。
1931年(昭和6年)、「らい予防法」の成立によりハンセン病患者を国立療養所へ強制隔離することで、日本政府はハンセン病の絶滅を目指した。
この誤った隔離政策が差別を助長することとなり、1948年(昭和23年)「優生保護法」の対象にハンセン病が明記され、強制的に避妊手術が行われた。
人間というものは精神的な未熟さゆえ、自ら考えることを放棄し多数派に流される。
いわゆる大衆心理だ。
とくに島国で暮らす日本人にとって、自分たちと異なる人種、たとえば外国人や障害者をこぞって差別する傾向にある。
国立療養所へ追いやられた患者らは、家族も仕事も人権も自由もなにもかも根こそぎ奪われ、そこで一生過ごすことを余儀なくされた。
1996年(平成8年)に「らい予防法」は廃止されたが、入所者は当然に高齢であることや、後遺症による身体障害が残っていることから、ほとんどの人は療養所から出ようとしなかった。
いまさら、失われた人生を取り戻せと言われて何ができるというのか。
私が訪れた国立療養所は、もはや小さな村だった。
敷地面積35万平方メートルの広大な自然の中に、畑や田んぼ、商店、ポストや神社まであり、療養所と知らなければ一般的な集落そのもの。
その外周を覆う深い森だけが、かつての差別の面影を残していた。
じつはここには、華美な賑わいとは縁遠い静かな桜の名所がある。
偏見や差別の根強い1950年(昭和30年)代後半、入所者らは、
「いつの日か、外の人々と我々がこの桜の下で花見をしながら食事を楽しみ、酒を酌み交わす時代が来てほしい」
という願いを込めてたくさんの桜を植えた。
子どもをつくることすら許されなかった彼らは、叶わぬ夢の愛情を桜に注ぎ、大切に育ててきたのではなかろうか。
そう思わざるを得ないほど、美しく立派な桜並木がここにある。
時代が変わったいま、春になると周辺住民らが訪れて花見を楽しむ。
桜の下ではしゃぐ子供たちの声を聞きながら、入所者は何を思うのだろう。
自分たちのひ孫世代であろう子供たちの、キラキラと輝く笑顔を眺めながら。
高齢である彼らは、優しく穏やかな表情をみせる。
それに比べ、あまりに多くの悲しい過去を聞かされた私は、ただ呆然と立ち尽くす。
気の利いた言葉の一つもかけられずに。
*
布おむつの山は一向に減らない。
見渡すかぎりの白い布と、独特の異臭に包まれる私は気が狂う寸前だった。
家具も時計も何もない、時の止まったこの部屋で一人黙々とおむつをたたむ。
おむつには、どんなにきちんと洗濯し乾燥させても消えることのない、独特なにおいがついている。
異臭と言ってしまえば簡単だが、それだけではとても足りない、なんとも複雑で歪んだにおい。
これこそ人間が生きている証、排泄物の変化したにおいだ。
乳飲み子とは違う、年齢を重ねた大人の排泄物を受けとめる布おむつ。
それを一枚ずつ手でたたんで重ねる。
ただひたすら、たたんでは重ねる。
顔を上げれば天高く積まれた布おむつの山。
どんなにたたんでも、決して終わることのない白い布たち。
ここに希望はあるのだろうかーー
*
あのとき何を学んだか、当時のレポートで書くことができなかった。
それどころか未だに言葉で表せない。
だが、人間の闇と強さを知ったのは事実だ。
ーー私はなぜ生きている?
あの四畳半の思い出とともに、生きている意味、生かされる意味を考え続けることが、もしかすると「求められる答え」なのかもしれない。
私は決して、あのにおいを忘れない。


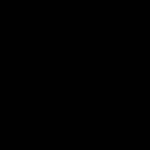

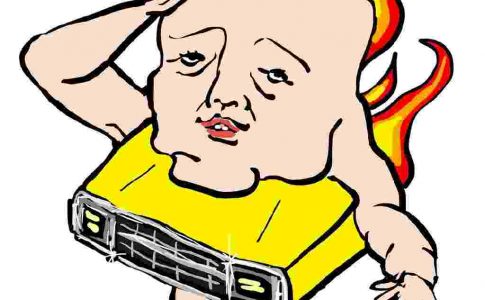

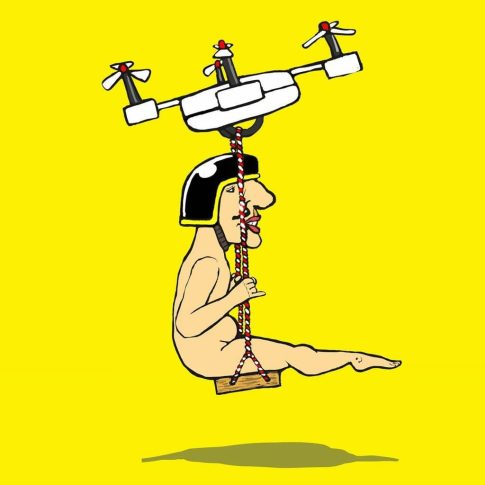

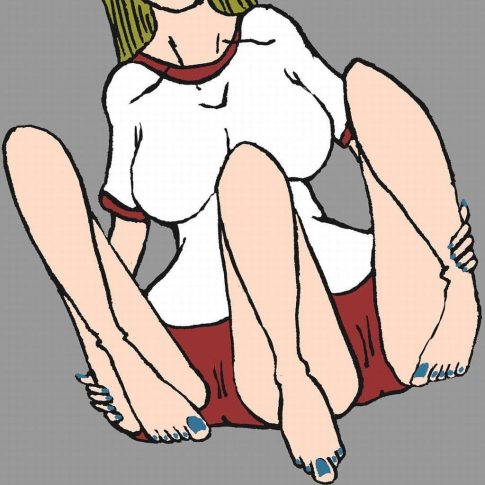












コメントを残す