じつは何を隠そう、わたしは読み書きが得意ではない。四年以上も毎日、二千字の文章を書き続けてきたにもかかわらず、"読み書きが得意ではない"はさすがに嘘っぽいが、事実だからしょうがない。
正確には、"得意ではない"というよりも"好きではない"というべきだが、とにかく書類に目を通したり、論文を書いたりすることが苦痛なのだ。それでも仕事柄、書類作成を余儀なくされたり法律を読み解いたりしなければならず、嫌々ながらもそんな毎日を送っているわけだが。
ところが最近、文章を書くことで「嬉しい」と思えることがあった。それは美容師である友人のヘアサロンの、紹介文を手直ししたときのことだった。
友人の職業は美容師なので、髪の毛を切ったり巻いたり染めたりすることに長けている。そんな彼との付き合いも15年を超え、もはや気心の知れた腐れ縁となった。
さらに今日までの間、彼にはいくつもの災難が降りかかった。そしてその度、偶然なりともわたしが手助けをすることとなり、間接的に苦楽を共にしてきた仲なのだ。
そもそも、お調子者である上に根っからの"いい奴"である彼は、いかんせん騙されやすい。高校までは甲子園を目指す球児だったが、緑豊かな田舎で育ったせいか他人を疑わない性格が仇となり、ヒトを欺くのが得意な連中のターゲットになりやすかった。
「友達に借りてるカネを、返さないといけないから・・」
店は繁盛しているにもかかわらず、資金繰りに違和感を覚えたわたしは、その内訳についてしつこく追及したことがあった。すると彼は、友人への借金返済が大部分を占めている・・ということを白状したのである。
しかも金額が「借りた金を返す」レベルではなかったため、いったいどういうことなのかを問い詰めると、「利子があるから」とのこと。——カネを貸した友達・・ていうか、友達がトイチの利子を要求するか?
その時点で"貸主"が友達ではないことくらい、およそ感じるであろう悲しい現実だが、彼はそれでも貸主を友達だと信じていたのだ。このくらい、バカで純粋なオトコなのである。
そんな彼も借金を整理し法人を設立し、都内の一等地でヘアサロンを営むまでに成長した。そして今回、美容学校の生徒向けにヘアサロンのパンフレットを作成することとなった模様。
会話の流れでパンフレットのゲラを見せてもらったところ、レイアウトや写真はオシャレでいい感じだが、いかんせん中身(文章)がいただけなかった。やたら滅多に小難しい言葉や流行りのワードを並べて、「こういう言葉を使っておけば、イマドキっぽくて刺さるだろう!」という、稚拙で浅はかな欲望が丸出しなのだ。
・・なんてひどいことは思っていないが、彼の人間性も伝えたいことも一ミリも伝わらない内容であることが、個人的に非常に残念だった。そこでわたしは、髪の毛を切ってもらう間を利用して紹介文を書き直すことにした。
はじめは、元の文章をちょいと手直しする程度のつもりだったが、"ナウでキャッチーでSDGsなワードチョイス満載、みんなでハッピーになれる、そんなイケてるオレのヘアサロン!!"という、鳥肌モノの文章を手直しすることは不可能。結局のところ、すべてわたしが書き直す羽目となったのだ。
とはいえ、大した作業ではなかった。なんせ、われわれは15年の付き合いがあるわけで、彼がどんな人間でどんなことを伝えたいのかくらい、説明されなくても十分理解しているからだ。
ちなみに、文章の素人は「自分の想いだけをつらつらと綴る」傾向にある。言わば単なる独り言であり、他人に読んでもらう目的はそこには存在しない。そのため、熱い想いを他人に伝えたいならば、他人の目線というか他人の温度まで下げる必要がある。
自分の言いたいことを好き放題にばら撒くだけでは、同じ温度の仲間にしか響かないわけで、それこそ「内輪ネタ」で終わってしまう。他人に響かせるためには、やはり他人に向けてぶっ放さなければならないわけだ。
そんなこんなで、わたしから見た"彼"という人間そして目指す方向性を、彼好みにイマドキっぽくまとめたあげたところ、予想以上に喜んでくれたのには驚いた。
(わたしは、真面目な文章はてんでダメだが、個人的な想いや訴えをいい感じにまとめるのは、案外得意なのかもしれないな・・)
大喜びの彼から何度も何度も礼を言われるので、「本業なんでね」と生意気な返事をしたところ、
「いや、本業の域を超えてる感がある!」
という、これまで聞いたことのない嬉しい褒め言葉をもらったのだ。だがむしろ、この言葉がわたしに刺さった。
こちらもカネをもらって書いたわけではなく、友達としてちょっと協力してあげようか・・程度のノリだったため、片手間といえばそれまでの意気込みだった。現に、髪の毛を切ってもらいながら作文したわけで、片手間かつ時間つぶし以外の何ものでもないわけで。
それでも彼にとっては、伝えたいことの百パーセント以上が詰まった文章に感じたのだろう。そりゃそうだ、何年キミとバカやってきたと思っているんだ!
*
というわけで、わたしの得意なことで友人が喜んでくれたことが、なぜかとても嬉しかった・・という、よもやま話である。









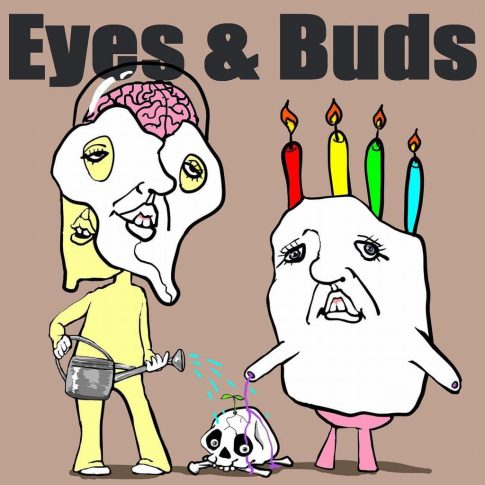











コメントを残す