都内に住んでいると、いわゆる「観光地」へわざわざ出向くことは少ない。
たとえば、わたしは東京の象徴である東京タワーの近所に住んでいるが、東京タワーに上ったり東京タワーの麓ではしゃいだりすることはない。夜になると鮮やかな電飾が目に入ることはあるが、だからといって現地まで行こう!とまでは思わないわけで。
まぁ、「見慣れ過ぎたせいで、感動が薄れているんだ!」と言われればそれまでだが、ほかにも築地やスカイツリーへもわざわざ行こうとは思わないことから、わたし自身が「観光するくらいなら、カフェで仕事するほうが楽しいし充実できる」と考えているのだろう。
そんなわたしは今日、東京を代表する、いや、日本を代表する観光地を訪れた。それは古き良き日本が残る街、台東区浅草にある浅草寺だ。
仕事ついでの通り道になることもなければ、偶然通りかかることもない土地・浅草。そんな歴史ある由緒正しき観音霊場に降り立ったわたしは、外国人のあまりの多さに驚かされた。
それなりに海外からの観光客がいるだろう・・と思ってはいたが、まさかここまで外国人まみれになるとは、予想だにしなかった。そもそも、都営浅草線の浅草駅に到着すると、右も左も外国人だらけ。むしろ、都内在住の日本人はわたしだけではなかろうか?と疑うほどの、異国情緒あふれる光景が広がっていた。
「人力車いかがですかぁ」
そして駅から雷門までの道中は、車夫の兄ちゃん姉ちゃんらの威勢のいい呼び声がこだまする。それにしても、細マッチョなイケメン男子が祭りで着るような腹掛けのコスチュームに身を包む姿は、まさに眼福にあずかるといっていいだろう。
あっという間に、かの有名な雷門(風雷神門)へたどり着くも、そこはもはや外国人エリアとなっていた。飛び交う言葉に耳を澄ますと、英語に中国語、韓国語、タイ語、タガログ語、さらには判別不能な言語で溢れている。聞こえてくる日本語といえば、交通整理をしている警察官の怒鳴り声くらいで。
「チョットスミマセン」
欧米人と思われる若い男子が、わたしの横をすり抜ける瞬間にこう呟いた。その感じは「日本語が話せる」というよりも「日本に来たら最低限、口にするべき日本語を知っている」といった感じ。
とはいえこれだけの人混みならば、英語で断りを入れてもまったく違和感はない。にもかかわらず「郷に入っては郷に従え」ということで、頑張って日本語を使ってくれたわけだ。
——むしろ日本人よりもマナーがなってるというか、なんだかこちらが恥ずかしくなる。
なぜこんなにもヒトで賑わっているかというと、運よく今日は「金龍の舞」が行われる日だったのだ。・・なんてわざとらしい言い方をしたが、実はわたしも「金龍の舞」目当てに浅草寺へやってきたのだ。
アメリカから一時帰国した友人の仲良しが、この金龍の舞の奉演に参加しており、その雄姿(?)を拝みにきたのである。
金龍の舞とは、昭和33年(1958)に本堂再建を記念して創られた「寺舞」のこと。ちなみに金龍という名は、浅草寺の山号「金龍山」に由来するのだそう。そして、観音さまを象徴する「蓮華珠」を先頭に、これを守護する「金龍」が仲見世や境内を練り歩くのだが、まるで生きた龍のようなダイナミックかつ妖艶な動きに、訪れた参拝者は拍手喝采の大喜び。
さらに、金龍の舞は毎年3月18日と10月18日に行われるが、観音さまのご縁日である「18日」にちなんで龍の全長は18メートル、重さは約88キロ、そして8名の金龍使いによって勇壮華麗な舞が繰り広げられるのだ。
そんな貴重なイベントに遭遇できたことは、この上ないラッキーである。ましてや、自分一人では決して訪れることのない場所なので、たまたま誘ってくれた友人に感謝するのであった。
それにしても、浅草寺というのはすべての規模がデカい。敷地の広さも相当だが、雷門に吊るしてある大提灯など、高さおよそ4メートル、重さ700キロもあるわけで、誰があれを張り替えるのだろうか。ちなみに、2020年に6回目の掛け換えを行ったばかりとのことだ。
また、仲見世を通り過ぎたところにある宝蔵門(仁王門)には、これまたバカデカい大わらじが貼りつけてある。高さ4.5メートル、重さ500キロ、藁の量は2,500キロ、山形県村山市の有志より奉納されたのものだ。
どうやらこのわらじは仁王さまの力を表すらしく、「このような大きなわらじを履く者が、この寺を守っているのか!」と、驚いた魔物らが去って行くのだそう。・・ていうか、いったい何人がかりでこの大わらじは完成するのだろうか。もしもわらじを編む技術継承が途切れたら、仁王さまにキレられるだろうな。
*
というわけで、外国人観光客と同じくらいのテンションで浅草寺を満喫したわたしは、港区ではお目にかかれないほどの広大な青空を眺めながら、「台東区も捨てたもんじゃないな」などと思うのであった。





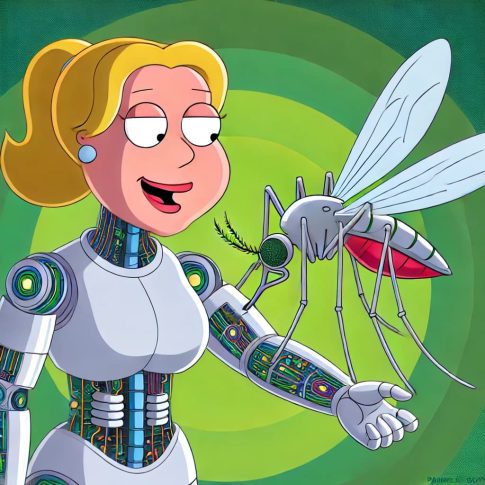


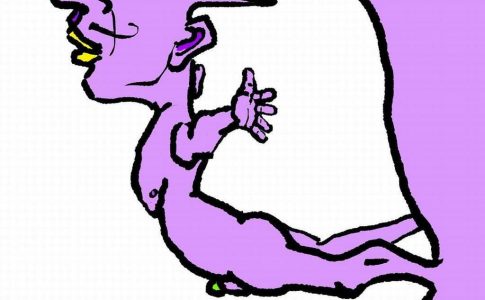












コメントを残す