「あぁー、それは食べちゃダメー!って、思わず声に出しちゃいましたよ」
笑いながら後輩がそう言った。なんのことかというと、過去にわたしが食べた「霜がこびりついたキュウリ」のコラムを読んだときに、思わず制止させようとしてしまった、という話だった。
「そんなの、もうカビだって分かるじゃないですか。それなのになぜ食べちゃうんだーて、独り言だけど呟きましたよ」
その言葉を聞いたとき、わたしは己の語彙力のなさを恥じた。
後輩は、わたしのことをバカだと思ったのだろう。誰がどう見たってカビに決まっている白いフワフワを、もしかすると霜柱なんじゃないか?…などと勘違いするようなおめでたい輩は滅多にいない。
いくらキュウリを製氷機の真下で保存していたからといって、表面をびっしりと覆うほどの霜柱が発生するとは、まともな人間ならばさすがに考えないはず。そんなことはわたしにも理解できるし、その程度の常識?ならば当然のようにわきまえている。
ではなぜ、それほどまでにまともな感覚を持っていながらも、白カビと霜柱とを見間違えたのかというと、誰がどう見ても霜柱にしか見えない立派なカビが生えていたからに他ならない。
そして、その状況描写が上手くできなかったがために、後輩から笑われる羽目になったのだ。あぁ、わたしに文才があったなら——。
*
正直に話すと、あのときわたしは薄々気が付いていた。この白い繊維質のような綿毛は、もしかするとカビなのではなかろうかと。だがどうしても信じられなかったのだ。あまりにも美しくキラキラと輝く白い存在が、まさか、陰湿で有害な菌であるなど、誰が想像できようか。
透明なビニール袋に横たわるキュウリは、結露により汗ばんでいた。さらに、製氷機の真下で冷やされていたことからも、この見事な白い毛羽立ちは氷あるいは霜であると考えるほうが妥当。
それと同時に、わたしは幼少期を思い出していた。
長野の田舎で育ったわたしは、冬になると黒茶色の土が盛り上がり、踏むとシャクシャクと心地よい音を立てる霜柱が好きだった。あえて霜柱のある場所を見つけては、わざわざ踏んづけてから先へ進むというように、小学校へ向かう途中の畑に目を光らせながら登校したものである。
(そうだ、これはあの時の霜柱と同じ形状をしているじゃないか——)
そう感じてしまったわたしは、その白い繊維質の物体が霜柱あるいは細かな氷の結晶にしか見えなかったのだ。
そして何よりも、そう信じたかったのである。
もしもこれがカビだと断定してしまったならば、もうこのキュウリを食べることはできない。近所の軒下マルシェで購入した美味しいキュウリを、みすみす捨てるような真似はわたしにはできない。
——であれば、これはカビではないと決め込んだ方が幸せなのではないか?
これは、キュウリを育ててくれた農家への敬意であり、軒下マルシェへの感謝であり、なによりもフードロス削減への強い想いからの発想である。なにもわたしがバカで世間知らずだからではない。すべては尊い精神的思想、言い換えれば「食べ物への愛」からくるものなのだ。
*
そして今、わたしはスイカを食べている。軒下マルシェで購入した、美味しいスイカである。
しかしスイカというのは、なんとも厄介な黒い種が埋め込まれており、表面上は取り除けたとしても、スプーンですくえば次から次へと現れてくる。シャインマスカットやナガノパープルのように、皮ごと食べられて種もない上に甘くて価格も手頃…というような、超優秀な品種改良がおこなわれればいいのだが、スイカに限ってはそうもいかない模様。
まぁ、人間の欲望のために手間暇かけて高コストな種なしスイカを栽培したところで、スイカ農家も割に合わない。ならば、いつまでも種をプップと吹き出す方式でかぶりつくのが、スイカの正しい食べ方といえるのだろう。
そんなことを考えながら、口の中で黒い種を選別してはゴミ箱へ吹き飛ばす作業を繰り返していたわたしだが、なんと、大失態を犯してしまったのだ。
誤って、思いっきり種を噛んでしまったのだ。
これは実際に、黒い種を噛みつぶしたことのある人にしか分からないだろうが、スイカの種はとにかく不味い。「よりによって、こんなにも嫌味な不味さである必要などないだろう!」と、逆ギレしたくなるほどの不味さなのだ。
(この種の不味さ、すなわち、非可食部ならではの独特の味と、スイカの甘みを損なわれた怒り、さらには口の中に残る不愉快な苦味を、どう表現したら伝わるのだろうか・・・)
夜中まで考えたが、その答えは見つからなかった。やはりわたしには、語彙力が不足しているのだ。
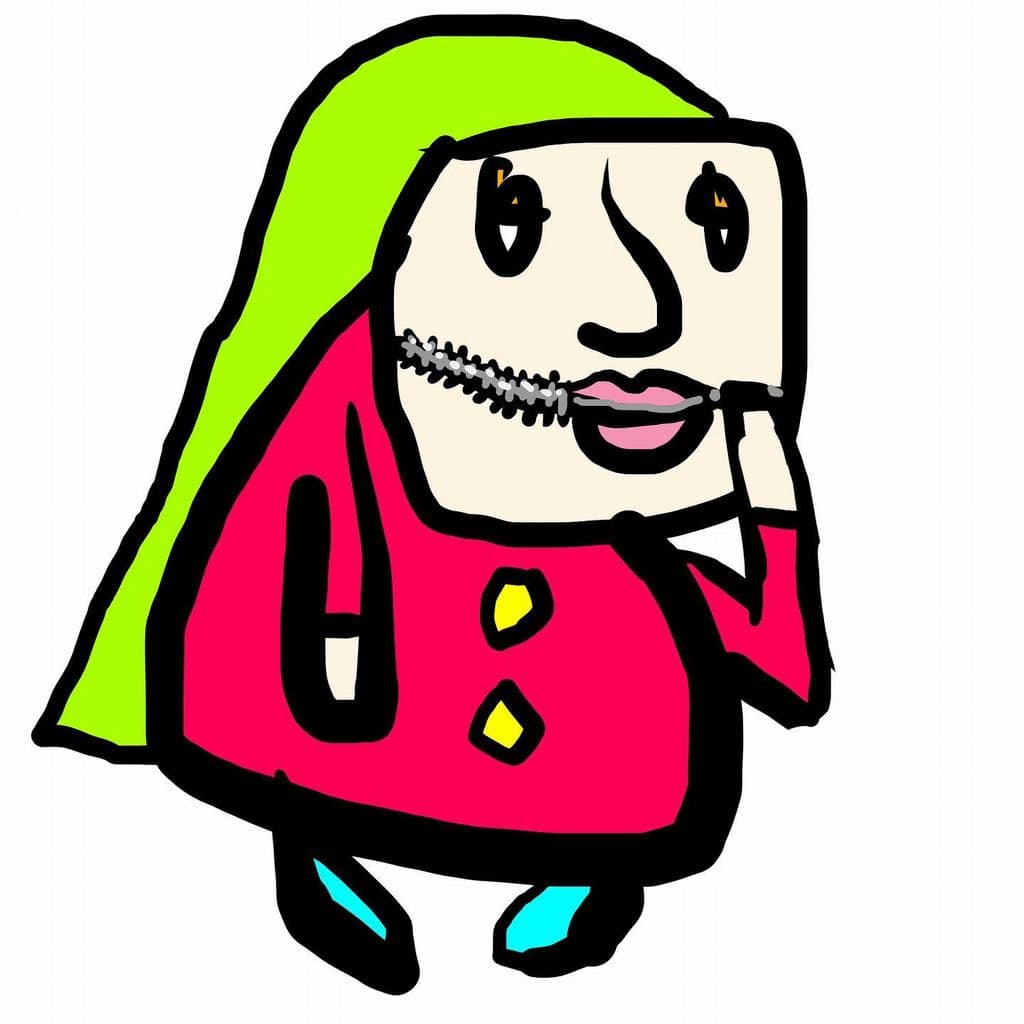


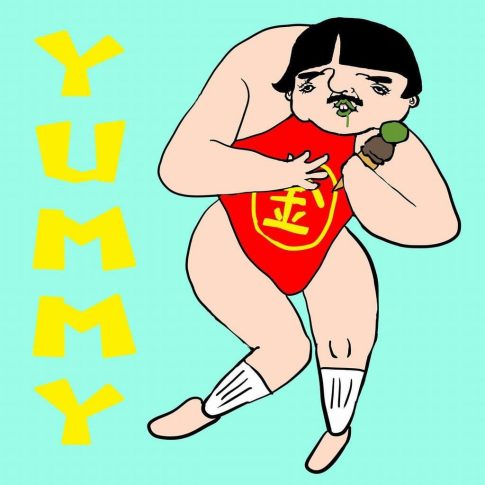




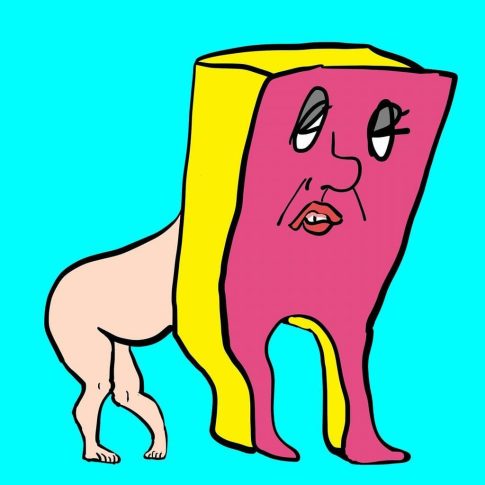
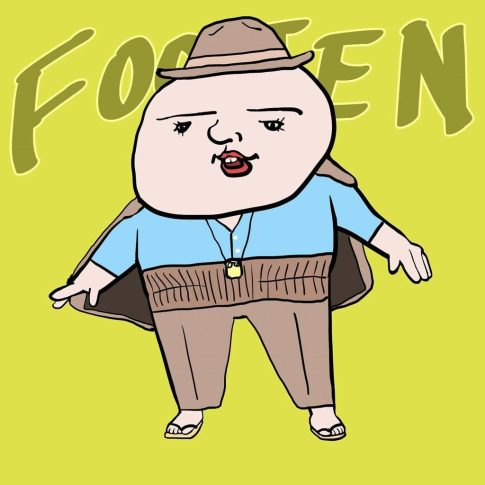











コメントを残す