――ガサッ
(あー、落ちたか)
活きのわるい大マグロのようにソファへ横たわりながら、グレートプリテンダー(頭脳派詐欺師集団のアニメ)を見ていたわたしは、スマホに届いたメッセージを確認した後にテーブルへと戻した。
目線はアレクサだったので、およそテーブルの隅にスマホを置いたつもりだったが、予想以上に端っこすぎたため床へと落ちたのだ。と、そこで口を開けて待ち構えていたゴミ箱に、わたしのスマホは消えていった。
たまたまわたしの意識があるときにスマホが落ちたからいいが、もしもこれが寝ている間だとしたら、まぁいずれは発見するだろうが目が覚めた瞬間はビビるだろう。
今のご時世、スマホがなければ何もできない。朝はスマホのアラームで目を覚まし、その日の天気とSNSを一通りチェックする。出かける前には電車の時刻を確認し、ランチやカフェもスマホで調べる。そして会計は電子決済で終了…といった具合に、暇があればSNSや動画で時間をつぶし、分からないことがあればネットで検索し、もはやわれわれの生活はスマホに左右されているのだ。
あいにくわたしはスマホの他にもガラケーを持っているため、スマホをゴミ箱に落としたとしてもガラケーから電話をかければ、こいつの居場所はすぐにわかる。あとは、デバイスを探すアプリを使って見つけることもできるだろう。
しかし11年前、スマホを落とした場所は分かっているにもかかわらず、救出できなかった苦い思い出がある。
*
場所はロンドン。オリンピック開催に合わせて交通機関も整備されており、新品のシートやペイントの匂いで車両は包まれていた。
あれはモノレールだったか地下鉄だったか、わたしは無人電車の先頭車両に乗り込み、上機嫌で流れる景色に見入っていた。
(お、見えてきた!)
目的地の駅が近づく。駅の改札で友人らと待ち合わせをしているので、電車を降りたらすぐに合流できるだろう。
そしてわたしは、電車を降りると改札へと向かった。
(あ、そうだ。念のため到着のメッセージを送っておこう)
尻ポケットに入れておいたスマホへと手を伸ばしたわたしは、思わずギョッとした。わたしの尻は、柔らかくて丸みを帯びていたのだ。いや、それは当たり前だし、むしろそれ以外の尻であれば恐ろしい。
そうじゃなくて、尻にあるはずの薄っぺらい角ばった感触がないのだ。そんなはずはない、車内で所在地を確認したりSNSを見たりしたわけで、数分前までは確実にわたしの手元にあったのだから。なぜだ、なぜ――。
(ざ、座席の隙間だ・・・)
シートに腰かけると尻ポケットの口は真後ろを向く。そこから少しだけ顔をのぞかせたスマホの頭が、運悪く背もたれとシート隙間に刺さってしまったとする。それに気づかず座り続ければ、わたしの尻の圧力(ケツ圧)でスマホはグイグイとシートの隙間へ押し込まれる。その結果、気付けばスマホは座席の裏側へ落下し、見た目ではこの世から消え去ったことになる。
わたしは咄嗟に振り返ると、今まさに発車した電車に向かって走り出した。大きく手を振りながら追いかけたのだが、そもそも無人電車なわけで誰も気づいてはくれない。
そこで、ホームに立っていた駅員にしがみつき「あの電車を止めてくれ!」と叫んだが無駄だった。動いている電車を止めることが無理である以前に、わたしがしがみついた男性は駅員ではなく、オリンピックのボランティアだったからだ。
――こうして無慈悲にも、電車はどんどん遠ざかっていった。
その後、あのスマホを巡って色々と事件は続いたが、今でもロンドンを走る電車の座席裏で静かに眠っているのだろう。
何らかのきっかけで、シートを上げてわたしのスマホが目を覚ますのは、あと何十年先の話だろうか。その頃のスマホはガラケーのような存在となり、もはや電源も入らない化石となっているのかもしれない。
そんなちっぽけな存在に踊らされる人間とは、なんとも哀れな生き物である。
*
まぁとにかく、意図的にスマホをゴミ箱に捨てる人間はいないだろうが、テーブルに置いたつもりのスマホが消えたときには、是非ともゴミ箱を漁ってみるといいだろう。
いや、それよりもよそ見しながらスマホを放り投げるのを、やめるべきか。



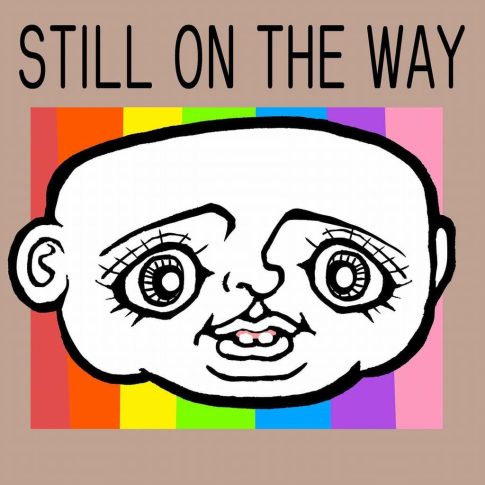


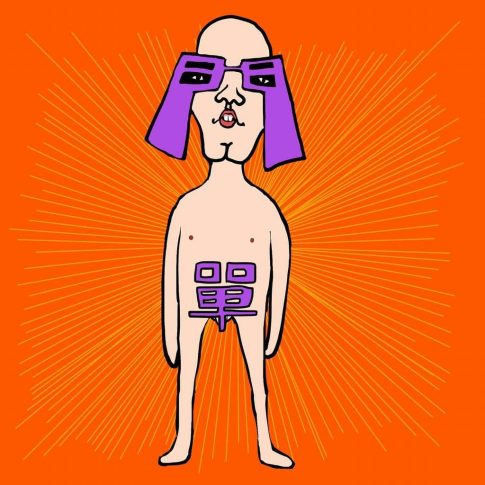














コメントを残す