目の前には若くて美しい女子がいる。愛らしい笑顔を振りまきながら、楽しそうに近況報告をしてくれる。
ーーあぁ、若いって素晴らしい。
などと考える余裕すらないほど、わたしはとある現実と戦っていた。それは寒さだ。
家を出るときに確認した天気予報では、本日は快晴で最高気温17度。この17度という気温がややこしく、決して暑くはないが寒くもない。つまり日差しさえ確保できれば間違いなく温かい。だが風でも吹こうものならジャケットが必要な寒さとなる。
もちろん上着をはおって外へ出たが、今は店内にいるので上着は脱いでいる。しかしこのご時世、コロナ対策で入り口のドアは解放されており抜群の換気状態。店内は店外ばりに風通しが良い。
そして太陽が当たらない分、寒い。
入店当初はまだよかった。駅からここまで歩いてきたわけで、むしろちょうどいいくらいに体は温まっていた。そして上着を脱ぎ、雑談に花を咲かせているうちに、わたしの体はみるみる冷えていった。
若い女子は用意周到、厚手のニットを着ている。今思うと彼女はジャケットなど着ておらず、外も中も同じ身なりだった。店内では腕まくりをしていたことすら思い出される(白くて細くてしなやかな腕が脳裏に焼き付いている)。
それに比べてわたしは、ラグラン袖の七分丈ロンティーを着ている。これ一枚だ。
ラグラン袖という名前の由来は19世紀にさかのぼる。イギリス・オランダをはじめとする連合軍とナポレオン一世率いるフランス軍とが、ベルギーのワーテルロー近郊で繰り広げた戦争(ワーテルローの戦い)があり、そこで右腕を失ったイギリスの初代ラグラン男爵、フィッツロイ・サマセットが「(腕がなくても)容易に着脱できるコート」をオーダーし、出来上がったデザインが「ラグラン袖」という形状だった。
ーーいや。
今この時点ではラグラン袖かどうかよりも、手首が明らかに露出するほどの短さのロンティー一枚であることのほうが問題だ。前腕には鳥肌、爪の色は不気味な紫色。
「だったら上着を着ればいいじゃないか」
そんなことは分かっている。分かっているが、タイミングが難しいのだ。じつは食事がスタートした頃、その当時からやや寒かったが食べることで体が温まり、今ほどの鳥肌も血色の悪さも見られなかった。このまま食べ続けて乗り切ろうと思った矢先、ジェラートが届いてしまったのだ。もちろん、注文したのはわたし。
「ジェラートは食後にする?」
店員に聞かれるも、
「ううん、今すぐ食べたい」
と答えたのもこのわたしだ。目の前の女子は、最後じゃなくて先に食べちゃうんですかぁ、と笑っていたが、わたしにはポシリーがある。それは「好きなものから先に食べる」だ。
「いま大地震が来たら、ジェラート食べずに逃げられる?できないよね。だからアタシは先にジェラートを食べるの。そしたら安心して逃げられるでしょ?」
得意げに説明する。女子は、えーじゃあジェラート食べなかったら逃げないんですかぁ?とクスクスしながら質問するが、なんたる笑止。当たり前だ。そういう愚行を避けるためにも、わたしはいつだって先にデザートを食べるのだ。
そして口へ運ぶは「ビーガンいちじく」と「稲取キウイ」のジェラート。非常に美味かったし先に食べてよかったと思っている。
ーー思っている。
だからこそ、寒い素振りなど見せられないのだ。もしここで上着に手を伸ばそうものなら、目の前の女子はこう言うだろう。
「ジェラート食べたら寒くなりますよね」
そんなことも分からなかったのかと、陶器のようにつるんとした肌を惜しげもなくクシャクシャにさせて笑うだろう。それだけは断じてさせまい。つまりわたしは、寒さに耐えなければならないのだ。
ようやく食事が後半に差しかかった。だが、もしここで上着に手を伸ばそうものなら、目の前の女子はこう思うだろう。
「あ、早く帰りたいですよね。急ぎます」
そんな不要な心配をさせたくはない。たとえわたしが、ちょっと寒いからはおるだけだよ、と補ったとしても、女子は内心「この人は早く帰りたがってるんだ」と思い込んでしまうだろう。それだけは避けねばならぬ。
そして2時間が経過した。カッコつけて腕組みをしたり、太ももと胸を近づけてみたり、寒さをしのげそうな行動はすべて試した。もうその頃にはじっとしていられないほどの寒さに襲われ、わざと動いていなければ震えを悟られるほど、わたしは震えていた。
「そろそろ行きましょうか」
ーーこの一言よ。
この一言をおよそ2時間待っていた。決して早く帰りたかったわけではない、ただ、上着をはおるタイミングの問題から、この言葉を待つしかなかったのだ。そしてこの言葉を聞いた瞬間、目の前の女子が今まで以上に女神に見えたことは言うまでもない。
Illustrated by 希鳳
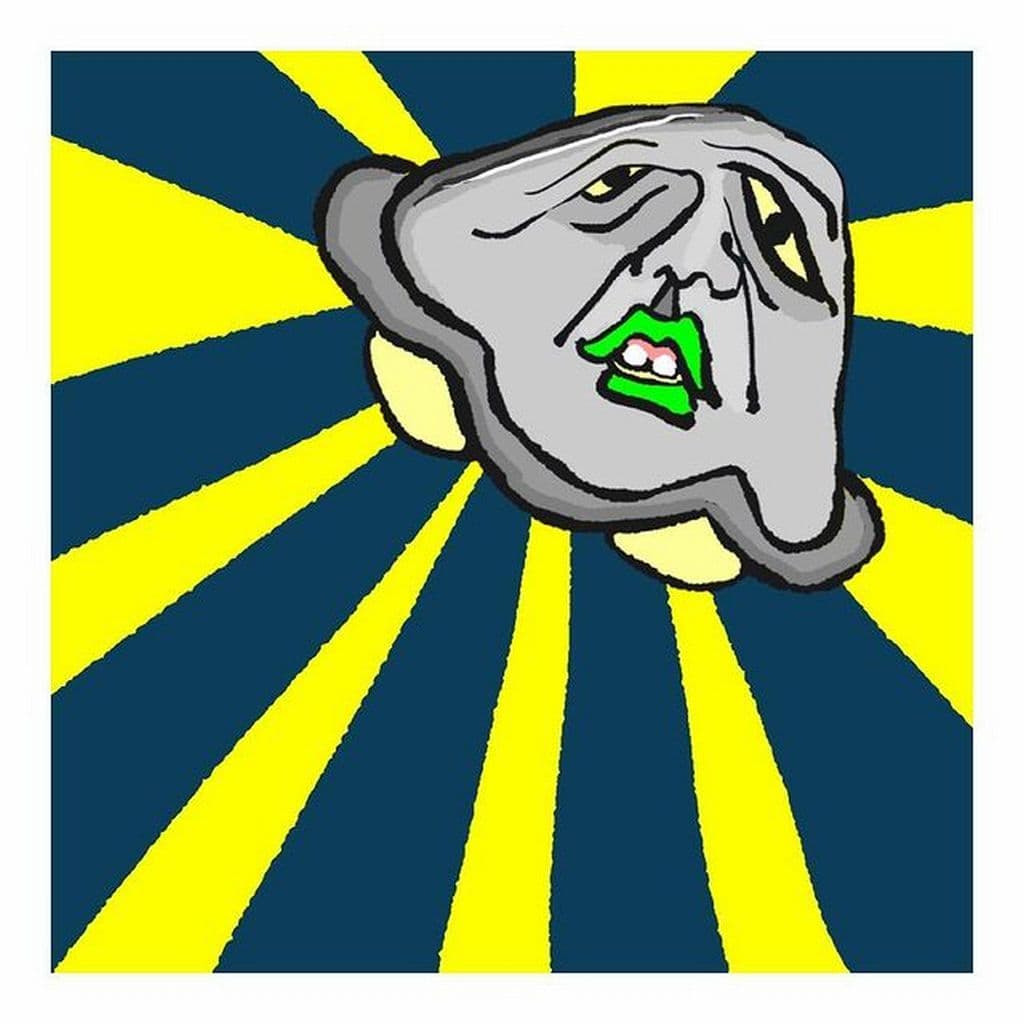



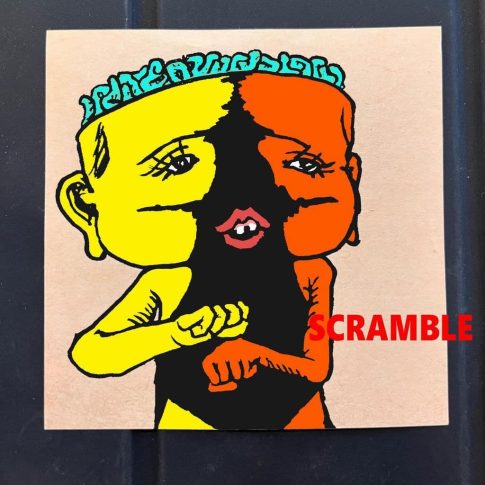

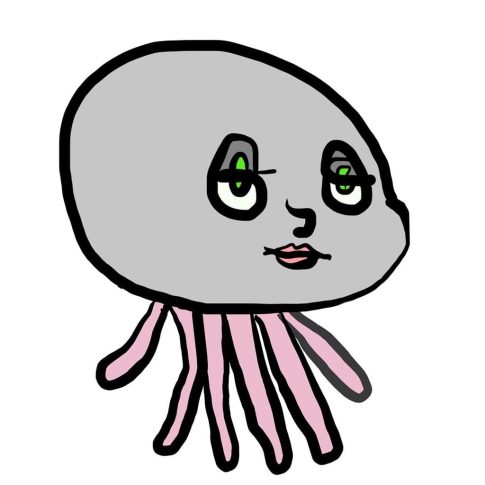


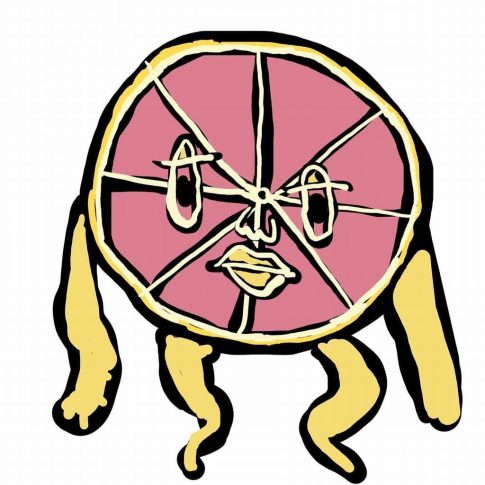











コメントを残す