他人との距離感というのが、とくに難しいご時世である。フィジカル環境だけでなく、SNSのようなデジタル空間での関係性というのも、大いに難しい世の中となってしまった。
挙句の果てには自分を隠し偽ってまで、その世界で生きようとする輩までいるわけで、なにが本当なのかどれが本物なのか、もはや誰にも分からなくなってきた。
そんな今だからこそ、ヒトの手のぬくもりがやけに温かく感じたのかもしれない。
*
気温18度の都内は、半袖でも過ごせるほどの最高の季節を迎えた。穏やかに照らす太陽は夏ほどの激しさもなく、かといって冬の透明感も消え去り、まさにちょうどいい柔らかさである。
(ポカポカしてていい気分だ!)
そんな呑気な独り言をつぶやきながら、わたしはカフェへと向かった。
――4時間後。さすがに夜の7時を過ぎると、空気もひんやりしている。今の気温は10度前後だろうか。風が吹くと思わず身震いしてしまう。
昼間は暖かいといえども、まだ4月であることを忘れてはならない。まだまだ朝晩は寒いのである。
(なんか、あったかい物でも食べたいな・・)
外出時に寒さを紛らわすには、室内へ逃げ込むのが一番。しかし今まで、カフェという暖かい室内で何時間も過ごしていたわけで、今さら別のカフェに入るくらいならば、さっさと駅に向かうのが得策だろう。
だが、ここから最寄り駅までは5分ほど歩くことになる。別に、頑張って歩けないことはない。寒いといったって10度はあるのだから。しかし心の弱いわたしにとって、この寒さを受け入れながら駅へ向かうことは、ちょっと厳しいのである。
しぶしぶ横断歩道へと向かう途中、遠くに「温かい食べ物」の象徴を発見した。そう、肉まんだ。しかもあれは巨大肉まんである。
暑いときに掻っ込むかき氷というのも生きた心地がするが、それよりも、寒いときにほおばる大きな肉まんほど「生きていること」を実感できる食べ物はない。美味しさ以上に、生(せい)への感謝が湧き上がってくる、とでもいおうか。
とりあえずわたしは、その大きな肉まんめがけて横断歩道を渡り始めた。
「こんにちはー」
狭い店内には客の姿は見当たらない。奥の厨房に店員の気配がするが、とくに作業をしている様子もなく、見るからに暇そうである。
するとひょっこり、レジの下から別の店員が現れた。中国人のおばちゃんだった。
「持ち帰りで、肉まんを一つください!」
活舌よく大きな声で注文を伝えた。するとおばちゃんは、なにかごにょごにょとつぶやいた。骨伝導のヘッドフォンを着けていたわたしは、慌ててこめかみから離すとおばちゃんに聞き返した。
「アッタカイノ?ツメタイノ?」
どうやら、ショーケースで温められている現物か、冷凍保存されている肉まんかを尋ねている模様。すぐさまかぶりつきたいわたしは即答で「あったかいの」と答えた。
「t(%$#&」
ヘッドフォンは外しているが、なんと言ったのか聞き取れなかった。再び「え?」と聞き返すわたしに、
「ツメタクナッタラ、レンジで15ビョウネ」
と、少し怒った表情でおばちゃんは言い放った。
肉まんが冷たくなることなどありえない。なぜなら、代金を払ってこの店を出たら、その瞬間にかぶりつくからだ。ほっかほかで分厚い肉まんの皮を想像するたけで、口の中はヨダレで洪水状態である。
それよりなにより、早く肉まんを渡してくれ。テラス席しかないこの店は、室内といっても外と同じ気温である。厨房はあったかいかもしれないが、客はブルブル震えながら料理を待つことになる。
あぁ寒い、一刻もはやく肉まんを!
「サムイノ?」
目の前を横切ろうとしたおばちゃんが、なんと、わたしの両腕をさすってくれたのだ。寒がる子どもを温めるかのように、何度か上下に腕を動かすと、そのまま肉まんのショーケースへと通り過ぎて行った。
見ず知らずの他人に、なれなれしく腕をさすられるとは。恋人ですらこんなことはしないだろう。いや、日本人はこういうことをしないのかもしれない――。
だが不思議なことに、わたしは寒さを忘れていた。正確には「寒い」という感情を喪失していた。
エアコンやハロゲンヒーターなど、小汚い暖房器具が店内の片隅に置いてある。それでも、そんなものよりも、おばちゃんの素手のほうが温かかったのである。
見ず知らずの人間になれなれしく触られる行為は、貴重であり稀有な経験といえる。そしてそんなこと、いまの日本でやろうものなら、誤解を含めとんでもない事態に発展しかねない。
それでも、中国人のおばちゃんの手は、わたしにとっては暖房よりも効果があった。あれこそが、中国ン千年の秘技なのだろうか――。
そんなことを思いながら、肉まんをほおばり駅へと歩き出したのである。



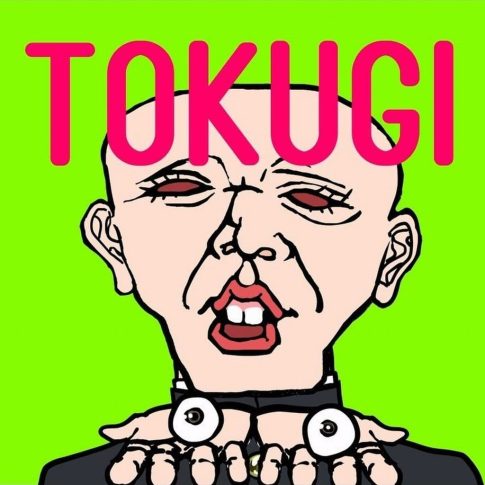
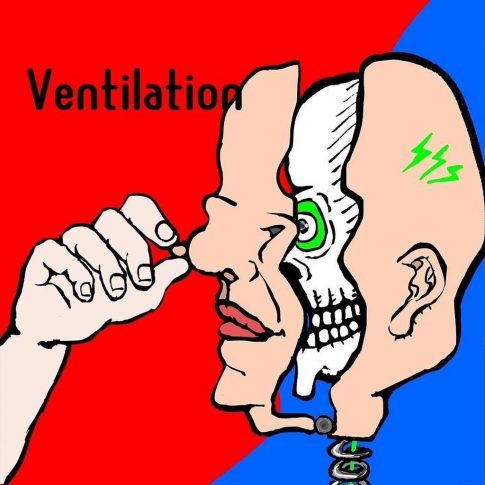


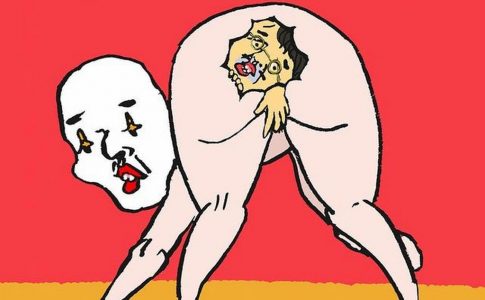


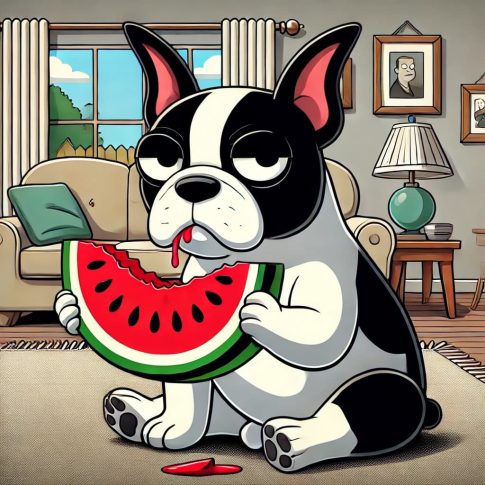










コメントを残す