私は今、漆黒の大海原と対峙している。そしてこの光景、何十年か前にも見た記憶がある。
あれはたしか小学生か、中学生の頃だったか。なぜか我が家に「赤福」が置かれていた。あんこ嫌いの私にとって、あの赤福という和菓子は信じられない食べ物という位置づけ。
そんな赤福のフタを取ると、一面ぎっしり敷き詰められたあんこの海が広がっており、大海原をほじくると底の方から窒息しかけたモチが現れた。子供心にも救出の必要性を感じた私は、すぐさま赤福に備え付けられているヘラを使って、かわいそうなモチたちの救助に向かった。
次々と助け出されるモチを水道水で丁寧に洗うと、ポイッと口へと放り込む。
(――うん、美味い!)
ほんのり砂糖の甘味が残るモチは、モチモチの歯ごたえとツヤツヤの輝きを放ちながら、私の胃袋へと消えていった。そして最後の一粒を救助すると、残された穴だらけの海面をヘラで撫でて整える。
赤福のあんこはやわらかく伸びがあるため、でこぼこの粘土を滑らかにするよりも簡単に、ほとんど触れるだけの力で荒れた水面を落ち着かせることができた。
仕上げに、最初あった通りの荒波を再現すると、私はそっとフタを閉じたのである。
*
あの時に見たあんこの海が、いま再び目の前に現れたのだ。しかもあの時よりもはるかに大きな大海原が広がっている。おまけに今回は海ではない、氷河だ。あんこでできた漆黒の大氷河が、木箱に隙間を与えることなく敷き詰められている。
そう、これは信州下諏訪にある新鶴本店の塩羊羹。高級感溢れる杉折りの木箱と、鶴の掛け紙と紅白の水引で結ばれた羊羹は、なんとも立派な贈答品。
木蓋をそっと外し、四方から折りたたまれた厚手の紙を一枚ずつ開いていくと、そこには目を見張るばかりの塩羊羹がでーんと横たわっていた。
この逃げ場のない、進退窮まった状況に私はふと天を仰ぐ。そして一筋の光を見た。
(そうだ、私はもはやあんこが食べられるのだ)
先日、とある高級羊羹を口にしたことで、あんこもあずきも克服したかのようにみえた私。だがあれは、青柳正家の羊羹に限った話のようで、その他のあんこはどんなに評判がよくても、残念ながらご縁のない日々が続いた。
そんなある日、友人から突如このような甘い誘いを受けた。
「普通の羊羹とは全然ちがって、寒天の量が多くて小豆のくせが少ない塩羊羹なんだけど、トライしてみる?」
その塩羊羹とやらもかなり有名で、由緒正しい和菓子店のもの。昭和39年に両陛下への献上品として選ばれた過去もあり、正真正銘の本物といえる。
歴史あるものはそれなりの裏付けがある。そして長く愛されるにはそれなりの価値があるわけで、これを試さずに上杉謙信も天竜道人も語れまい。
青柳正家の羊羹を丸ごと2本食べ尽くした私は、そのキャリアを引っ提げて、信州・新鶴の塩羊羹からの挑戦を受けることにした。
そして今日、敵に塩を送る、いや、友に塩羊羹を贈る形で、立派な逸品が届いたのである。
(それにしても、これは赤福どころの話ではないな)
滑らかな表面は照明の光を反射してキラキラと輝く。指で突くと適度な硬さと羊羹独特の粘りを感じる。しかし今まで体験したことのある羊羹との違いは、その大きさだ。
通常、羊羹といえば縦長の直方体で拍子木のようなイメージ。だがこの塩羊羹は、A4サイズのノートがすっぽり収まるほどの大きさがある。
――つまり、20個入りの赤福のフタを開けたような景色が広がっているのだ。
(あの頃はまだ若かった、だが今は違う)
かつて赤福と対峙した時の記憶がよみがえる。
ただなんとなく、食べ物の好き嫌いの一つとして、あんこが嫌いだったあの頃。しかし今は違う。紆余曲折を経て、人生の荒波に揉まれて、様々な経験を積んでここまで来た。
現に先日、食べることのできる羊羹に出会えたわけで、ゼロがイチになることの価値を侮ってはならない。これまでは口にすることも憚られたあんこの塊に、美味い美味いとかじりついていたではないか。あれこそが事実でありリアルなのだ!
私は台所からカレーのスプーンを取ってくると、さっそく、モーゼの海割りのごとく漆黒の大海原、もとい大氷河へと突き刺した。
(人生は、チャレンジの繰り返しだ)
ニヤリと口角を上げると、カレーのスプーンにたっぷり乗せた塩羊羹を、一気に口へと放り込んでやった。
(了)




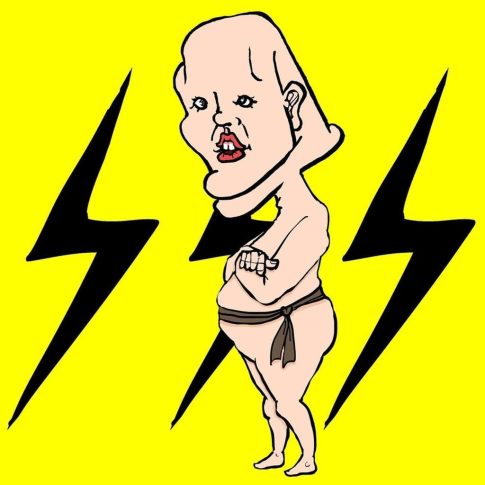
















コメントを残す