生ごみのニオイというか、ヌメッとした何ともいえない食べ物の残骸のニオイーー。
俺は今、流し台の前に立って本を読んでいる。座ってばかりいると体がダルいので、たまにこうして台所で本を読むことがある。
本といっても昔の作家というか文豪が書いたものを、知ったかぶりする程度の読書。それを読んでどういう影響を受けたとか、そんな感想は反吐が出るほど嫌いだ。
不思議なもので、明治から昭和にかけての小説は、貧乏くさいシチュエーションで読むと味が出る。たとえば古びたアパートの階段に腰かけて読んだり、夜中に公園の薄暗い街頭下で読んだり、そのくらいがしっくりくる。
その延長で、室内で読むなら台所がいい。家の中でもっとも貧しさに溢れているのが台所。とくにこの「貧乏の象徴」ともいえる、切れかけた寒々しい蛍光灯というのが乙なところ。
季節柄さすがに虫は飛んでいないが、ハエや蚊がチラチラ影を作るのも、台所ならではの趣がある。
そしてこの生臭さ。昨日、いや一昨日から流しを掃除しようと思いつつ、結局「明日でいいや」とやり過ごしてきての今日。自分が悪いし、この嫌なニオイすらも貧しさの象徴の気がして居心地がいい。
この台所、というほどの広さもないが、この空間に存在する照明は、切れかけた蛍光灯しかない。あとは居間からこぼれる灯りで補う以外に、台所を明るくする方法はないわけだ。
こうして立って読むうちはまだいい。蛍光灯の真下でページをめくるので、暗いどころか本の汚れまで確認できる明るさがある。
だが立ち疲れて床に座ると、ルビが読めないほど暗くなる。そうなるとルビを無視して読み進めるしかないが、読めない漢字を勝手にイメージするのもまた、俺なりの読書の醍醐味といえる。
せっかく台所にいるのだからと、やかんで湯を沸かす。冷蔵庫があるにはあるが、中身は空っぽ。かといって水道水を飲むのも味気ないから、こうして湯を沸かすのだ。
ゴボゴボ音を立てて吹き出した湯を、湯呑に注いでしばらく冷ます。
しかし湯呑ってやつはどうしてこうも持ちにくいのか。猫舌・猫肌の俺にとって、熱い茶や湯を飲むとき、熱さがダイレクトに伝わる湯呑はいつまでたっても持ち上げることができない。まだ取っ手のついたマグカップならいい。とはいえウチにそんなシャレたものはないので、こうして無駄に湯を冷ます時間を費やさなければならないのだ。
数分経ち、おそるおそる湯呑に触れてみる。ダメだ、まだ熱い。片手で本をめくりながら、逆の手で湯呑を触っては諦める。いい加減イライラした俺は、Tシャツの裾を引っ張り上げるとシャツ越しに湯呑をつかむ。
最初からこうすればよかったかもしれないが、どのみち猫舌なわけで白湯を飲むのも一苦労。ずずっと啜(すす)るとまだ熱い湯に舌が縮こまる。おまけに眼鏡が曇って文字が見えない。
再び床に座ると両手で本をめくる。今、俺に貧乏を満喫させてくれるのは、三島由紀夫の金閣寺だ。登場人物が貧乏な僧侶や学生がメインで、なんとなく自分とリンクしてちょうどいい。
ちなみに胸糞わるい部分を読むときは、決まって湯に黒酢を注いだ特製ドリンク片手に読み進めることにしている。不思議なもので、ただの湯であっても啜り続けると味が出てくるし、そこへ黒酢を加えようものならまるで豪華な吟醸酒に変化する。
こうして水道水と黒酢があれば、水から酒まで網羅したも同然といえるのだ。
俺が本を読むときは、何も考えたくないときでもある。人間関係に行き詰まったり、お先真っ暗な人生を突き付けられたり、そんなときに受け身でいると沼にはまる。だからこそ文字を読むのだ。
読書は能動的な行為だから、自分が読もうとしなければ進まない。映画やドラマのように、黙っていても勝手に進むものとはまるで異なる。そして漫画やアニメのように描写もないため、各々がイメージする世界で物語を進められる豊かさ、贅沢さがある。
金閣寺に登場する主人公やその友人、老師、母親、死んだ父親、娼婦どれをとっても、誰一人として同じ顔を連想しないだろう。俺の思うこいつらは、俺が思うこいつらであり、ほかの誰かが思う「そいつら」ではないーー。
こうして読み進めるうちに、いつしか考えたくない現実を忘れ、物語の再現に没頭して時間が過ぎるのだ。
さらに面白いのは、文豪の作品というのは3回楽しめるということ。1回目は物語に入り込みイメージを膨らませて楽しむ。2回目は言葉の使い方や表現方法だけに着目し、内容無視で読破する。そして3回目は一歩引いた目線で客観視しながら読んでみる。
これは3回ともまったく違う感想となるのが面白い。とくに3回目の読み方は「俺ならこう読まない」という前提で読むので、俺の中の別人が読んだ感想が聞けて非常に興味深い。
こうして生臭い台所で立ったり座ったりを繰り返しながら、金閣寺を3回読んだ。なんという偶然か、蛍光灯がペカッペカッと最後の力を振り絞ると、怪しく力尽きた。
(完)






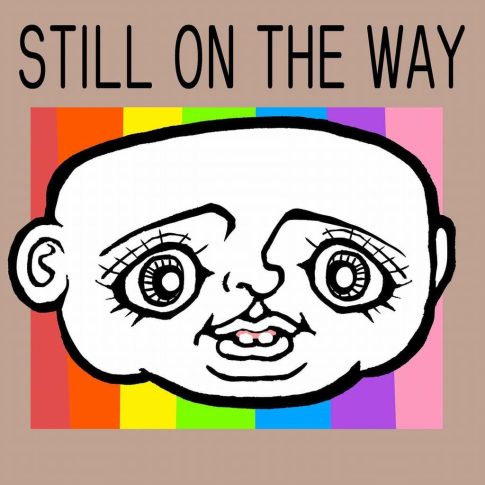


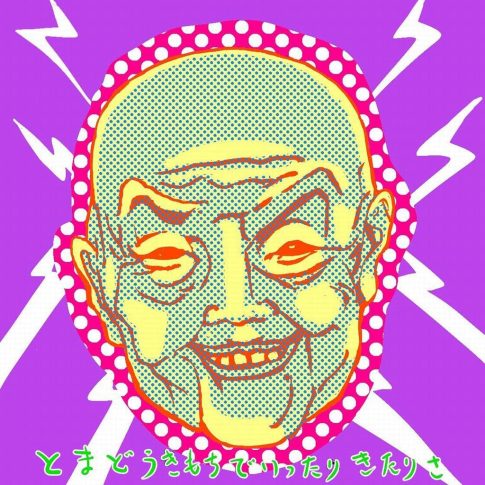











コメントを残す