月に一度届く「月刊社労士」をパラパラとめくっていたところ、時代の流れを感じるニュースに目が留まった。それは"日本における出生率と在留外国人数の変動について"だった。
厚生労働省が調査・統計している「人口動態統計速報(令和6年12月分)」によると、昨年の出生数は72万988人で、令和5年と比べると5%減少し過去最少を更新。一方、死亡数は161万8684人ということで、令和5年より1.8%増加して過去最高となった。
その結果、自然増減はマイナス89万7696人で、令和5年より6万5824人の減少となり、こちらも過去最大かつ18年連続の自然減ということで、少子化の勢いに歯止めをかけるのは難しい様子。
そんな中、出入国在留管理庁が公表する「令和6年末現在における在留外国人数」によると、在留外国人数は過去最高となる376万8977人となり、令和5年度末と比べて10.5%も増加していた。
在留資格別でみると、「永住者」が24.4%で最も多く、「技能実習(45万6595人)」、「技術・人文知識・国際業務(41万8706人)」、「留学(40万2134人)」の順で二桁を維持するなど、労働力や教育を目的とした在留資格の増加が顕著。
そして、国籍別では「中国」が最多となる87万3286人、続いて「ベトナム」63万4361人、「韓国」40万9238人の順となっており、この上位三か国で50%を超えているのである。
とはいえ、日本における在留外国人比率は約3%で、世界的に見るとかなり低い数字といえる。たとえば、アラブ首長国連邦(UAE)などは約88%が外国人という内訳だが、これには西アジア特有の"諸事情"が関係しているのだ。
そもそも、石油や天然ガスなど豊富な地下資源で財政が保たれている西アジアの国々は、労働の担い手として外国人に依存する傾向がある。カネが有り余っていることを示すかのように、超高層ビルなど大規模なインフラ建設のプロジェクトを継続的に行っているため、常に外国人労働者を輸入しなければならない・・という事情があるからだ。
しかも、外国人労働者に永住権や市民権を与えることは稀なので、あくまで「一時的な労働力」として駐在していることからも、移民や共生という考えは持ち合わせていない。よって、揺るぎない資本に基づく経済活動の土台たる"特殊な労働市場"という構図が、圧倒的な在留外国人数を叩き出しているのである。
ちなみに、先進国における外国人比率を調べてみると、スイスやオーストラリア、カナダ、ドイツ、アメリカ、などいずれの国も15%から30%の範囲となっており、これらの数字と比べると日本の3%はかなり低いといえる。
だが、ヨーロッパ諸国はEUの自由移動制度により就労や居住の自由度が高い。さらにカナダやオーストラリア、アメリカなどでは"移民国家モデル"が確立しているため、外国人ありきの文化や経済が整っている点が、日本とは異なる。
加えて、200年以上におよぶ「鎖国」により、近代化へのハンディキャップを背負った島国・日本において、外国人との共存共栄はむしろ不自然といっても過言ではないだろう。そんな日本において、人口比3%が外国人・・という現状は、少なからず違和感を抱くものであるのは間違いない。
そこで、AIに「日本の総人口が年5%のペースで減少し、在留外国人が年3.5%で増加し続けると仮定して、在留外国人数が総人口の10%に達するのは何年後か?」という試算をさせたところ、「約30年後、すなわち2054年頃と推定されます」との回答を得た。
さらに、約71年後である2095年には総人口の半分が外国人となる見通しで、こうなったら単一民族という歴史を捨てて、多国籍国家として暗躍するしかないだろう。
*
日本にとって、多くの外国人と暮らすことは悪いことではないが、某歌詞にもあるように、「おまえが消えて喜ぶ者に おまえのオールをまかせるな」というフレーズだけは忘れないようにしたい。
己の進路を決めるのは自分自身であり、オールを奪われてからでは遅いのだから——。






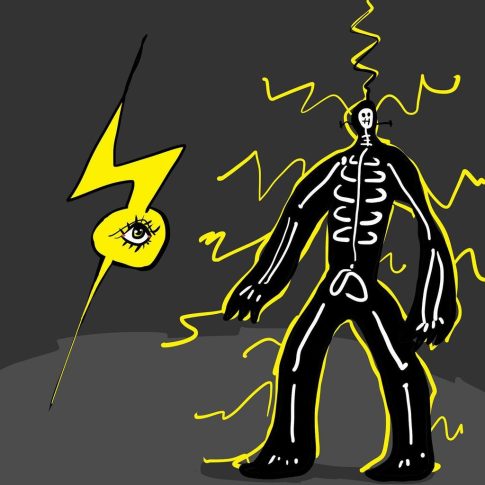
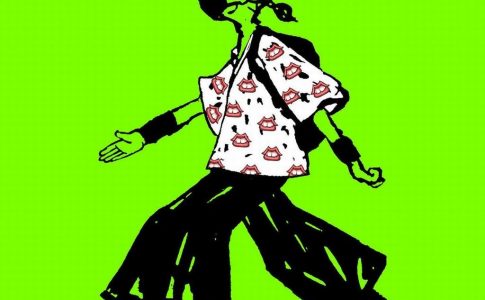

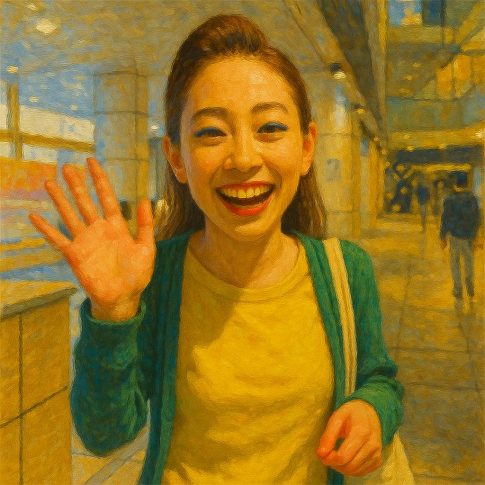
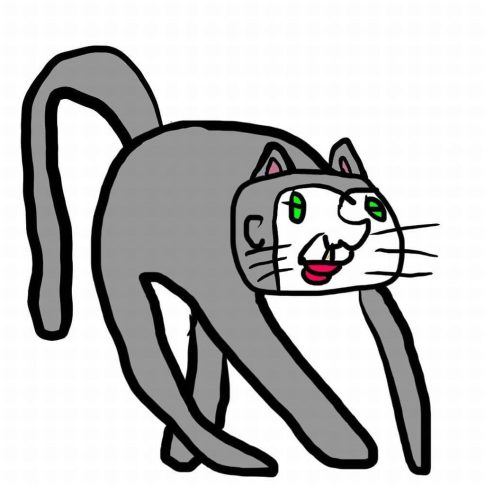










コメントを残す