わたしはカッコつけたがりなので、ピアノであれコラムであれ、他人に何かを披露するならば万全の状態に仕上げたい・・と思っている。無論、才能や実力というものが大前提にあるが、それはさておき今の自分にとってのベストを出し切れるかどうか・・に、すべてのチカラ(体力、精神力、技術力、集中力、イメージ力、運など)を注ぎたいのである。
ところが困ったことに、とある友人からピアノについて「未完成かもしれないが、今の状態を聞かせてほしい」という無謀なオファーがあった。これが、もしもピアノ素人の友人だったならば、渋々ながらも受け入れただろう。なぜなら、素人相手に出し渋るほどの実力ではないからだ。だが残念なことに、彼はピアノ経験者だった。
興味本位からの提案であることは明らかだが、それでもこちらとしては身構えてしまうわけで、最初は丁重にお断りをしていた。しかし、何度も断るうちに「わたしは一体、何をそんなに恐れているんだろう」と、疑問を抱き始めたのだ。
過去のピアノ歴をぶち壊して、新たに「真の音を出す苦行」に足を踏み入れたばかりの、修行僧たるわたしにとって、失うものなどなにもない。むしろ、すべてを捨てて今があるのだから、少しでも何かが積み重ねられているとすれば、それは誇らしいことじゃないか——。
そう思い直したわたしは、友人からのオファーを受け入れた。
*
某日、都内のピアノスタジオにて、ピアノ界のトップ・オブ・トップであるスタインウェイを前にしたわたしは、懐かしいようなおこがましいような複雑な気持ちを抱いていた。
今の自分が出せる音・・それは、このピアノにとってのベストからは程遠いはず。そして、その音色の陳腐さはわたしだけでなく、聴いている友人にも伝わるだろう。それでも、この期に及んで「弾かない」という選択肢はないのだから、鍵盤に触れるしかない——。
そこからさかのぼること数時間前、わたしはピアノのレッスンを受けていた。その時に"ピアノ経験者である友人の前で、スタインウェイを弾かなければならない事件"について、先生に愚痴をこぼしていた。ここまでの一連の流れを聞いた先生は目を細めながら、
「あら、それは大変なことになったわね。見せたくもない裸をわざわざ披露しなきゃならないなんて」
と言いながら笑った。
まさにその通りである。とくに、今取り組んでいるモーツァルトのソナタなど、むき出しの刃を素手で握るかのような痛みと恐怖を感じさせられるほど、先生の前で弾くことすら怖い・・という状況なのだ。それを他人の前で弾くなど、街中を素っ裸で踊るのと同じくらい恥ずかくて無意味で滑稽で、言うなれば"狂気の沙汰"以外のなにものでもない。
そんなことくらい、わたし以上に先生がよく分かっている。だが先生は、「何事もやってみなければ分からない」という精神の持ち主なので、今回の件についても「恥をかいてくればいいじゃない」と、好意的に受け止めてくれたのだ。
「その友達に、『わたしはね、今"寝たきりのおばあさんを起こさないように運ぶ練習"をしてるのよ。あとは、"ホバリングしたり低空飛行したりを繰り返す練習"をしてるの。どう?違いがわかる?』って、聞いてみたら?せっかくのスタインウェイなんだし、微妙な違いでも分かりやすいはずよ」
そんなアドバイスまでもらったわけだが、実際のところ、思った以上に時間がなかった。スタジオを借りた一時間はあっという間に過ぎてしまい、とりあえず何曲かを雑に弾いたところで残りわずかとなってしまったのだ。
その時わたしは、心の中で先生に謝った——ゴメン、いい音を出すことに集中できなかった。
カッコつけたがりは、どうしても上辺のカッコよさを求めたがる癖がある。そうすることで、その場を取り繕うことはできるかもしれないが、本当に大切なことや必要なことを取りこぼしてしまうのだ。——そんなことは分かっている。嫌というほど経験してきたし、数えきれないほどの失敗を繰り返してきたのだから。
それでもやっぱり、できれば曲を曲として聴いてもらいたい・・と思ってしまったのだ。
もしもわたしに、一つの音だけで相手を虜にするほどのチカラがあれば、曲を弾く必要など全くない。単なる音階であっても、それだけで心を揺さぶることができるからだ。実際に、音階だけでその場にいた観客が涙を流した——という逸話を持つピアニストもいるわけで、ピアノという楽器の響きや音色を十分に引き出すことができれば、それだけでヒトは感動するものなのだ。
それでもわたしは、現時点で奏でることのできる"最高の音を出す努力"を拒んだ。その代わりに、一曲を無駄に弾き切ることを選んでしまったのだ。その時に聞こえていた音は、なんとも殺伐とした雑音だった気がする。
だけど、いや・・だからこそ、こんな思いは二度としたくない。そのためにも、いい音を紡ぐこと——そしていつかそれが曲となり、誰かに響いてくれたらいい。
*
久しぶりに触ったスタインウェイは、やはりパーフェクトな役者だった。弾き手次第でどんな音でも出してくる彼(?)は、自分を完璧に使いこなしてくれる使い手を待っているのだろう。
雨降って地固まる・・ではないが、やめたほうがいいと分かっていても、あえて足を突っ込むことで知る感覚がある。それは負け惜しみでもなんでもなく、わたしにとっての貴重な判断材料であり、芸の肥やしとなる失敗——という名の経験なのだ。
今日からまた、階段を一段ずつ上って行こう。いつか明るい世界にたどり着くように。







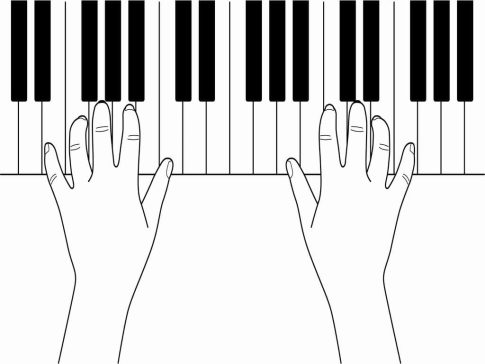













コメントを残す