"ピアノの先生の先生"のところで習い始めてから、早二か月が経とうとしている。出会ってまだ二か月とはいえ、それでも週に2回以上レッスンに通っているため、もうすでに気心知れた関係となりつつある。
そんな先生の先生・・言うなれば師匠には、一般的なイメージでの"ピアノを習う"とはちょっと違う教わり方をしている。なにを叩き込まれているのかというと、弾き方というより「ピアノという楽器の扱い方」なのである。
他の楽器の経験があまりないので断言できないが、管楽器でも弦楽器でもまずはいい音を出すべく、ロングトーンなりなんなり"音作り"をするだろう。
素人ながらも、ヴァイオリンやトランペットの演奏を聴いたときに、音がヨレていたりクリーンじゃなかったりすれば「あぁ、あまり上手くないんだな」と感じるわけで、中でも管楽器はそもそもの音が大きいため、出し方次第ですべてが台無しになることも。
正直なところ、打楽器に関してはそこまで違いを感じることはなかったのだが、友人の和太鼓演奏を聴いてからは、一つの音しか出ないと思っていた太鼓でさえ、叩き方や叩く部位によって音が変わるということを知った。そのくらい、楽器というのは音の出し方——すなわち、楽器の扱い方が重要なわけだ。
ところがピアノは、どちらかというと「いかに複雑な音形を弾きこなすか」とか「いかに速く指を動かせるか」といった部分に注目しがちであり、ピアノの音ひとつひとつの音色に気を使うことは少ない。
その理由として"複数の音を一気に出せる"という楽器の特性が挙げられる。
ピアノの演奏は、右手と左手でそれぞれの音を出すわけだが、少なくとも右手と左手という"二つの音"がある。さらには和音や重音のように、複数の音を一気に出す場合がほとんどのため、ピアノ一台でメロディーと伴奏・・言い換えれば"主役と脇役"を演じることが可能なのだ。
このような特性からも、鍵盤ひとつひとつの音色・・というより全体のバランスに意識が向いてしまうのは致し方ない。おまけに、指使いや音の強弱を常に意識しなければならず、単音の楽器よりも音色への配慮が薄れがち——。
そんなわけで、物理的な指の動きや単純な音量の大小のみを追い続けた結果、肝心の"音色"が置いてけぼりとなる演奏しかできなくなっていたわけだ。
(他の楽器ならばまずは音の出し方を習い、それから音色を追求するだろう。だがわたしは、どれがいい音なのかも分からないし、どうすればいい音が出せるのかも知らない。これじゃあ「ピアノ」という楽器を扱えていないも同然だ・・・)
そう感じたわたしは、ピアノという楽器の音の出し方を習いに、師匠の元を訪れたのである。
二か月が過ぎてようやく「どれがいい音なのか」が分かり始めた頃、並行してピアノの練習が楽しくなってきた。やはり何事も「できなかったことができるようになる」というのが、一番の楽しみにつながる。さらに、いい音を求める・・という作業はいつまで経っても終わりが来ないため、より良い音を求めてどんどん没頭することで、楽しみもどんどん増えていくのだ。
例えるならば、四角い氷をちょっとずつ削りながら球体にしていく作業のように、最初はいびつな丸だったものが徐々に滑らかなカーブを描き、どこをどう見ても角のない美しい球に近づく喜びは、言葉にできない満足と興奮を覚えるのと似ている。
しかも、ピアノの曲は無数に存在するため、全ての曲でいい音を出そうとすれば、それはもう一生かけても足りないのは言うまでもない。まるで、読みきれないほどの蔵書の山に囲まれた本好きの子どものように、終わりのない音楽の海を漂うわたしは、いつまでたっても飽きない現実を覚えたのである。
*
そんなわけで、今日もわたしは音色を求めて旅に出るのであった。






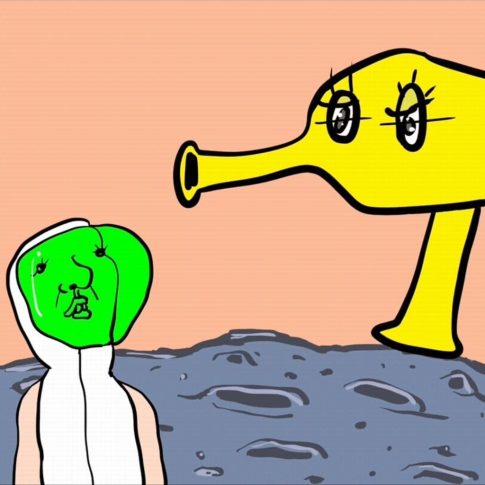
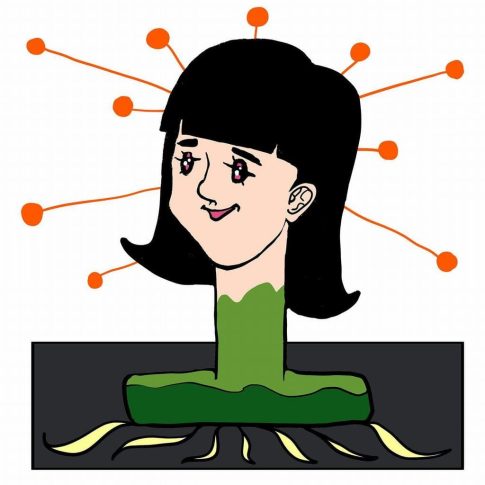













コメントを残す