戦いを終えたわたしは、改めて昨夜の試合について思い返してみた。
久しぶりに、適度の緊張と極度の集中を保ったまま舞台に立つことができた気がするのだが、その要因として「手を抜かなかったこと」が大きく関係していると思う。
いいところを見せよう・・などと邪なことを思うと、途端に調子は崩れるもの。もちろん、普段の練習でそう思いながら演奏しているのならば話は別だが、大体そういう人に限って、普段は一生懸命練習しているものだろう。
だからこそ、本番でそのマインドを変えることは得策ではない。だったらいつも通りに一生懸命弾いたほうがマシである。
そしてわたしは、ショパンのポロネーズ5番(本番で弾いた曲)の譜読みを始めた頃から一貫して、"楽譜に忠実であろう"と決めていた。なぜなら、感情移入できるほどの技術もセンスも持ち合わせていないからだ。
だったらまずは、楽譜に書かれたことだけでも再現できるように・・と考えたのだが、それをするにもやはり、曲の構成やショパンについて知っていなければならない。
なぜなら「当たり前にそうするべきこと」が、曲にはあるからだ。
たとえば、メロディーと伴奏があればメロディーを際立たせるのは当然のことだし、同じパッセージを繰り返すならば毎回同じ調子では弾かないし、そういった"別の意味での当たり前"を知らなければ、単純に楽譜に書かれたことだけを弾いてもしょうがないのである。
・・というわけで、技術的あるいは表現力的な基礎練習も行いつつ、ポロネーズに取り組んだわけだ。
そして終盤にかけては、途中でふと楽譜が飛んでしまう現象への対処法として、「左手のみ、次に弾く音を先に目で確認してから指をそこへ誘導する」という作戦に出た。
暗譜をするにはそれなりの練習方法があるが、今回わたしは楽譜を置いた状態で弾く・・という選択をしたので、完全なる暗譜をする必要はなかった。
だが実際のところ、楽譜を見ながら弾くというのは難しいもので、ある程度弾けるようになるとどうしても鍵盤を見てしまうのだ。
そのため、楽譜は置いてあるが「それを見ながら弾く」というのは現実的ではない。なぜなら、今さっきまで鍵盤を見ながら弾いていたのが、突然、楽譜を見たところで脳みそがバグるというか、"楽譜を見る"というマインドになっていないため、音符を見たとて指先へは伝わらないのだ。
これは不思議なことだが、本当にそうなるから不思議である。
次に弾く音(鍵盤)を目で示す=楽譜が頭に入っているというわけだが、とくに伴奏となる左手は失念しやすいため、少なくとも左手だけは目で誘導する方法をとろうと、わたしは必死に左手の鍵盤を目で追った。
この練習の甲斐があってか、本番でもあくまでお守り代わりに楽譜を置いているだけで、鍵盤に集中しながら弾き終えることができた。
こればかりは「作戦勝ちだ」と、内心にんまりしたものである。
*
そしてもう一つ、本番に使う"武器"となるピアノについて。
ルーテル市ヶ谷ホールに設置されているピアノは、スタインウェイD-274というコンサートグランドの最高峰。あくまで個人的な感想ではあるが、その特徴はまさに「薄氷を踏む」かのような薄くて硬いタッチにある。
よって、アップライトで練習しているわたしからすると「触れただけで音が出る」という、恐怖にも似た感覚なのだ。
それに加えて、薄い氷のような脆さの中にも確実に硬さがあるわけで、本当に薄氷を踏むかの如く、繊細かつ緊張感をもって打鍵しなければならない怖さがある。
アップライト、しかも消音装置のついた電子ピアノの音と比べると、その幅はとてつもなく広い。わが家のピアノでは3段階しか出ない音も、会場のスタインウェイでは20段階くらい出てしまうから非常に困るのだ。
そのため、ホールリハーサルの時点で鍵盤のタッチの深さ・・いや、浅さを脳に叩き込み自宅へと持ち帰った。そしてひたすら、わが家では出ない音が「実際には出る」という確信の元で練習を繰り返した。
しかしこれは、拷問のような練習だった。なんせ実際に聞こえている音は3種類しかないにもかかわらず、脳内では「あの音」が響いているというイメージで弾き続けなければならないのだから。
それでも、本番でいきなり薄氷を踏まされたのでは対処に困るわけで、今のうちから「氷を割らずに歩き切る練習」をしなければ、当日困るのはわたしである。
そんなプレッシャーを自らに課しながら、本番までの数日を過ごしたのであった。
発表会当日、大勢の友人・知人が足を運んでくれたが、そのほとんどはピアノに精通しているわけではなく、どちらかというとわたしの筋肉とドレス姿を堪能するために訪れた面々だった。
演奏で唸らせることはできなくとも、入場シーンで笑いを含む感動を与えることはできるはず——そう考えたわたしは、早々とレンタルドレスやヘアメイクの予約を済ませ、みんなを喜ばせる準備を整えた。
だが、実際に会場に訪れた友人らを見て、衣装だけでは乗り切ることができないと悟ったわたし。
音楽やピアノに造詣が深くないメンツ相手だから、とりあえず弾き切ればいいだろう・・などという考えが通用しないことを、彼ら彼女らを見て知ったのだ。
(物事の本質が分かる人間に対して、安牌的な演奏を披露すれば満足できるのか——?)
音楽の専門家かどうかは問題ではない。むしろ、素人だからこそ真髄に触れることができると、わたしは信じている。
余計なウンチクなどどうてもいい。そこに本気のパフォーマンスがあったのか、やるべきことを全て出し切る演奏をしたのか・・それはむしろ、知識のある経験者よりもまっさらな素人のほうが、鋭い観察眼を持っているものだから。
こうしてわたしは、あのスタインウェイが持つポテンシャルをできる限り引き出す演奏を心がけた。そのためには、触れただけで出る音をいかにたくさん散りばめられるか・・にあると自分に言い聞かせた。
強い音よりも弱い音のほうが、力と神経を使う。弱い音を出そう・・と、そっと触れたはいいが弱すぎて音が出なかったらどうか。それは当然「ミス」となる。だからこそ、しっかりと弱い音を弾かなければならないのだ。
さらに、強い音というのも、出し方によっては金属バットで殴ったかのような乱暴な音になるから注意が必要。わたしの解釈では、指を着地する勢いで打鍵すると乱暴な音になる。よって、瞬間的にでも鍵盤に触れてから押す・・という動きを心がけた。
強い音が乱雑であっていいわけがない。力強くも丁寧に——。
*
こうして、やるべきことが満載の12分間を終えたわたしは、ただただ過ぎ行く瞬間に感謝した。
一小節ごとに、もう二度と戻ることのないパッセージに感謝した。
決して振り返らない、振り返ったところでそこにはもう道はない。あるのは崩れ落ちた崖のみで、みるみる迫りくる空虚に飲まれる前に、わたしは前を向いて走り去らなければならないのだ。
だからこそ、悔いの残らない打鍵をしなければならない。なんとなくまとめあげるのではなく、わたしの全てをぶち込んだ演奏でなければ、結果的に足を踏み外して谷底へと落ちていくのだから。
——などと、素人が一丁前にプロっぽい考えを抱きながら、散々なミスを乗り越えて326小節の旅・・いや、戦いを終えたのであった。
*
会場に来てくれた皆さん、そしてSNSなどで演奏動画を視聴してくれた皆さん、本当にありがとうございました。
次回は二年後ですが、そのときはぜひ目の前でわたしの筋肉とドレス、そしてピアノを楽しんでください。









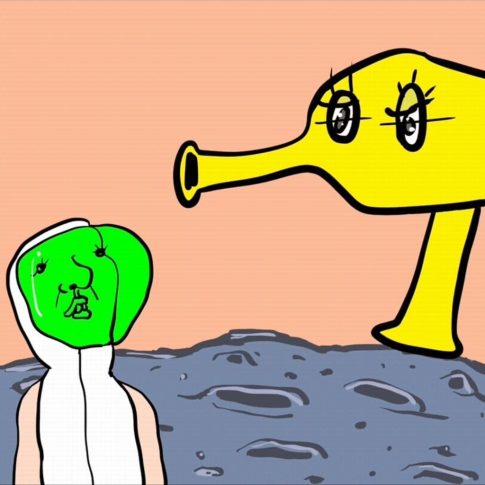











コメントを残す