「驚かないでね。リュックにカマキリが付いているの」
近くで誰かが囁いた。
わたしは今、乗客で溢れかえる銀座線の車内にいる。しかも運悪く「渋谷行き」のため、ハロウィーンの仮装をした若者や外国人でごった返している
「ハロウィーンのグッズか何かかと思ったけど、本物みたいだから・・・」
ケータイをいじっていたので声の主を見てはいないが、落ち着いた感じの女性だろう。リュックを背負う別の女性に向かって、静かにそう話しかけていた。
それと同時に、銀座線は溜池山王駅に到着した。
わたしは南北線への乗り換えのために、人混みをかき分けて降り口へと向かう。
そしてようやくホームへ降り立つと、わたしの目の前に「カマキリが付いている」と言われた女性が立っていた。
背中からリュックを下ろし、生地にしっかりとしがみついている緑色のカマキリに向かって、息を吹きかけている。
しかしながら、呼気で吹き飛ばされるほど昆虫も柔(やわ)ではない。
じっと見ているわたしに気付くと、女性はすがるような目で
「お願いです、取ってもらえませんか?私、虫を触れなくて・・・」
と懇願してきた。
まぁそんな気がする。とてもじゃないが、昆虫を素手でつかめるような顔はしていない。
「いいですよ」と軽く返事をすると、リュックにへばりつく緑の虫に近づいた。
(・・・カマキリじゃない、バッタだ!)
そう、こいつはカマキリではない。みるからに遠くまでジャンプできそうな、立派な後ろ足を持つバッタである。
細くて角ばった緑色のバッタは、リュックの繊維に手足を絡ませ「そう簡単には離れないぞ」というオーラを放っている。
ちなみに、わたしが想像するバッタの引き剥がし方は、胴体を両側からつまんで引っ張る方法。
だが、もしもバッタの腹を強く握りすぎて、圧死させたら可哀そうである。
かといって触角に触れるのはマナー違反な気もするわけで、わたしは密かに悩んだ。
(この、後ろ足を引っ張ってみよう)
体長の半分以上もある、長い後ろ足ならば掴みやすい。
足に触れられて、嫌がって飛んでくれたらラッキーだし、そうじゃなくても足をつまんで引き剥がして、そのままどこかへ逃がしてやればいい。
こうしてわたしは、バッタの右後ろ足をつまんだ。すると予想通り、バッタは嫌がってリュックから手を離したのだ。
すかさずホームへ着地させると、一部始終を見守っていたリュックの女性は、ホッとした表情でわたしに向かってお礼を言った。
「でも、ここじゃ踏まれちゃうよね」
小さな緑色のバッタは、まったく馴染めない色合いとテクスチャーのホームでじっとしている。
そのすぐ横を、人間たちが速足で通り過ぎて行く。
「まぁ仕方ないか。・・・じゃあね」
バッタを見守っていてもしょうがないので、わたしは女性を促しその場を去った。
だがしばらくして、どうしてもバッタの行方が気になるわたしは、元の場所へ戻ってみた。
すると、さっきと同じ場所でバッタは固まっていた。
そこでわたしは再び後ろ足をつまむと、人に踏まれないようなところ、たとえばホームの端っこに移動させてやろうと考えた。
そして、長い後ろ足をつかんだ瞬間――。
バッタはものすごい力で嫌がったのだ。
人さし指程度の大きさの角ばった緑の生き物が、信じられないほどの強い力で必死の抵抗をみせたのだ。
(勘違いするな!わたしはお前を助けようと、足をつかんだのだぞ?)
いや、違う。そういうことじゃない。バッタは自らの意思で、わたしに捕獲されることを拒んだのだ。
助かるのか、はたまた殺されるのかは分からないはず。いやいや、そんなことはどうでもいい。バッタは、とにかくわたしに捕まりたくなかったのだ。
その結果、人が行き交う危険な場所に取り残されたとしても構わない。
運悪く踏まれて死んでも構わない。
そんなことよりも、今ここでわたしにつまみあげられることが、嫌なのだ。
――そんな強い意志を感じた。そう、バッタの後ろ足に触れたわたしの指先から、奴の「断固たる拒否」が伝わってきたのだ。
わたしはしばらく、その場で呆然とした。
人助けをして逆襲に遭うとは、思いもよらなかった。正確には人ではないが、それでも命を助けようと差し伸べた手を、あんなにも全力で拒否されるとは思わなかった。
まるで、わたしに夢中だったはずのオトコにフラれた気分である。
身じろぎせず、その場でうずくまる緑の角ばったバッタ。
そしてそれを見下ろす、放心状態のわたし。
(これも運命ってやつか・・)
バッタの固い意志に負けたわたしは、後ろ髪を引かれる思いでその場を去った。
ここへはもう二度と、二度と戻ってこないと誓おう――。
*
南北線の車内で、わたしは一人悔やんだ。
(あぁ、せめてもう少しだけ、人の少ない場所へ着地させるんだった)
果てしない罪悪感に襲われる。
(それでも、どうか覚えておいてくれ。誰かに踏まれてこの世を去ったとしても、わたしは決して忘れない。驚くほどの強さでわたしの指を蹴り飛ばした、漲るお前の生命力を)
(了)




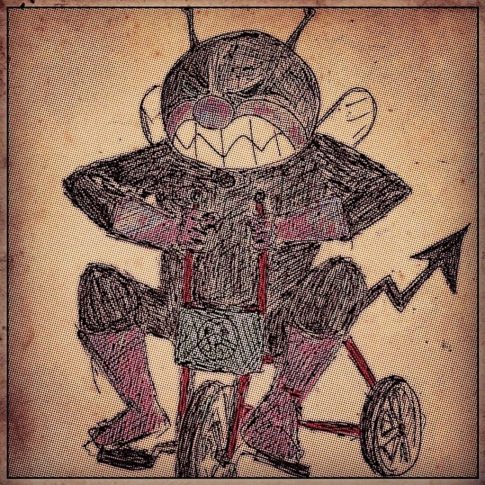
















コメントを残す