日常生活を送る中で、「真っ暗」という空間に身を置くシチュエーションはほぼないだろう。
暗くて有名といえば映画館。エンドロールが終わり、場内の照明が点くまでの数秒間、いわゆる真っ暗になる。
だがあれだって、非常出口の灯りや座席下のフットライトなど、何かをぼんやりと判別できる程度に明るい。
また、真夜中というのも真っ暗といえる。しかし都内においては、街の灯りが邪魔をするので、懐中電灯なしでも十分歩くことができる。
田舎の夜道は真っ暗に近い。とはいえ月や星の輝きで、うっすらと輪郭が浮かび上がってしまうだろう。
つまり、本当に真っ暗な空間というのは、普通に生活を送っていても経験できないものなのだ。
ところがわたしが知る限り、ここだけは確実に「真っ暗だ」と断言できる場所がある。
それは、長野市にある善光寺の本堂のさらに奥、お戒壇(かいどう)巡りの回廊だ。
最後にここを通ったのは、高校生の頃。暗黒よりも暗い闇、吸い込まれそうな恐怖しかない地下回廊を、そろりそろりと摺り足で進んだ記憶が蘇る。
目の前に手をかざそうが、何も見えない。前を見ても後ろを振り返っても、人間の視覚で認識できるものなどなにもない。
そもそも、自分自身がそこにいるかどうかも怪しくなるほどに、暗闇以外に信じられるものは何もないのである。
お戒壇巡りとは、
「瑠璃壇床下の真っ暗な回廊を巡り、中程に懸かる『極楽の錠前』に触れることで、錠前の真上におられる絶対秘仏の御本尊様と結縁を果たし、極楽往生の約束をいただく道場です。」
と、善光寺は説明する。
つまりここは、単なる真っ暗な廊下ではなく、修行の場となる「道場」なのだ。
これには得心が行った。
回廊の距離はわずか45メートル。明るい状態ならば、10秒あれば駆け抜けられる距離にもかかわらず、真っ暗闇を恐る恐る歩を進めるわけで、5分かかってようやく地上に戻ることができる。
歩き方としては、右手で壁を伝いながら順路を確認し、左手は前に伸ばして先を行く参拝客とぶつからないとうにするのだ。
回廊の幅がどのくらいなのかもわからぬまま、もしも右手を壁から離したら、
「わたしは一生、この暗闇に閉じ込められるのではないか」
という恐怖に襲われるため、とにかくひたすら右手で壁を撫でながら、”極楽の錠前”に触れる瞬間を待つのであった。
これほどまでに心細く、耐えがたい恐怖を押し付けられる行為など、精神修行以外にありえない。
よって、極楽浄土行きを約束されるための修行であることに、ひどく納得してしまったのである。
*
そして今日、久々に「暗闇の恐怖」を体験すべく、お戒壇巡りに善光寺へやって来た。
国の施策である全国旅行支援の影響か、関西弁など地方の方言が飛び交うなか、わたしはさっそく回廊へと向かった。
最新型の「電子マネー対応タッチパネル券売機」で参拝券を購入。これならば、現金特有の「小銭やお釣りのやり取り」に煩わされることなく購入できるため、便利である。
その後、我先にと押し寄せる観光客とともに、わたしは暗闇へと向かった。
回廊の入り口から続く手すりは、高校生当時のままである。多くの人に撫でまわされ、ツルツルに磨き上げられた分だけ時代を感じるが。
そしていよいよ、階段を下り始めた。
右手でしっかり手すりに掴まると、待ち構える暗黒の世界へ、ゆっくりと歩を進めていった。
お戒壇巡りが初めてと思しき関西人らが、わぁわぁきゃあきゃあ騒ぎながら消えて行く。
(ここは道場であり修行の場。なにしに来たのかわきまえてもらいたい!)
修行の先輩として、背後から厳しい視線を放つわたし。
――とその時。
なぜか廊下の左端に、ぼんやりと灯りが見えるではないか。
さらにその先の床にも、小さな蝋燭の炎らしきものが見える。
(修行の場なんだから、真っ暗でなきゃ意味がないんじゃ・・・)
当時の恐怖が思い出せなくなるほど、足元の左前方が薄明るいのだ。
――いったいなぜ??
途中、本来の暗闇に包まれた区間もあったが、回廊の三分の一くらいはぼんやりと灯りに助けられた感覚。
住職に尋ねたわけではないが、きっと、暗闇すぎてパニックになったりトラブルを起こしたり、といったケースが相次いだのではなかろうか。
まさかとは思うが、
「こんな真っ暗じゃ、子どもが怖がるでしょ!」
などとクレームをつけた親がいたとすれば、とんだ笑い種である。
とにかく、暗闇初心者たちの反応は上々だったが、ベテランのわたしにとっては拍子抜けする結果となった。
1センチ先すらも見えないスリルと恐怖を乗り越えて、ようやく触れることができる大きな鍵。
煩悩に打ち勝ち、恐怖すら跳ね飛ばす精神力を誇示する代わりに、極楽浄土行きの権利を勝ち取るのでる。
それらのに、こんな手ほどきがあったのでは、極楽浄土とやらは大渋滞となるだろう。
*
次回、お戒壇巡りをする機会があれば、入り口の階段から目を閉じて進むとしよう。
もはや己にハンデを課さなければ、真の暗闇と相対することすらできない世の中となってしまったのだ。




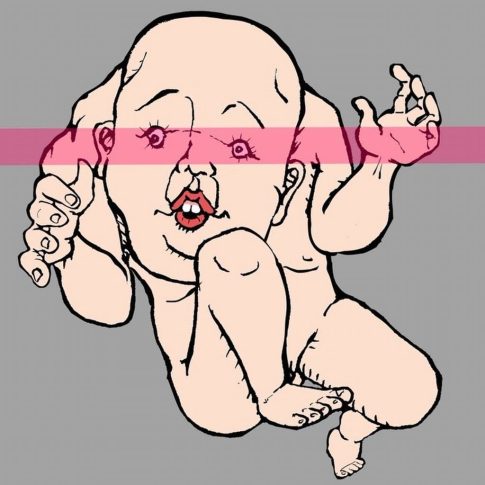


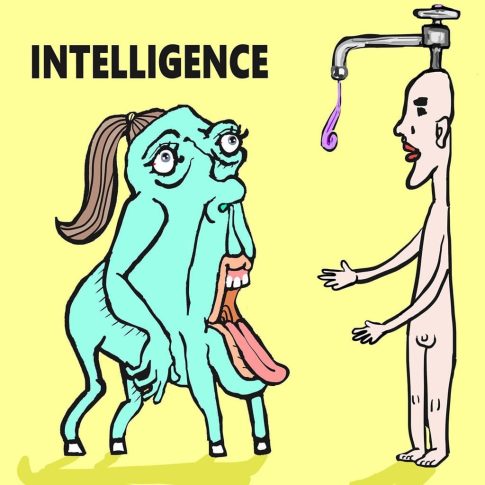













コメントを残す