さかのぼること西暦900年代、中国の宮廷や上流階級の女性の間で「小さい足は美、貞淑、高貴さの象徴である」との考えから、女性の足に対して纏足(てんそく)が行われるようになった。
纏足とは、かつて中国で行われていた”女性の足を人工的に小さく変形させる風習”で、女子が5歳から7歳頃になると始められた。
その方法とは、足の甲を内側へ強く折り曲げ布で何重にもきつく縛ることで、足の指が足裏に押し付けられ甲が折れ曲がる・・という、じつに残酷で非人道的なやり方だった。
そして、女児が成人する頃には、足の長さが7~10センチほどの「三寸金蓮(さんすんきんれん)」と呼ばれる、極端に小さな足が完成するというもの。
当時の中国では、纏足が結婚の条件であったり、歩行が不自由=外出しないことで貞操を守るという価値観と結び付けられたりと、女性の従順さや上品さ、貞淑さの象徴として纏足が存在していた。
だがこれは、言い換えれば”男性による支配的価値観における理想の女性像”なわけで、現代においては女性差別および人権侵害の象徴として歴史的な研究対象として扱われている。
(とはいえ、1912年の中華民国成立と同時に「纏足禁止令」が公布されたというから、比較的最近まで続いていた・・という見方もできる。しかも、農村部ではその後も慣習として続いており、1949年の中華人民共和国成立に伴い、政府が大々的に禁止および取り締まりを実施したことで、纏足がほぼ完全に消滅したといわれているが、あれだけ広大な土地に13億人以上の人間が暮らしているのだから、もしかすると未だに纏足の風習が残っている地域があっても不思議ではないだろう)
というわけで、強制的に小さな足を作らされた女性らは、痛みと苦しみに耐えた結果、「結婚」というオンナの幸せを手に入れてきたわけだ。だが、そんな苦痛から逃れるべく足元に自由を与えたことで、足幅がどんどん広がっていったわたしは、当然の結果的として「オンナの幸せとは無縁な人生」を送ることとなった。
なにを隠そうここ10年、雨が降ろうが雪が降ろうが年間を通してサンダルしか履かなかったわたしの足は、いつの間にか前後左右に広がり、見るからに丈夫で安定感のある「土台」を完成させていたのだ。
よくよく観察してみると、足長(爪先から踵までの長さ)も伸びているのだが、それよりなにより足囲(親指から小指の付け根までの長さ)と足幅(足の横幅)が格段に広がったことで、一般的な女性用の靴に足が入らなくなっていた。
そのため、辛うじてつま先を突っ込むことはできても、小指までスッポリ入ることはない——そう、足底のみならず足指までもが丸々と太く立派に育ってしまったのだ。まるでマサイ族の足のように!!
こうして足元に自由を与えた結果、伸び伸びと成長した足底および足指は、四方八方に拡張・隆起したことで、もはや誰からの抑圧も受けることなく圧倒的なデカさと分厚さを誇るようになったのである。
そのため、過去に購入したお気に入りの靴たちは、どれもオブジェとしての価値しか持たなくなっていた。
(あぁ、このUGGはロンドンで買ったものだし、こちらのビルケンシュトックは今では売っていない代物・・大して履きもせず大切にしまっておいた結果、もう二度と履けなくなるだなんて、いったい誰が想像できただろうか)
お気に入りの靴たちは、クリーニングに出して完璧な状態で保管するのがわたし流。そのため、新品同様の状態で眠っていたお姫様たちを取り出すと、断腸の思いでゴミ袋にぶち込ん——で、できない。
数回しか履いていない上に保存状態のいい靴を捨てるなんて、しかも、気に入って買った靴たちを「ゴミ扱い」することなど、どう考えてもできるはずがない。
とはいえ、メルカリ等で売るのは面倒なので絶対にできない。かといって、サイズ(25~26センチ)的に履ける女性が少ないことと、好みの違いもあることから、誰彼構わず押し付けるのも憚られる。
それよりなにより、どうせならば気に入って履いてくれる者の手に渡ってもらいたい・・と願うのが、マサイ族となったわたしの小さな我がままでもある。
(まぁ、友人の手で捨てられようが売られようが、それはそれで満足だ)
*
というわけで、明らかに戦闘部族化した我が足を拒む靴たちを、泣く泣く断捨離する覚悟を決めたわたし。
これからも、世間の常識などに囚われず足元の自由を守ることで、冠婚葬祭時には苦痛に顔を歪める人生を送るのである。




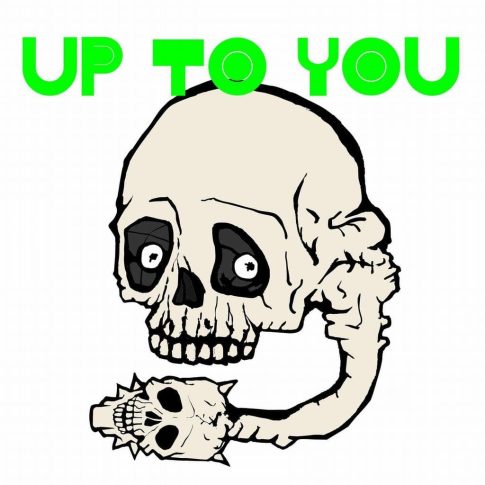




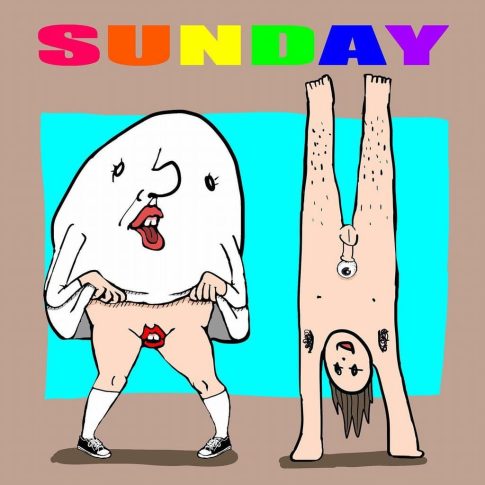
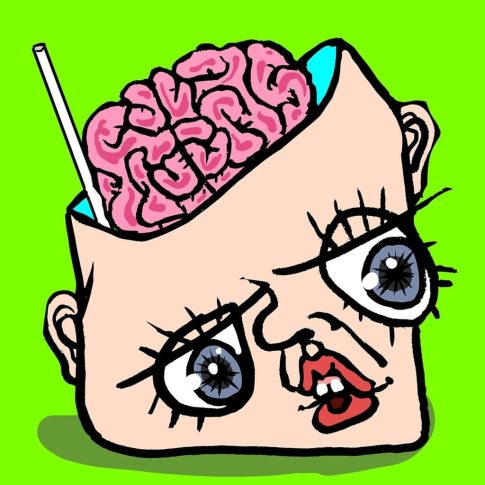










コメントを残す