――暑い。
夏なんだから暑いに決まっている。だがそれにしても暑すぎる。
同じ暑さでも、オーストラリアやアメリカ西海岸のような、カラッとした暑さならばまだ我慢できるのに。
いや、そんなことはない。
車社会のアメリカやオーストラリアで、40度を超える炎天下をモタモタ歩いていれば、それはほぼ「死」を意味する。
*
宿泊先のエアビから最も近いコンビニまで、徒歩約15分。
見渡す限りの広大な土地と、立派なアスファルト道路しかないラスベガスで、私は生ぬるい覚悟と共にコンビニへ向かって歩き始めた。
正午過ぎ、私と空の間には邪魔するものは何もない。余すところなく紫外線を届けようとする、美しく済んだ青い空。なんらかの電磁波を放っているであろう、殺人マシンと化したギラギラの太陽。
そんな過酷な環境下において、たまに吹きつける熱風だけが、辛うじて「私はまだ生きている」ということを教えてくれた。
(これは・・・コンビニにたどり着く前に力尽きるかもしれない)
こんなバカげた考えを持ったことは、未だかつてない。炎天下とはいえ、たった15分歩いたくらいで人間が死ぬなどという、笑えない冗談があるはずもない。
だが事実、私はいま生命の危機を感じている。
帽子もなければ水もない。タオルも新聞紙もなにもない。おまけに、日陰となりうる建物すら存在しない。つまり、私の命を奪うべく照り付ける灼熱の太陽から、逃れる術はないのだ。
足元を一匹の虫が這っている。だが、この虫はあと数分でこの世を去るだろう。もはや見た目からも容易に確認できるほど、命の残量に赤信号が灯っているのだ。
砂漠地帯を切り拓いて作られた人工都市、ラスベガス。甘っちょろい考えで道を歩いていたら、冗談抜きに危ないということを思い知る。
なぜなら、携帯電話の画面には「高温注意」の文字が現れ、うんともすんとも動かなくなったのだ。
(地図も見られない、助けも呼べない。もう終わりだ・・・)
*
そんな懐かしい思い出がよみがえる。
だがここは、アメリカでもなければネバダ州でも砂漠地帯でもない。東京都のど真ん中、港区は白金である。
そして駅前のスタバは今日も満席。とはいえさすがにテラス席は空いている。そりゃそうだ、なにも命がけでコーヒーを飲む必要などないからだ。
テラス席を満喫するのは、大柄な外国人とそのペットである大型ブルドックのみ。そこから少し離れたテーブルに、私は腰を下ろした。
氷を少な目に入れてもらったアイスコーヒーが、みるみるカサを増していく。しまった、多めにしとけばよかった――。
10分もしないうちに、私は何らかの限界を感じ始めた。首や脇だけでなく、腹や太ももからもじわじわと溢れ出る大量の汗。さらに額からは大粒の玉がボタボタと滴り、あえなく両目を直撃。
朦朧とする意識のなか、私はなぜこのような苦行に挑戦しているのか自問自答する。無論、答えは出ない。
テーブルの下に敷き詰められたタイルに、腹をこすりつけながらゴロンと寝ころぶブルドッグと目が合う。
あぁ、そこは確かにひんやりとしていて気持ちよさそうだ。それに比べて私のところは・・・灼熱地獄だ。
もはやここまでかと、命が絶える前に席を立とうとしたその時、まさかの「神風」が吹いた。
(おぉ!まるで結露しそうな冷たさだ!!)
なんと、スタバの隣りの花屋から冷気が流れ出てきたのだ。ちょうど客が店を出るタイミングで、入り口のドアが開いたのだ。
それにしてもなんという冷たさだ。地獄の業火に悶え苦しむ私に、天国から救いの手が差し伸べられたかのような、高貴で清々しい冷風である。
まさに心が洗われる思いだ。ベトベトでドロドロの薄汚れた罪人に向かって、このような透明で澄み切った清風が届けられるなど、本来、あってはならなぬこと。
これこそが、神の思し召しなのだろうか?
「おまえのような低俗で卑しい人間にも、一度だけチャンスを与えてやろう」
そんな声がどこからともなく響いてくる。
(あぁ、神よ!)
意を決した私は、すぐさま席を立つと帰宅の途についた。
そうだ、帰ったらすぐにシャワーを浴びよう。そしてキンキンに冷えた部屋で、昼寝をしよう――。








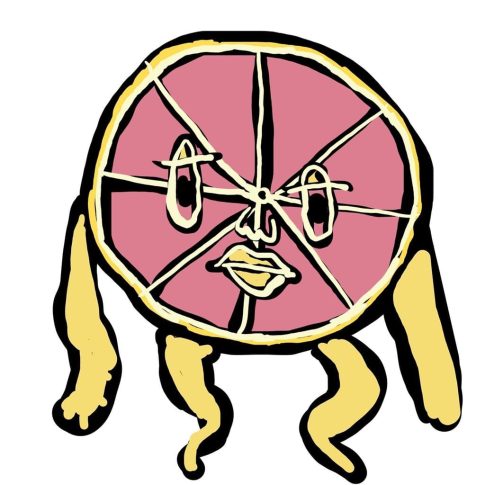












コメントを残す