(このオッサン、絶対に「弁当ジジイ」ってあだ名付けられたわ)
ホテルのフロントで、オッサン、いやクライアントの社長がゴネているーー。
ことの発端は、わたしが弁当の愚痴をこぼしたことだった。
*
「16時に届く予定の弁当が、来なかったんですよ」
ミーティングの冒頭、アイスブレイクとして本日起きた”食べ物の恨み”を披露したわたし。
今回、「特製ハンバーグ弁当付き」の宿泊プランを選択。今日は仕事があるので、16時に弁当を届けてもらうよう手配した。
しかし、16時を過ぎてもチャイムはならない。腹の虫がグゥグゥ鳴く。
さらに17時半になっても人っ子一人来やしない。
(今さら届いても、出かける準備もあるし食えないな)
とりあえず、部屋を出るまでには弁当は届かなかった。その理由を移動途中に考えてみた。
まずはフロントが時間を聞き間違えた可能性が高い。16時ではなく6時と聞き間違えた結果、18時過ぎに届けられたのではなかろうか。
そうでなければただ単に伝達ミスか。
たしかに宿泊プランに弁当は付いているが、事前に注文しなければ届かない。フロントからキッチンへ、わたしの弁当の予約が伝わっておらず、結果として弁当が用意されなかったか。
いずれにせよ、本日の弁当を手に入れることはできなかったのだ。
そんな話をしたところ、地元の社長がご立腹。
「私がフロントに注意しますよ」
やはり地元愛の血が騒ぐのか。遠路はるばるやって来た客人をもてなすのは、当然の義務といった勢い。
ミーティングが終わり、駅前のホテルまでゾロゾロと移動すると、早速、例の社長がフロントへ向かって切り込んだ。
「×××号室の彼女のところへ、弁当が届かなかったらしいのだが」
フロントのほうでもおそらく全てを把握しており、すぐさま横一列に並ぶと雁首を揃えて頭を下げた。
「まことに申し訳ございません。18時にお届けに伺いましたが、ご出発の後でした」
(やっぱり。時間を間違えたんだ)
すると社長は理解を示すフリをして、こう返した。
「そうだろうね、きっとそうだと思ったよ。それはいいんだ、もう済んだことだし」
すぐさまフロントは、
「お弁当代を返金させていただきます」
と提案してきた。
その弁当は通常だと2,000円する高級弁当だ。弁当付きプランが格安だったので選んだが、さらに2,000円が返ってくるとなると破格も破格、超激安プランとなる。
悪くないな、とほくそ笑むわたしを尻目に、社長、もといオッサンはこう続けた。
「いやいや、お金を返してほしいわけじゃないんですよ」
(デ、デター!!!クレーマーの常套句!!)
思わずわたしは吹きだした。だがマスクをしているため、失笑はバレず。
「では、明日のお弁当を2つにしましょうか?」
まだ若いフロントマンは、しどろもどろになりながらも、返金以外の提案をした。
「いやぁ、さすがに一人で弁当を2個もらってもねぇ」
オッサンはニヤニヤしながらわたしを見る。若いフロントマンと、そのサポート役と思われる先輩とが、このオッサンは何が言いたいんだ?と言わんばかりの表情で立ち尽くす。
「んー、そうだな。たとえば明日の弁当を、数は1個で2個分ギュッとまとめた感じにできないかな?」
(どういう意味だよ)
「なんていうのかな、弁当は1個なんだけど、中身は2個分の価値があるというか」
(回りくどい言い方すんなよ、ハッキリ言ってみろ)
「つまり、明日の弁当をグレードアップできないかな?」
オッサンは真剣だ。客人に良い旅の思い出を残してもらおうと、思いつく最高の提案をひねり出した。
だがフロント側は目をまん丸くして固まっている。オッサンの背後にいるわたしも、あまりに図々しい提案に耳を疑った。
「え、えっと。できるかわかりませんが、やれるだけやってみます」
ふと我に返った若いフロントマンは、当たり障りのない返事をする。
「いや無理ならいいんです。いいんですけどね、せっかくだから今日の分を明日に上乗せして、ちょっと豪華な弁当になると嬉しいなと」
オッサンは酔っぱらっているせいか、同じことを何度も繰り返す。
やや恥ずかしくなったわたしは、マスクをずらして口元を見せると、オッサンの背後からフロントマンに向かって読唇術を使ってメッセージを送る。
(気・に・し・な・い・で)
フロントマンらはそれに気づくと、プッと吹き出しそうになるのを必死に堪えた。堪えながらも口元が緩みかけている。
「無理にとは言わないんでね。ただ、彼女に弁当が届かなかったからなぁ、その分はどうにかしてもらえるといいなぁ」
酔っ払いはウダウダと絡み続ける。
その背後からわたしは、両手を合わせ必死に謝罪する。
我々の寸劇を正面で傍観するフロントマンは、もはや目をつむりうつむいている。先輩のほうは微かに首を横に振っている。
(頼むからこれ以上笑わせないでくれ)
そう言いたいのだろう。
そんなこんなで、酔っ払いは
「じゃあ、そういうことでよろしく」
と、上機嫌で踵を返すとその場を去った。
もちろんわたしは、フロント陣に向かって小声で、
「ほんとゴメンね。なにもしなくていいからね」
と手を合わせ謝罪した。そして急いで酔っ払いの後を追った。
*
翌日、16時ジャスト。部屋のチャイムが鳴る。
ドアを開けるとそこには、正装に身を包む支配人が銀のトレイを持って立っている。
「この度は大変申し訳ございませんでした。私どもの全力を尽くした料理をお持ちしました。お口に合うと良いのですが」
その顔からは、謝罪というより誇らしさが溢れていた。間違いなく、自信作をこしらえたのだろう。
手渡された銀のトレイには、でっかい漆塗りの松花堂弁当の器と、炊き立ての白米、そして水中花の上に乗せられたビシソワーズがキラキラ輝いている。
ーー京都・吉兆顔負けの、見事な松花堂弁当だ。
このスペシャル弁当がどれほど美味かったか、というのは正直どうでもいい話。
それよりも、あの支配人の表情から伝わる誇らしさには、思うに、料理長含め従業員たちの想いが詰まった「渾身の作品」である、という自負を感じた。
ーーメニューにあろうがなかろうが、我々はここまでのことができ、ここまでの弁当が作れるんだ。
そんな職人たちのプライドが伝わる弁当だった。
そしてあの弁当を作り上げたことこそが、彼らが積み重ねてきたキャリアであり、センスであり、パワーであり、未だかつて成し遂げたことのない達成感につながったのではなかろうか。
松花堂弁当のどこをどうひっくり返してほじっても、出てくるのは完璧に調理された料理だけ。
朝食のビュッフェには並んでいなかったイクラやウニ、ボタン海老、トリュフなどが惜しげもなく詰め込まれている。
そして何より、炊き立てのもっちりとした白米が美味かった。
(これを知ったらオッサン、してやったりだろうなぁ)




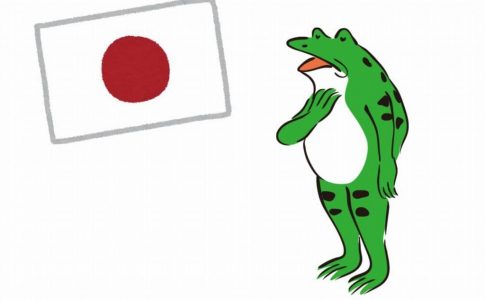


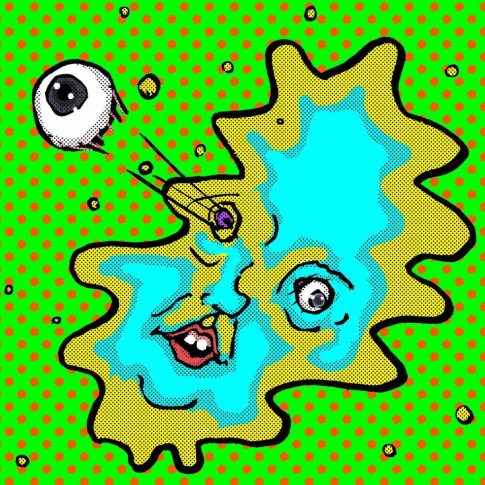


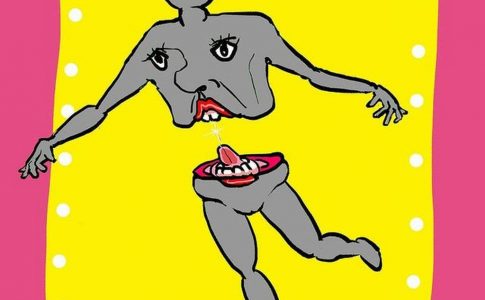










コメントを残す