人生で最も「人生の勉強」をさせてもらったのは、紛れもなく麻雀だった。
麻雀との出会いは、大学一年生。
正直、なんでバイト先に雀荘を選んだのか覚えていない。
ただ、雀荘というカルチャーは自分にフィットしていると感じていた。
大隈商店街にある雀荘「麻雀No. 1」で、私はバイトを始めた。
麻雀なんて打ったこともなければ見たこともなかった。
*
雀荘のバイトは2人一組でシフトが組まれる。
バイト初日は、法学部のマサさんとだった。
マサさんは、競馬と麻雀と巨人を愛するわりと古風なイケメンだった。
バイト2日目は、商学部の蹄さんとだった。
蹄さんは、学生当時からオッサンの風格のあるとても賢くエロい人だった。
バイト3日目は、第一文学部のアベとだった。
激弱のイジラレキャラを確立していたアベの顔面は、常に緑色だった。
バイト4日目は、法学部のヤスキとだった。
あまり本性を見せない物静かなタイプだが、酔っぱらうとはじける単純な人間だった。
バイト5日目は、社会科学部の岩崎さんとだった。
「カイジ」か「アカギ」を地で行く、生粋のギャンブラーだった。
このあたりが、雀荘バイトの主要メンバーだ。
バイト開始早々、派手にやられた私は初月のバイト代は0円だった。
そう、この先輩らは容赦なく私から金をむしり取った。
そして彼らの口癖は、
「本気で打たずに、強くなれるとでも思ってんのか?」
悲しいかな、週6~7でバイトに入っていた私の財力は、先輩らに完全に掌握されていた。
つまり、うまく調整されながらきっちりと搾取された。
しかし徹マン(徹夜で麻雀)後、全財産を搾り取られた私に、先輩たちは一風堂のラーメンをおごってくれた。
まぶしい朝日を浴びながら食べる一風堂は、今でも忘れられない味だ。
*
私に、競馬と麻雀と巨人(野球)を教えてくれたのは、まぎれもなくマサさん。
野球はさほど興味がわかなかったが、その他はドはまりした。
シフト上、土曜の徹マンに私とマサさんのペアで入ることが多く、朝になるとその足で府中か中山へ向かった。
そう、競馬場へ。
「おまえ、明日府中行くんだから金とっとけよ。飛ぶんじゃねーぞ」
マサさんは、私の競馬への余力(余財)を気にしてくれる優しい先輩だ。
私が飛びそう(註:払える点棒がなくなること)になると、うまいこと調整し生き残らせてくれた。
「おいアベ。オマエのリーチでコイツ(私)飛ぶぞ。
少しは考えて打てよバカ」
雀卓を蹴りながら、マサさんはアベを叱る。
「あ、ほんとだ。リーチやめます」
アベも素直に聞き入れる。
こうして私は、首の皮一枚残されるのだ。
キレイさっぱり飛ばして(終わらせて)くれればいいものを、決して殺さず生き地獄を味わわされるのだ。
*
そうこうするうちに、さすがに負けなくなってきた。
これまでは一ヶ月のバイト代が全額、先輩らのお小遣いに回っていた。
が、3か月くらいすると、バイト代が私の手元に残るようになった。
点数計算も覚え、相手に振り込まなくなり、最低限迷惑をかけない麻雀が打てるようになってきた、そんなある日。
*
場は南4局オーラス、私は断トツのビリ。
トップは「親」の蹄さん。
「2家」マサさん「3家」岩崎さん。
2家と3家は微差の接戦。
「ウマ」を採用しているため、この2人の争いはし烈だった。
※ウマ:4位→1位、3位→2位へ、別途点数を分配することで、より差をつけるルール
同時に、私は「ホンイツ(混一色)」がイーシャンテン(註:テンパイの一歩手前)だった。
リーチして裏ドラ乗ればハネマンあるぞ!と、ウキウキしながら手を進めて行った。
その時、
「おまえ、勝負の邪魔するなよ」
下家(シモチャ)で「親」の蹄さんが囁いた。
(リーチ・ホンイツで満貫(マンガン)確定、決して悪い手ではないのに、なぜ??)
蹄さんはカワ(註:場に出ている捨て牌のこと)を見つめたまま、見向きもしなかった。
場は静かに続いた。
「おまえさ、その手で倍満(バイマン)以上確定すんの?
じゃなければ、二人の勝負の邪魔をするな」
――背筋が凍った
「二人の邪魔」とは、2家のマサさんと3家の岩崎さんとの争いのことだ。
私の持ち点(数千点…)から、仮に岩崎さんから直で振り込んでもらったとしても、順位に変動はない。
マサさんから直で振り込んでもらえば、マサさんが3家、岩崎さんが2家となるが、私のビリは変わりない。
要するに、倍満を確定させずにリーチすることは、自分の順位が変動しないため無意味なこと(持ち点は増えるが)なのだ。
さらに「ウマ」が乗るため、2家と3家では大きな差が出ることを踏まえると、順位の変動を伴わないリーチは、2家3家争いをしている二人の邪魔をすることになる。
これは、ある意味「マナー違反」と言える。
そして、長い目で見ると自分自身の「ツキ」を逃がすことにつながるのだ。
蹄さんの手をみるとすべてツモ切り。
つまり、ある程度テンパイ(註:あがれる状態)させながら、アンパイ(註:相手に振り込まない安全な牌)を切っていたのだ。
オーラスでトップの蹄さんにとって、この2人に振り込みさえしなければトップキープで逃げ切れる。
しかし下手に振り込めば、手によっては「3家」まで見えてしまう。
つまり、ある程度のところで自分がツモアガリするつもりだったのだろう。
とは言うものの、後輩たちの熱いバトルも見ものだったため、しばらく流れを静観していた、という感じか。
――私は顔から火が出るほど恥ずかしかった
麻雀がこの1局のみで終結するゲームであれば、なにしたって構わない。
しかし、また次の半荘(註:ゲーム)が待っている。
もっと言うと、明日も明後日も麻雀は続く。
長い目でみた時、この場をどう乗り切るのかで訪れる未来が変わる。
勝てもしない、負けをやや減らす程度の盲目的なリーチでこの場を荒らすことが、自分の未来のツキを殺すことになる。
そういうことを私はまだ知らなかった
結局、私はベタ下りした。
蹄さんは非常に賢い人なので、あの発言自体が「ブラフ」だった可能性もある。
ただ「2人の勝負の邪魔をするな」という意見は、間違いなくその通りだと思った。
そこから、私の「麻雀人生」が始まった。
麻雀はセンスやテクニック、そして運が必要なゲームだ。
しかし、4人の得体のしれない人間どもが打つということは、自分一人の力ではどうにもならない、不可抗力の「流れ」が生まれる。
その流れをどう支配するか、どうやって流れに抗うのか、もしくは従うのか。
私は、空気(流れ)をかぎ分ける「嗅覚」を麻雀で鍛えられた。
いま、自分は進むべきか、耐えるべきか。
誰の足を引っ張ればいいのか、誰をアシストすればいいのか。
これは社会生活とまったく一緒だ。
本当に嬉しいのはバカ勝ちしたときではない。
私の “戦略” によって場が動いたときだ。
雀卓を囲む4人の運命を「私」が動かしたとき、物理的には表現できない喜びとエクスタシーを感じる。
それが、麻雀を打つ、ということだ。
社会人になってから麻雀を打つ機会がなくなった。
たまには、あのヒリヒリするような勝負の世界を思い出したいな、と思わなくもない今日この頃。






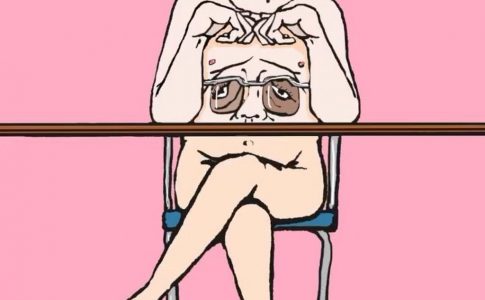














コメントを残す