スポーツ新聞社で働いていたとき、わたしはよく「お使い」に行かされた。コンビニやカフェは日常茶飯事、夕飯や夜食を買いに遠出させられることもあった。
中でも、わたしにしか務まらないお使いがある。それは競輪の車券を買う仕事だ。内勤記者たちの儚い希望を背負い、新橋駅前にある場外車券場「ラ・ピスタ新橋」へと向かう、重要な任務だった。
ラ・ピスタ新橋は会員制の場外車券場。会員であるわたしは、会員ではない記者たちから現金を預かり、すでに塗りつぶされたマークシートを握りしめ新橋へと送り出される。
今思えば記者たちのデスクには、ラ・ピスタのマークシートが山のように備え付けてあった。あれもわたしが大量に持ち帰ってきたものだ。
世間一般の認識として、「デスクに山盛りの競輪のマークシート」が公認の企業や業種は稀だろう。だがここは競輪の予想や取材が本業ゆえ、マークシートが散乱しているほうが仕事熱心といえる。
当時からすでにインターネットでの購入がメインだったが、わたしの周りで勝てる記者はほぼおらず、みんな口座は空っぽ。
しかも競輪のみならずJRA(中央競馬)、地方競馬、ボートレース、オートレースと、ありとあらゆる公営競技に手を出すため、口座が空になるのに時間はかからない。
そこで頼みの綱となるのがナイター競輪であり、わたしという足軽の存在である。
あれは一種の中毒だ。とにかく車券を買わなければ気が済まない、手が震える、イライラする。よく言えば職業病、正確にはギャンブル依存症。
だがそんな人生もアリだろうーー。
*
ある日のお使いのこと。某競馬記者に呼ばれ、ぼそぼそと耳打ちされる。
「ちょっと靴底を直してもらいたいんだ」
見ると革靴の底がすり減っている。ラ・ピスタのすぐそばにある靴修理屋ですぐに直せるとのこと。まぁついでだからいいですよ、と現金と革靴を抱えて新橋へと向かった。
先に靴を修理屋へ預けてから車券を買い、全員見事に外れたのを確認してから靴を受け取りに戻った。
「できましたぁ?」
ご高齢の店主に声をかける。
「おぉ、もう少しで終わりますよ。しかしこの靴の持ち主は有名人ですな」
ーー有名人?
たしかに靴主は競馬記者の中ではある意味有名だ。しかし、店主が思うような有名人とは違う。
遠慮がちにわたしは、
「んー、どうでしょう。そこまで有名ではないかと」
と答えると、店主は目を輝かせながらこう返してきた。
「芸能人、あるいは舞台俳優さんでしょうな」
ーーわたしは絶句した。
この店主は靴修理キャリアうん十年を誇る名手だろう。爪の中まで黒く染みついた汚れが物語っている。しかし、思いっきり勘違いしている。
「私くらいになるとね、靴を見ればわかるんですよ。その人が」
その瞬間、吹き出しそうになるのを必死にこらえた。
ーーいやダメだ、ここで笑ったら店主に失礼だ。
「靴はその人を表すんだよね。この人は高貴な家柄の人だ。多分テレビにも出ている有名な俳優さんじゃないかな」
ーーた、たしかに靴主は、土曜深夜の競馬番組に出演したことがある。
「ホラ、革が喜んでる。立派な人の足を包み込むことができて」
頼むからそれ以上言葉を発しないでくれ。わたしは嘘をつきたくない。今のところうんともすんとも答えていないわけで、まだ嘘はついていないーー。
そんな「立派な人」のお使いで車券を買い、靴底の修理に来たわたしは、なんとも微妙な気持ちになった。
ーー確かに、わたしが知らないだけで靴主は俳優なのかもしれない。さらに靴主が高貴な家柄かどうかなど、わたしには知る由もない。そして少なくとも、いま目の前で靴底を直している店主の「夢」を打ち砕く必要などまったくない。店主は立派な俳優の革靴を修理していることに酔いしれている。そして店主のキャリアからしても「そう」でなければならない。ここで事実を伝えることで店主に恥をかかせてはならない。
「はい。おっしゃる通り、有名な舞台俳優です」
わたしは堂々と嘘をついた。いや、嘘とは言い切れない。人は誰でも与えられた職業という「役」をこなす俳優なのだ。靴主だって家に返れば父であり夫でありペットの飼い主である。
そう、人生という舞台で主役を演じる俳優なのだ。
ーー帰り道、どうも腑に落ちないわたしがいた。
Illustrated by 希鳳









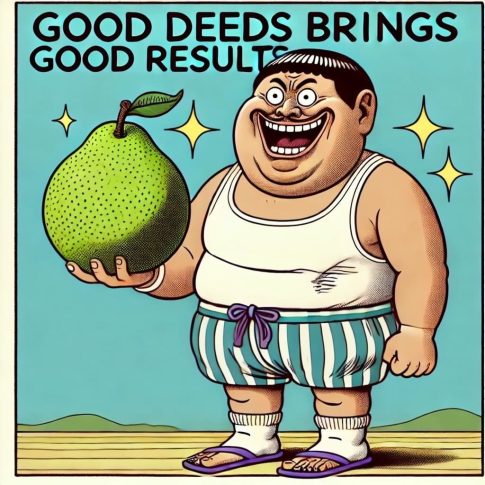











コメントを残す